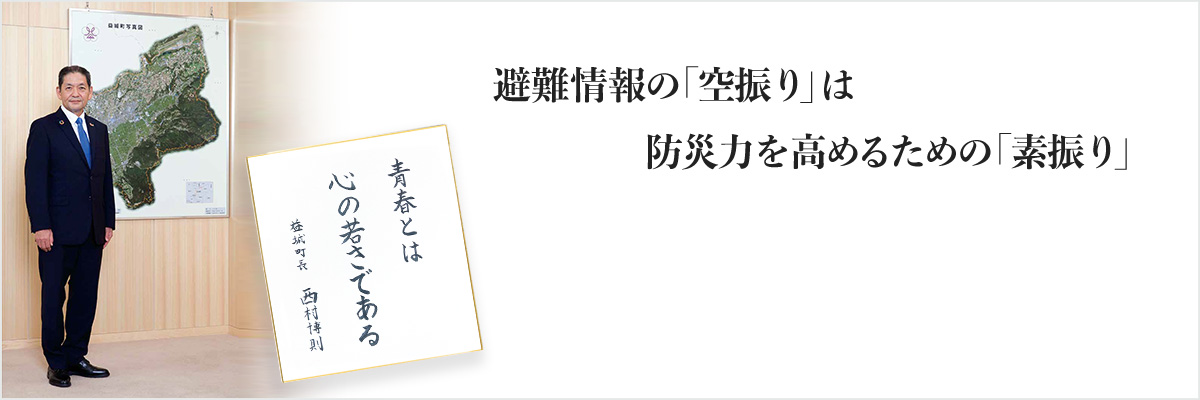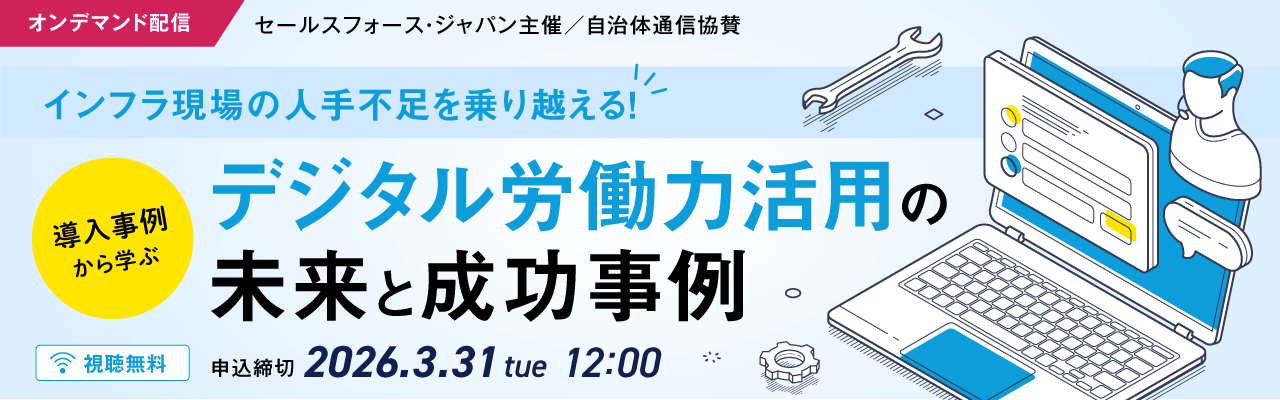※下記は自治体通信 Vol.52(2023年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。
平成28年4月、2度にわたる震度7の巨大地震に襲われ、甚大な被害を受けた益城町(熊本県)。それから7年。復旧・復興の道のりを歩む同町では、ひとつの大きな節目を迎えた。この5月、同町の防災機能の中枢を担う役場新庁舎が完成し、供用を開始したのだ。今後は、震災の教訓を活かした防災対策やにぎわいづくりに政策の主軸が移るという同町。震災の教訓をどのように活かし、どういった発展の姿を描いていくのか。町長の西村氏に聞いた。

役場とはどんな時でも、町を照らす存在であるべき
―平成28年の熊本地震から7年。復旧・復興の歩みは現在、どの程度まで進んでいますか。
まずは、これまで全国から多くのご支援をいただきながら復旧・復興を着実に進められたことに、あらためて心より感謝申し上げます。この間、災害公営住宅の建設や宅地復旧のほか、町道や公共施設などの整備といったハード面の早期復旧を先行して進めてきました。これらの復旧事業はそのほとんどが完了し、現在は「震災前よりも輝かしい町をつくる」という創造的復興に大きく舵を切っているところです。
―今年5月には、創造的復興の象徴でもある役場新庁舎が供用を開始しました。
新庁舎に関しては、「安全安心の拠点」として建て替えを進めてきました。旧庁舎が地震で大きな被害を受け、本来の災害対策本部機能を担えなかったという苦い経験があったためです。建て替えにあたって私は3つの条件をつけました。第一に、大地震の際にも災害対策本部機能を失わない、安全な免震構造を備えること。第二に、町民が休日でもいつでも気軽に立ち寄れること。そして第三に、夜には明かりが灯り、町の未来を照らす灯台のような庁舎であることです。先の地震の際には、被災直後の停電で真っ暗な中でも300人ほどの町民が、不安を抱えながら役場をめざして集まってきました。その経験から、役場はどんな時でも町を照らす存在でなければならないと考えたのです。
住民参画を重視した「益城町復興計画」
―防災力を強化した新庁舎は、今後の都市計画でも重要な役割を果たしそうですね。
ええ。復旧・復興を進める中で、当町では防災対策事業の推進と同時に、将来の人口減少にも備えた「防災コンパクトシティ計画」を進めています。この計画において庁舎は象徴的な存在になります。この都市計画では、過去の水害の経験も活かし、「浸水ゾーン」や「居住誘導ゾーン」といった区画を設定するゾーニングの考え方を導入し、防災・減災対策の強化を図っています。今年7月、早くもこの計画が試される場面がありました。2度にわたって発生した線状降水帯の影響により、当町は過去に経験のない記録的な大雨に見舞われ、河川は氾濫し、道路や住宅、農地、農作物などに甚大な被害をもたらしたのです。しかし、町民には犠牲者どころか、けが人さえも一切出ませんでした。それは、過去の被災経験を活かした町民の迅速な避難行動の賜物であったと同時に、防災コンパクトシティ計画の有効性や必要性が図らずも証明されたものだと受け止めています。
―一連の復旧・復興事業において大事にしたことはありますか。
この間の復旧・復興の取り組みは、指針となる「益城町復興計画」の策定から着手したわけですが、そこでは一人でも多くの町民が参画するというプロセスをもっとも重視しました。各団体の代表を集めて町が議論を主導する方法論もありえましたが、建物ひとつにしても、町が一方的につくった施設には町民も愛着がわきませんし、大事に使われることもないからです。実際に、発災から3ヵ月にわたって、合計21回、延べ約1,600人の町民の皆さんと意見交換を重ねました。その経験が、町内各地区での「まちづくり協議会」立ち上げにつながりました。
―その成果は、どういったかたちで表れていますか。
この意見交換会をきっかけに、特に次代を担う若者世代の想いや声を反映したいと考えていたところ、若者世代が復興とまちづくりについて議論するワークショップ「益城町未来トーーク」が立ち上がり、さまざまな取り組みが実践されています。たとえば、未来トーークから町に提案された「復興大使制度」の創設です。これは芸能、スポーツ、文化芸術などの分野で活躍する方々にご協力をいただき、町の創造的復興に関する情報を広く発信してもらう取り組みです。また、若手職員の発案で企業との連携によるPR動画を作成しており、その動画は10万回以上再生されています。さらに、若手職員の発想による益城の米を原料にした焼酎や、東海大学の学生たちと協力してつくった地元産のスイカを使用したアイスなどの特産品の開発にも成功しています。震災を契機に若者がまちづくりに参画できる環境づくりが進んできたことを、大変うれしく思っています。

「スタンドプレーはいらない」と肝に銘じた被災経験
―今回の震災から、どのような「気づき」が得られましたか。
教訓とともに、あらためて気づかされたのは、「トップとしての決断の重さ」です。1回目の地震の際、町民約2,000人が総合体育館に避難してきました。メインアリーナには約1,000人を収容するスペースがあったのですが、実はその時点で、体育館の天井パネルが数枚はがれており、私は「収容は危険」と判断しました。その判断は大きな批判を受けたのですが、2日後の2回目の地震で天井パネルはすべて崩落してしまいました。もし、町民を収容していれば、多くの死傷者が出たことは間違いありません。その時に、町長としての判断の重さを痛感するとともに、「スタンドプレーはいらない」と肝に銘じました。
ただ一方で、決断すべき時は大胆に決断することも必要です。たとえば避難情報を出す際、それが「空振り」に終わることを恐れる気持ちが起こってしまうものです。しかしその時は、「これは空振りではなく、素振りなんだ」と捉えるようにしています。野球やバドミントン、剣道などは素振りを重ねるほど力がつきます。素振りで防災力が向上したと考えることが大切です。
将来の町の姿を見据えた「攻め」の行政へ
―今後の町政ビジョンを聞かせてください。
今年3月に阿蘇くまもと空港の旅客ターミナルがリニューアルオープンを迎えたのを皮切りに、4月に東海大学阿蘇くまもと臨空キャンパスが開校、さらには今後、県主体の知的産業集積計画「UXプロジェクト」や台湾の半導体企業大手TSMCの進出など、当町周辺を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。これを好機とし、にぎわいの架け橋となるべく当町でも土地区画整理事業や産業団地造成事業を推進し、将来の町の姿を見据えた「攻め」の行政運営に転じようと考えています。そして町の将来像として、総合計画が掲げる「住みたいまち、住み続けたいまち、次世代に継承したいまち」の実現のため、全力で取り組んで参ります。