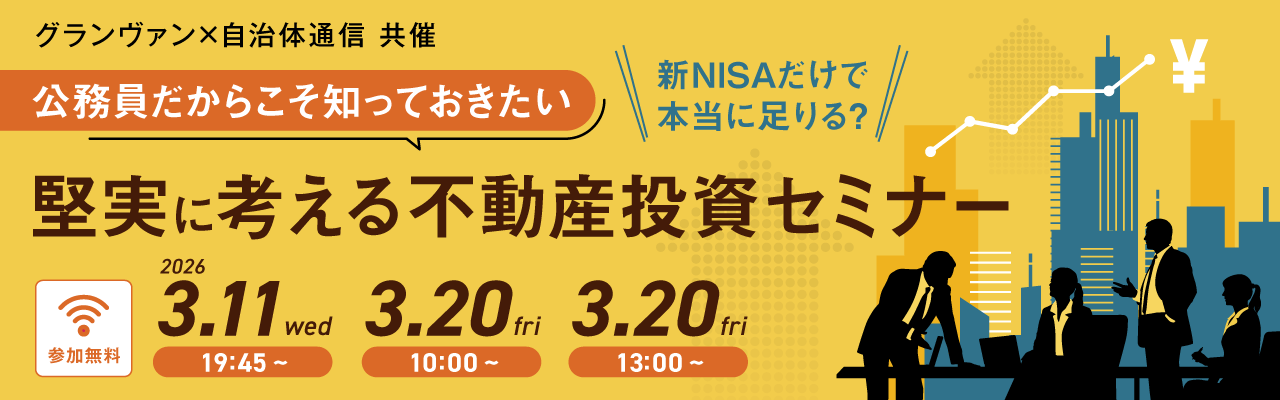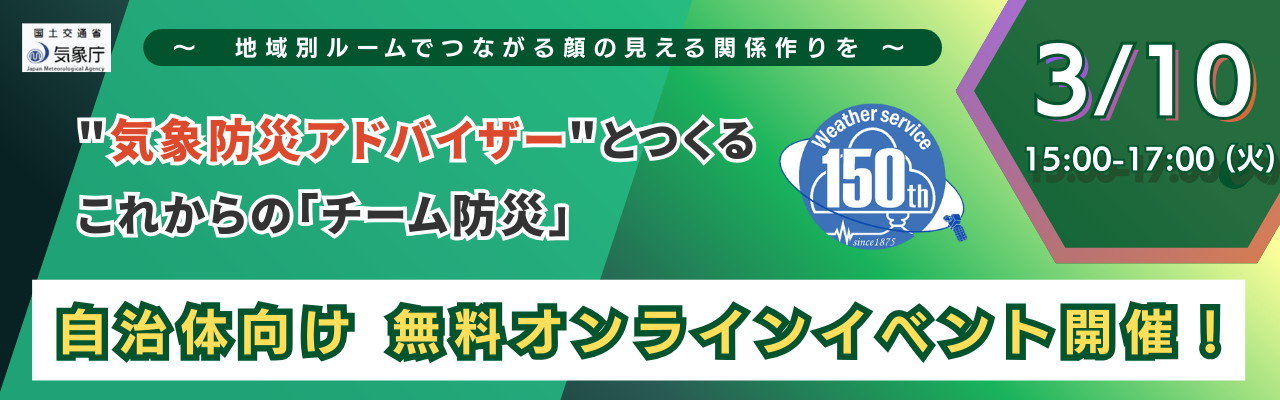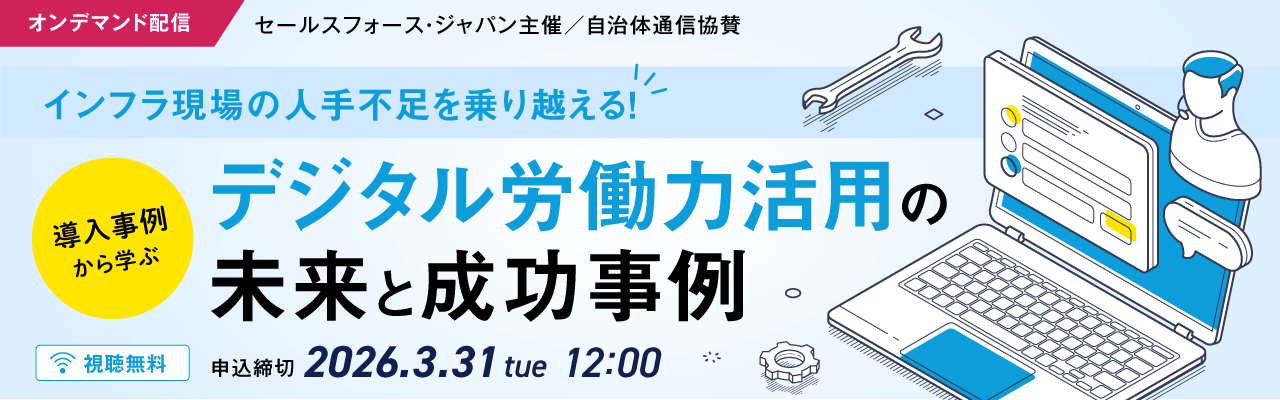民間企業が介入することで 「改善」にまで踏み込んだ認知症対策

筑波大学の矢田幸博教授が主体となって実施された、「認知症リスク測定会」。約500人の高齢者を対象に測定を行い、認知症の疑いなどさまざまな症状を示す高齢者に対し、民間企業3社の商材による介入試験を実施。認知機能に影響するとされる「水素吸引器」、頻尿・軽失禁に対処する「紙おむつ」、睡眠効果が期待される「紅茶」を希望者に使ってもらい、その効果を検証した。
鹿児島県西之表市 の取り組み
民間企業が介入することで 「改善」にまで踏み込んだ認知症対策
日本全体で「2060年には高齢化率が40%程度になる」と予想されるなか、西之表市(鹿児島県)では、2025年との予想に。同市では健康寿命の延伸に向けた取り組みが急務であり、その一環として「認知症リスク測定会」を平成29年に実施したことを『自治体通信』16号で紹介した。同市の担当者ふたりに、その後の取り組みについて聞いた。
※下記は自治体通信 Vol.17(2019年4月号)から抜粋・一部修正し、記事は取材時のものです。
鹿児島県西之表市データ
人口: 1万5,390人(平成31年2月末現在) 世帯数: 8,056世帯(平成31年2月末現在) 予算規模: 148億3,379万6,000円(平成30年度当初予算) 面積: 205.66km²概要: ロケット基地を有する種子島の北部に位置し、東・西・北は海に面し、南は中種子町と接しており、島の総面積の約45%を占めている。歴史は古く、縄文・弥生時代の遺物が出土。鉄砲伝来の地であり、最近ではサーフィンの聖地として有名。農業、漁業といった第一次産業が盛んで、安納いもの発祥地であり、さとうきびを原料とする黒糖や焼酎、トコブシ、トビウオなどの海産物も豊富であり、『種子(たね)ばさみ』は特産品。
―測定会の後、住民の健康増進に向けての意識は変わりましたか。
山中:西之表市全体で「どう変わったか」という判断は難しいですが、測定会に参加し、矢田先生からカウンセリングを受けた高齢者からは「どういうところに気をつけなければいけないかを知ることができた」という話は、個人的には聞いています。
森:認知症の人やその家族、あるいは認知症に関心がある人を対象に、お茶を飲みながら語り合う「認知症カフェ」という集いを2ヵ月に1度開催しているのですが、毎回約30人が参加。そうした参加者は、少しずつですが増えているのではないでしょうか。
そのほか、地域サロンや体操教室など、ボランティアを含めた参加者も増えていますので、地域の輪は広まりつつあると思います。
介入試験の結果を活かした市ならではの取り組みを
―健康増進における今後の方針を教えてください。
山中:現在、介入試験の結果分析を矢田先生に行ってもらっているところです。そのデータ結果があきらかになれば、市が高齢者に推奨している「元気アップ体操」に組み合わせるなど、新たな取り組みに活かしていきたいと思います。
森:まだ正式な結果報告は受けていませんが、おそらく水素吸引や紅茶の香り、紙おむつの使用で、症状になんらかの影響が出ている人が現れていると思うんですね。そうした高齢者の協力をえて事例として発表するなど、健康増進の取り組みを広く伝えていけるのではと考えています。
我々がどんな取り組みをしても、最終的に住民の意識が高まらなければ、本当の健康増進にはつながっていきません。こうした介入試験も含め、引き続き住民の意識を高める取り組みを行っていきます。

測定会に参加し、認知機能対策のために現在も「水素吸引」を行っている高齢者に話を聞いた。
※内容は個人の感想です