マイナンバーカードの活用で広がる行政サービスの可能性
マイナンバーカードの発行開始から10年目となる令和7年、人口に対する保有枚数比率は約8割まで高まりました。同年度からは、「マイナ免許証」の運用が開始されるなど、マイナンバーカードでできることはさらに増えていく見通しです。また、職員の業務効率化や住民サービスの向上を目的に、マイナンバーカードを活用した独自の取り組みを進める自治体も増えてきています。本記事では、マイナンバーカードの普及状況や、マイナンバーカードを活用するメリット、自治体の取り組み事例などを紹介します。
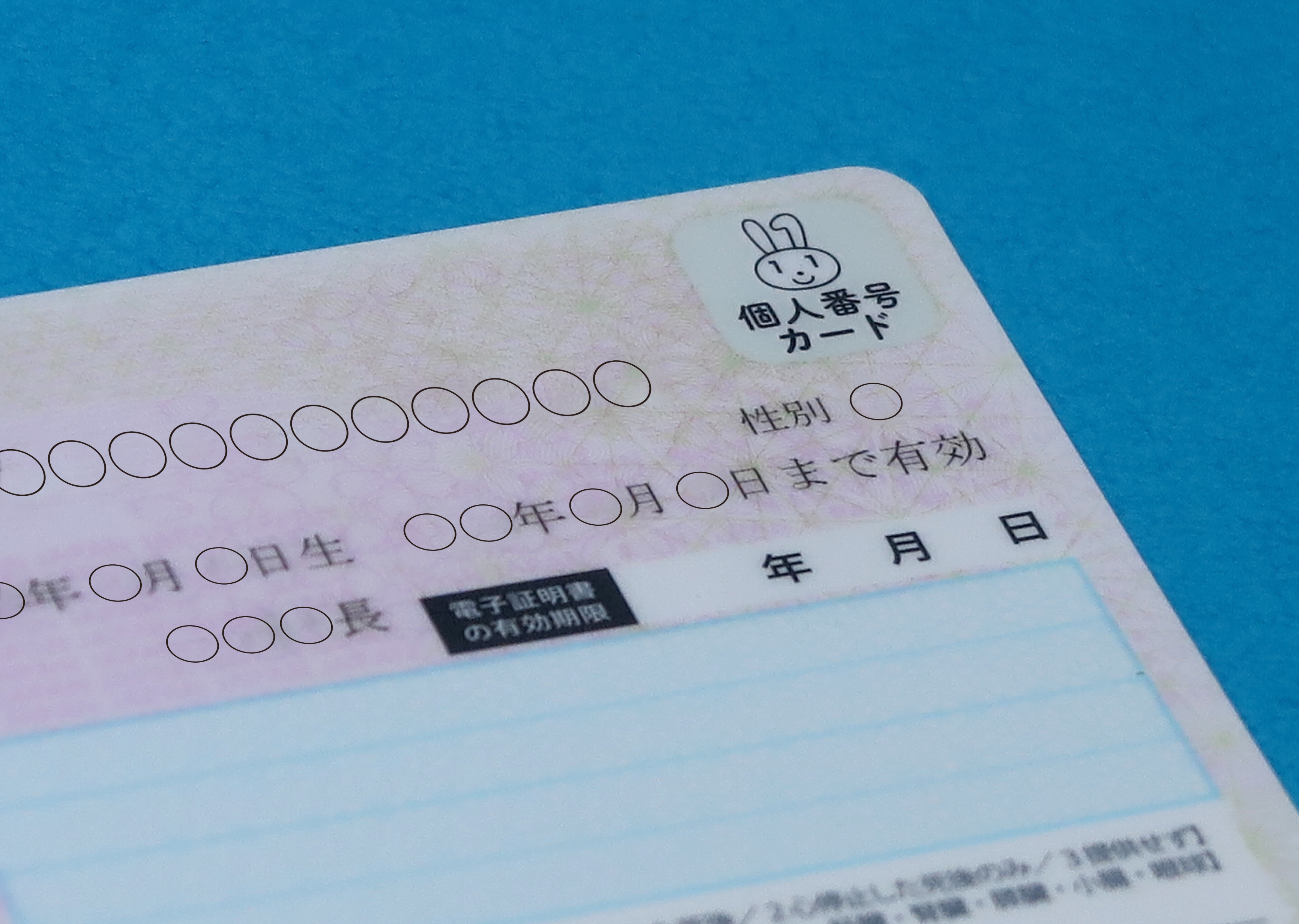
マイナカード保有、人口の約8割に
総務省の発表によると、令和7年1月末現在のマイナンバーカードの保有枚数は9,695万1,056枚で、人口に対する割合は77.6%です。保有枚数率を都道府県別に見ると、15の県が80%を上回っており、最も高いのは宮崎県で84.2%でした。都道府県別の保有枚数率の上位10自治体は以下の通りです。
1位 宮崎県:84.2%
2位 鹿児島県:82.0%
3位 秋田県:81.6%
4位 佐賀県:81.2%
5位 山形県:81.2%
6位 富山県:80.9%
7位 山口県:80.8%
8位 岐阜県:80.7%
9位 福井県:80.6%
10位 島根県:80.6%
保有枚数は、交付枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたもの。交付ベースで見ると、平成28年1月の交付開始以来、枚数は累計1億679万4,806枚にのぼり、人口に占める割合は約85%まで高まりました。マイナンバーカードの普及拡大には、2万円分のポイント・キャンペーンや、健康保険証を廃止してマイナ保険証に一本化するという施策が奏功したとされています。
マイナカードでできること
マイナンバーカードに記載される数字12桁の個人番号(マイナンバー)は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。総務省では、マイナンバー制度について、「行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤」と説明しています。
また、マイナンバーカード関連システムの開発・運営を担う地方公共団体情報システム機構(J-LIS)では、「マイナンバーカードでできること」を、以下のようにあげています。
- 個人番号を証明できる
- 1枚で本人確認ができる
- 証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
- コンビニで住民票の写しなどの公的な証明書を取得できる
- 健康保険証として利用できる
発行開始から10年目となる令和7年からは、マイナンバーカードでできることはさらに増える見通しです。この春以降は、マイナンバーカードと運転免許証を一体化させた「マイナ免許証」が始まるほか、マイナ保険証のスマートフォンへの搭載、マイナ保険証を活用して救急隊員が搬送する患者の通院歴や服用中の薬などの情報を確認できるようにする「マイナ救急」など、新たな行政サービスが相次ぎ始まる予定となっています。
行政がマイナカードで活用できる「3つの箇所」
マイナンバーカードには、大きく分けて以下の3つの利用箇所があります。
① カード券面(個人番号)
② ICチップの空き領域
③ 電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)
このうち①の「カード券面」に関して、表面は、金融機関など本人確認が必要な窓口における本人確認書類として利用することができます。裏面には個人番号が記載されています。
そして、②の「ICチップの空き領域」と③「電子証明書」の利用は、マイナンバーカードを「行政の効率化」や「国民の利便性向上」につなげるために、有用な機能と言えるでしょう。
マイナンバーカードは非接触型認証に対応しているため、ICチップの空き領域機能を活用することで、自治体職員は、住民にカードを専用の認証端末にかざしてもらうだけで、さまざまなサービスを提供できる仕組みを構築することができます。
この空き領域は、市町村・都道府県等は条例で定めるところ、また国の機関等は総務大臣の定めるところにより、それぞれの独自サービスのために使用できます。ICチップの空き領域を活用することで、たとえば、図書館の貸し出しカウンターを無人化したり、災害時に避難所の受付にマイナンバーカードを提示してもらったりすることで避難世帯員全員を一括で受け付けられるといった活用が可能になります。
さらに、マイナンバーカードは、「公的個人認証サービス」(JPKI)を介すことで、住民はマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンを使うだけで、さまざまな関連サービスの利用や申し込みをオンライン上で完結できるようにもなります。これによって申し込みや手続きのオンライン化の促進につながれば、自治体職員は業務効率の向上を目指せるようになるでしょう。
公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用し、オンラインで利用者本人の認証や契約書等の文書が改ざんされていないことの確認を公的に行うことで、安全・確実な本人確認を実現できるサービスです。行政機関だけでなく、民間企業の各種サービスにも導入できるため、住民サービスの向上に向けたDX推進の取り組みとして、公民連携の事例が数多く生まれています。
電子証明書のうち、「署名用電子証明書」には、氏名、住所、生年月日、性別の「基本4情報」が記載され、e-Taxの確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。また、「利用者証明用電子証明書」は、マイナポータルやコンビニ交付の利用時など、本人であることを証明する際の手段として使えます。
下からは、マイナンバーカードを活用し、職員の業務効率化や住民サービスの向上につなげた自治体事例を紹介します。

【豊島区】避難所運営の効率化に道筋
豊島区(東京都)では、東日本大震災の際に、帰宅困難者を含めて1万人を超える避難者を受け入れた経験があるほか、その後の台風被害などでも避難所を開設した経緯がある。そのなかでは、避難所の入所受付時の混乱によって施設の前に長蛇の列ができてしまうといった、避難所の運営をめぐる課題を感じていた。 そこで同区は令和2年秋に、区内全35ヵ所の避難所の混雑状況を可視化し、空き施設へと誘導する「避難所混雑可視化システム」を導入。その後、同システムを開発した民間事業者から新たに「避難所マネジメントシステム」の提案を受け、令和6年には、その導入に向けて実証実験を行った。このシステムは、従来、入所者が紙へ記入し、職員がデータ入力してきた入所者名簿の作成をデジタル化し、避難所受付やその後の避難所運営を効率化するもの。受付時にマイナンバーカードから「基本4情報」を読み取ることで入所手続きを迅速に行い、避難者のスムーズな入所と受付職員の業務負担軽減を同時に図った。 実証実験は令和6年10~11月に2回、実施。1回目は避難所運営に携わる職員に、2回目は区民数十人に参加してもらい、発災時を想定した受付手続きを再現した。 |
|---|
実証実験の結果では、従来紙への記入とデータ入力で合計約100秒かかっていた受付時間が、マイナンバーカードの読み取りで24秒に、アプリからは7秒と大きく短縮されたそうです。同区の担当者は、「発災時には実験とは異なる混乱も予想されるが、職員の経験やスキルを問われることなく迅速な受付ができるのは大変心強いと感じた」と話しています。区民の一部からも過去に、「入所管理をデジタル化できないか」との要望を受けていたため、参加した区民からもシステムを評価する声が相次いだということです。
【佐賀市】「スーパーアプリ」で住民サービス向上
佐賀市(佐賀県)では、令和4年3月に佐賀市DX推進方針を策定し、同年7月には、スマートシティ宣言を発出。「スマート・ローカル!SAGACITY」をスローガンに佐賀市版DXを推進している。そのなかでは、世帯保有率が9割を超えるスマートフォンに着目。スマートフォンを市民・地域・企業・行政をつなぐ「デジタルタッチポイント」として、さまざまなサービスを1つのアプリで提供する「スーパーアプリ」を民間事業者に委託するかたちで開発し、令和5年6月にリリースした。 |
|---|
この佐賀市のスーパーアプリには、「ごみ収集日のプッシュ通知」や「電子申請」「図書館利用カードのデジタル化」「防災情報提供」など、さまざまな機能が並んでいます。このなかで、スーパーアプリ活用の利便性を高める仕組みとして実装しているのが、マイナンバーカードの公的個人認証機能を活用した「デジタル市民証」という機能です。
デジタル市民証は、アプリ上において、二次元コード方式で発行されます。ここには、氏名、住所、生年月日の情報を保有。避難所やイベントなどでの入場受付に利用できるものとしています。この機能によってユーザーが佐賀市民であることを証明できるため、電子地域振興券と連携させるなど、観光・地域経済活性化策への活用も期待されているそうです。
さらなる行政サービスの向上へ
デジタル庁によると、マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービスを導入している民間事業者の数は、令和7年2月3日現在で652社に上っています。そのなかには、上記で紹介した事例のように自治体との共同によって独自のサービスを生み出している企業が数多くあります。さまざまなオンライン申請機能を職員がノーコードで構築してSNSの『LINE』上に実装できるシステムなど、自治体向けに特化したプラットフォームを精力的に開発・提供している企業も少なくありません。
マイナンバーカードの普及が進んだいまこそ、こうした民間企業のアイデアや知見、技術を活用しつつ、さらなる職員の業務効率化や、住民サービスの向上を目指すことが、自治体には求められてくると言えるでしょう。

【参考】
総務省「マイナンバーカード交付状況について」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html
総務省「マイナンバーカード」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html#merit
デジタル庁「マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス(JPKI)導入事業者及び事例一覧」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/private-business/jpki-introduction/mynumbercard-user-list


.png)

