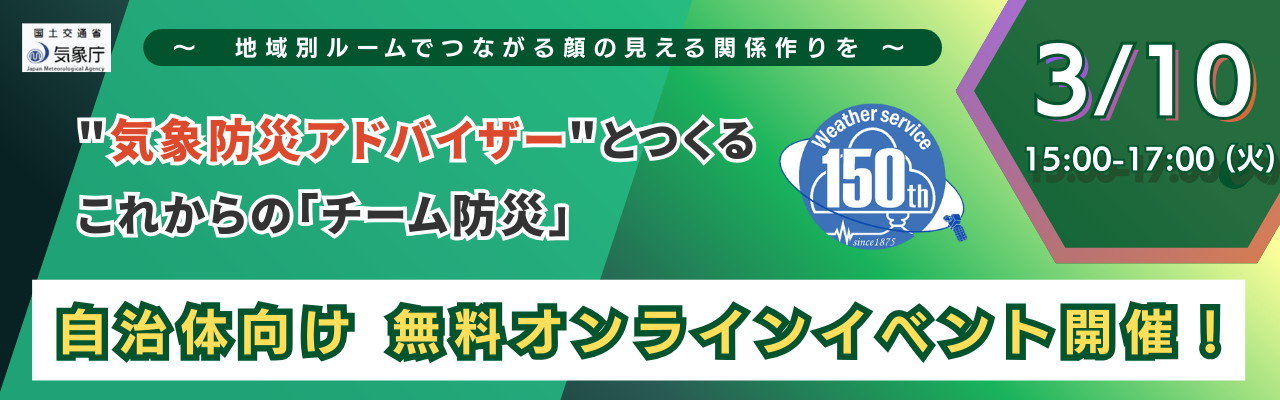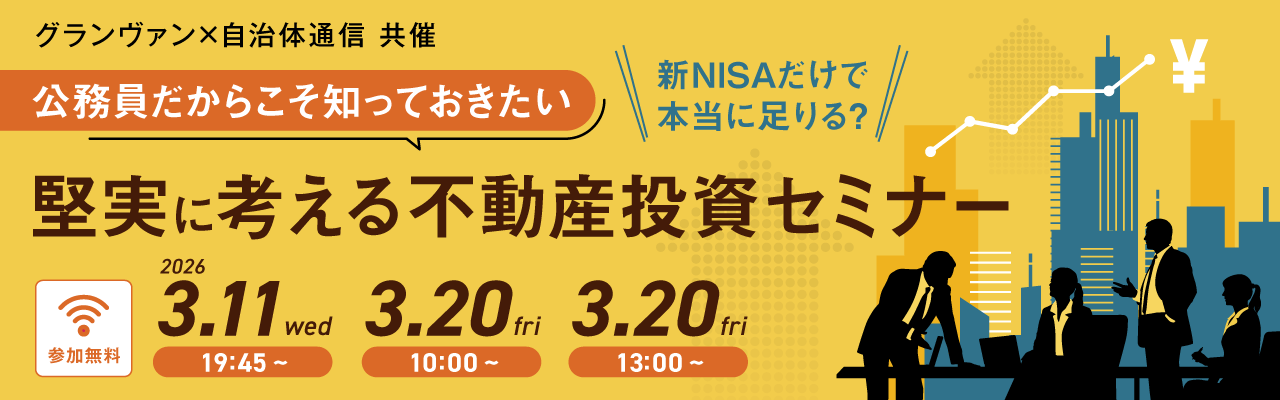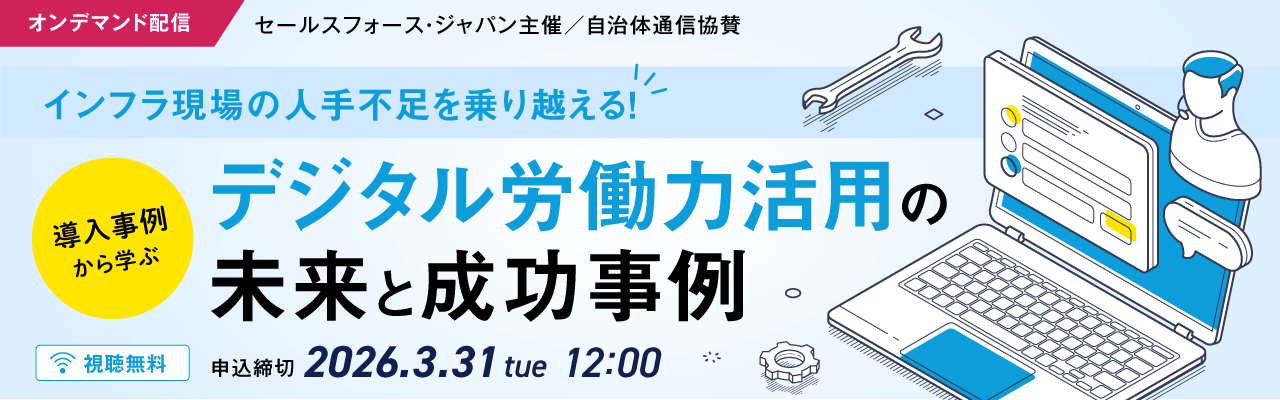【地域活性化】地域創生に取り組むキーワードは、「魅力発信」と「誘客促進」
(ANAグループの地域創生 / ANAホールディングス(ANAあきんど))


※下記は自治体通信 Vol.69(2025年10月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。
人口減少や高齢化が進む自治体において、各地域が持つ特性を活かした持続可能な社会をめざす「地域創生」の取り組みが進められている。ただ、「具体的になにをすればいいかわからない」という声もある。そうしたなか、ANAグループにおいて、自治体の地域創生をけん引しているANAあきんど代表の原氏は、「地域の『魅力発信』と『誘客促進』が重要だ」と話す。同氏に、その理由に加え、地域創生に取り組むポイントなどを聞いた。

単に航空便を増やしても、効果は表れない
―地域創生のなかでも、地域の「魅力発信」と「誘客促進」に注目した経緯を教えてください。
我々は、航空機を使って旅客や貨物を安全・快適に国内外に輸送する役割を担う航空会社グループです。そこで、集客を図りたい各自治体と一緒にキャンペーンを行うなど、さまざまな共創に取り組んできました。当然、各自治体は我々に対し、より多くの旅客を域内に運んでくれることを望み、「飛行機の便数が増えれば、旅客の数も増える」と期待されるケースも多いです。しかし、旅客がその土地に行く需要がない限り、便を増やしても直接効果は表れません。そこで、まず取り組むべきは、地域の魅力を発信することであり、それから誘客促進を図ることが重要だと我々は考えているのです。
―自治体が、2つの観点で地域創生に取り組むポイントはなんですか。
大きく、4つのポイントがあると我々は考えています。1つ目は、観光資源の魅力づくりです。よく言われることですが、地元の方々が当たり前の風景や食べ物だと思っているものが、ほかの地域や国の人たちには感動される資源になりえます。これは、日本全国、どこの地域にも当てはまることです。そうした資源の掘り起こしおよび磨き上げを行い、それを地域の事業者とも関係性を強化しつつ、旅行商品として開発する。いわば、地域の認知度を高める起爆剤をつくるのです。
―2つ目はなんですか。
最初に取り上げた地域への誘客促進、そのための仕組みづくりです。たとえば、複数の交通手段を連携させてルート検索・予約・決済までをワンストップで提供するサービス、さらにはクーポンと連動した地図アプリなどで利用者の周遊を促すような観光DX、そして多言語対応、接客面の人材育成などです。そうして、交流人口・関係人口を増やす仕組みを整えるのです。
―3つ目はなんでしょう。
地域産品の商機拡大です。誘客促進のためには、地域産品を手に取ってもらい、実際に食べてもらうことも効果的です。そこで、地域事業者と連携して地域産品を活かした商品やサービスを開発し、物流環境や販路開拓の環境を整える必要があるのです。これは、地域経済の活性化にもつながります。
―4つ目を教えてください。
地域外で認知拡大・プロモーションを行うことです。ターゲットを明確化したうえでPRイベントやフェアを行ったり、メディアやSNSなどを通じた情報発信をしたり、タイアップ企画を実施したりする。そうして、地域ブランド力をさらに高めていくのです。
地域創生には、こうした4つのポイントの相互連携・同時推進が重要です。しかし、自治体がそれらを個別の民間企業に依頼すると施策間の連携が損なわれかねません。そこで、私たちはグループ全体のネットワークとノウハウを活用し、そうしたサービスを一貫して自治体に提案しています。

ネットワークを活かし、さまざまなサービスを提案
―実際に、どのようなサービスを提案しているのでしょう。
我々はおもに、「観光振興」「産農振興」「イノベーション」「ふるさと納税」の4つのアプローチによるサービスを提案しています。まず、観光振興のサービス例のひとつに、スマホアプリ『ANA Pocket』があげられます。これは、徒歩、自転車、自動車、電車、飛行機などの移動によりポイントが貯まるスマートフォンアプリです。貯めたポイントでハズレなしの「ガチャ」を引くことで、ANAのマイルや各種クーポン券などと交換できるのが特徴です。また、アプリから得られた人流データを分析し、観光施策に活用することも可能です。
産農振興では、「スピード輸送」のサービスがあげられます。
―具体的に教えてください。
航空機を活用したスピード輸送のサービスです。輸送の手段はたくさんありますが、スピードに関しては飛行機に勝るものはないでしょう。これを活用すると、たとえば地方の朝採れたての作物を、その日中に都市部のスーパーに並べることができます。新鮮でおいしい食材を提供できるのはもちろん、それを味わった人の「地元に直接行って食べたい」というニーズ喚起も期待できます。
イノベーションのサービス例としては、『ユニバーサル地図/ナビ』を紹介します。こちらは、地域のバリアフリー情報を集約・発信する地図・ナビゲーションサービスです。高齢化が進む日本では、「旅に出たい」と考えても、足が弱って階段の上り下りもきついから外出をためらう人も多いでしょう。そういった人たちの背中を後押しするようなサービスです。
また、それら以外のサービス事例としても、ファンクラブツアーの企画や空港のデジタルサイネージを活用した情報の発信、人材研修、オーバーツーリズム対策も含めたインバウンド促進など、さまざまなサービスを自治体に提案しています。
―ふるさと納税のサービス例も聞かせてください。
「ANAのふるさと納税」があります。これは当グループのふるさと納税サイトで、専門機関の評価結果で3年連続顧客満足度1位*を獲得しています。現在1,100を超える自治体と契約し、利用者ニーズが高い、肉・魚介類・米だけでなく、実際に地域に旅行する際に使える「ANAトラベラーズクーポン」などの返礼品を取り揃えることで、関係人口の増加や観光誘客にも貢献しています。
*3年連続顧客満足度1位 : 令和5~7年 オリコン顧客満足度®調査『ふるさと納税サイト』ランキングより

一番大事なのは、地域が元気になっていくこと
―なぜそうしたサービスを自治体に提案して、自治体の地域創生を支援しているのですか。
人口減少が進むなか、多くの自治体が税収減など切実な問題に直面しているのは周知のとおりです。日本経済自体も、長年デフレが続いた影響で、全体的に沈滞しています。そうしたなか、一番大事なのは、地域が元気になっていくことだと我々は考えているのです。これはなにも、社会貢献の要素だけではありません。我々ANAの航空事業は、地域の元気があってこそ成り立つものですから。
―自治体との地域創生の取り組みが、ANAグループの企業成長にも好影響があるということですね。
そのとおりです。たとえすぐにではなくても、後々に利益があがる仕組みを考えていくことが重要です。社会貢献を重視しすぎて、長年赤字の事業を続けた結果、撤退してしまえば、それこそ自治体や地元の皆さまにも迷惑をかけてしまいます。ですから私は、地域創生に関する事業で儲けることが悪いとは思いません。「社会貢献」と「利益」のバランスを考えつつ、持続的な地域創生につながるサービスを提供するように意識しているのです。
地域創生で重要なのは、「支援」ではなく「共創」
―地域創生に関する、今後の取り組み方針を教えてください。
現在、ANAグループでは、31自治体と連携協定を締結しています。そして、地域創生を支える窓口として、全国に33支店があります(下図参照)。これからも引き続き、全国の航空ネットワークとノウハウを活かすことで、持続的な地域創生の取り組みを自治体と共に行っていきたいですね。そこで重要なのは、我々が一方的にサービスを提案するのではなく、自治体や事業者の皆さまなどを含めた地域の方々と対話をし、共に取り組むことです。そういう意味では、我々は「支援」ではなく「共創」を大事にしていると言えるでしょう。
団体型の旅行から個人旅行へと旅行スタイルも変化し、インバウンドも増加するなか、我々も航空券だけ販売してお客さまをお運びするだけの事業では成り立たないことを十分認識しています。我々は、地域創生を重要な事業の柱と捉え、各自治体と共創していきます。


| 設立 | 令和3年4月 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 723人(令和7年4月現在) |
| 事業内容 | 地域創生事業、航空セールス事業 |
| URL |