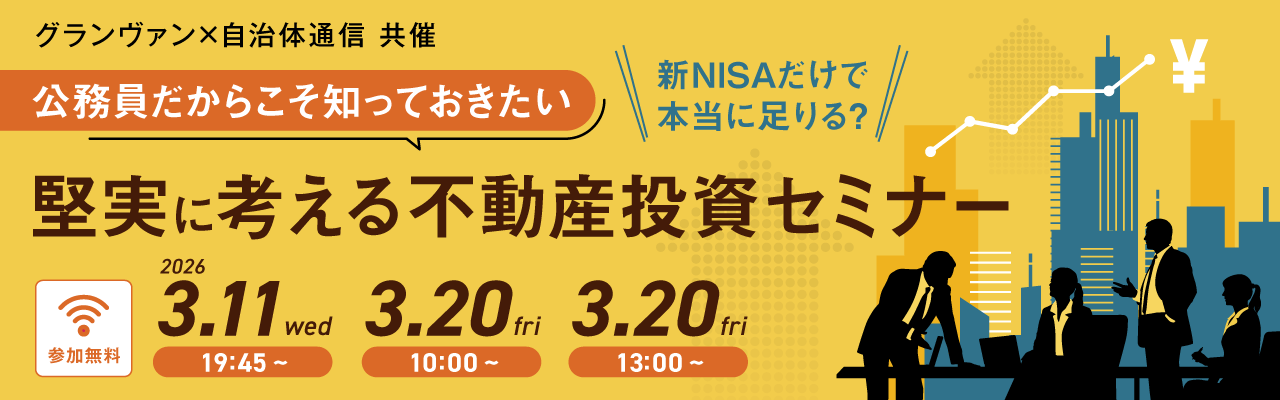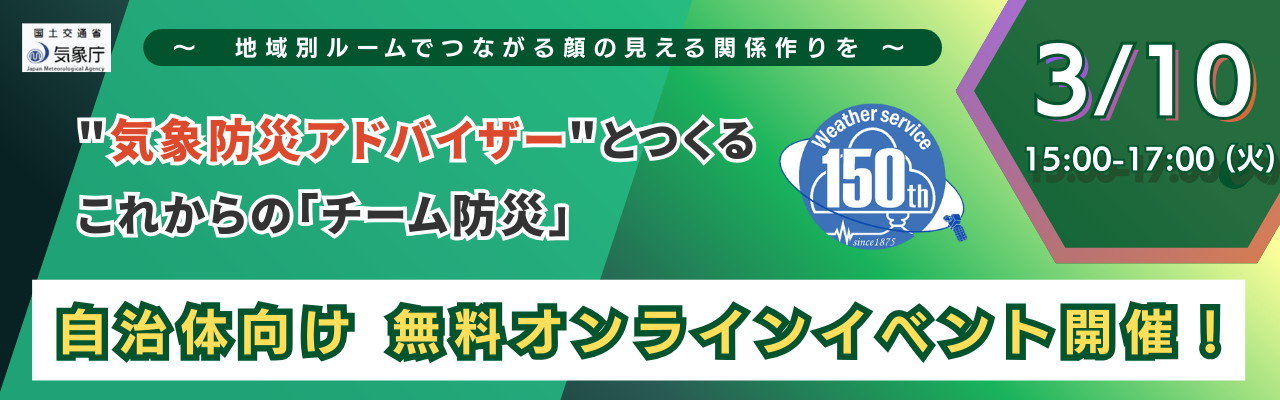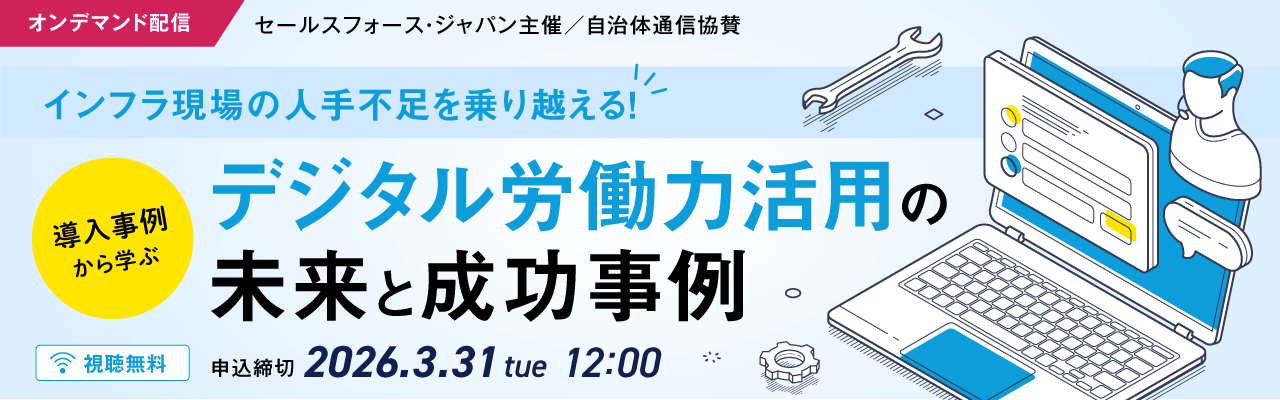【万博国際交流・地方創生】万博を「地方創生の加速装置」とし、持続可能な魅力ある地域づくりを

※下記は自治体通信特別号(2025年9月発刊号)から抜粋し、記事は取材時のものです。
大阪市の夢洲を舞台に10月13日まで開催される「大阪・関西万博」。連日、多数の入場者が詰めかける盛況ぶりが報告されている。ここには、多くの自治体も参加し、地域住民と万博参加国との交流のほか、地域の文化や魅力の発信などを行っている。そのなかには、国の枠組みである「万博国際交流プログラム」の支援を受けたものもあるが、そこにはどのような狙いがあるのか。同プログラムを管轄する内閣官房 国際博覧会推進本部事務局次長の井上氏に、事業の概要や趣旨などを聞いた。

一過性で終わらせない、万博参加国との交流の仕組み
―「万博国際交流プログラム」とは、どのような事業ですか。
万博には、国内外からの大きな人流を生み出し、未来社会の実現や共創に踏み出す機運を高めるといった特徴があります。教育的要素も強いので、こどもたちにとっては代えがたい「学びの場」にもなります。こういった万博の特徴を活かし、国際交流や人材育成につなげ、地域の活性化を促すきっかけにできないか。そうした考えのもと、各省庁の協力を得て、令和4年12月に「万博交流イニシアチブ」を立ち上げ、万博をこどもたちの育成や地域への観光誘客などの好機とする取り組みを進めてきました。「万博国際交流プログラム」はそのなかの1つの施策で、全国の自治体が万博参加国との人的・経済的・文化的な相互交流を通じて、地域の活性化を図ることを目的としています。万博を、いわば「地方創生の加速装置」として活用してもらう狙いです。
―具体的に、どういった枠組みで進められてきたのでしょう。
今回の万博には、日本開催の万博史上最多の158ヵ国が集いました。この機会を捉え、これまで交流実績は少ないものの、今後国際社会で存在感を増すと見られるアフリカ、中東、中南米、大洋州島嶼国など、いわゆるグローバルサウス諸国との新たな交流を促す仕組みとしました。また、一過性の取り組みとならないよう、「会期前の機運醸成」「会期中の万博会場内外での交流イベント」「会期後の交流継続」という3段階で取り組む制度としています。
国際交流が起点の地方創生を「万博のレガシー」に
―プログラムを通じて、どういった手応えを感じていますか。
プログラムには、交流計画として154件が登録され、登録自治体数も北海道から沖縄まで95自治体*にわたっています。現在、各自治体が万博会期前から準備していたさまざまな取り組みが、万博会場内外で実際に行われています。なかには、交流相手国のナショナルデーと連携した交流も行われるなど、今後の継続的な交流にあたってマイルストーンとなりえるようなものもあります。たとえば、国際交流を通じたシビックプライドの形成を図っている上板町(徳島県)とヨルダンの取り組みや、小規模自治体ながらも「ジャンベ(西アフリカの伝統的な打楽器)」を核とした交流により関係人口拡大をめざす三島村(鹿児島県)とギニアの取り組みなどは、その一例です。私も実際に万博会場を訪れた際には盛り上がりを感じており、万博の開催を機に各地域の施策は狙い通りに加速されているようです。
―国際交流を地方創生につなげるために重要なことはなんですか。
国際交流自体を目的化するのではなく、地域としてのビジョン達成のための1つの手段として活用してもらいたいのです。それは、プログラムに参画していない自治体においても同様です。近隣のプログラム参画自治体には、参考事例がたくさんあります。海外からの新たな発想は、地域産業の磨き上げや高付加価値化につながる面もあります。また、こどもたちにとって国際交流は次代を担う人材の育成といった観点のほか、自分が暮らす地域への理解促進やシビックプライドの醸成につながるでしょう。
首長自らが関心をもって関与していただくことで、自治体内での事業の位置づけも明確化し、事業の継続性も向上するのではないかとも考えます。万博を契機とする国際交流をはじめとした地方創生の取り組みが、「万博のレガシー」となることを期待しています。
*95自治体:内訳は19府県76市区町村、44都道府県域

これまで紹介した「万博国際交流プログラム」には、全国で95の自治体が参加し、さまざまな視点から国際交流が繰り広げられてきた。交流相手国の選定や交流の目的、具体的な施策の企画など、そこにはまちが抱える課題やめざすべき将来の姿といった、それぞれの自治体の事情が色濃く反映されている。ここでは、取り組みを主導した各自治体の首長たちを取材。まちづくりにおける国際交流の重要性や、実感する効果などについて聞いた。

「万博国際交流プログラム」へは、これまで築いてきたマリ共和国との交流をさらに発展させ、当町が推進する独自のまちづくりのかたちである「うらほろスタイル」をより一層進化させたいとの考えから参加を決めました。「うらほろスタイル」とは、義務教育の9年間でこどもたちに地元・浦幌町について深く学んでもらうために、学校、住民、事業者などとともに地域一体でつくり上げた独自の教育課程で、すでに18年の歴史があります。最終年度となる中学3年生には町への提言を行ってもらい、行政は地域と連携してそれを真剣に実現させる試みです。まさに「こどもたちの想いを起点にしたまちづくり」といえます。
マリ共和国とのつながりも、「うらほろスタイル」に興味をもった同国の知事が令和5年に行った当町への視察に端を発します。プログラムとしては昨年、マリの演奏家を招き、音楽や芸術、食文化やサッカーで交流を図る「マリフェアinうらほろ」を開催。今年は当町の小中学生13人が万博会場で、マリの伝統打楽器「ジャンベ」を使って演奏するイベントも行いました。異なる文化や価値観にふれることで、人生の豊かさや多様な価値観を知り、スケールの大きな人材として「うらほろスタイル」の担い手に育ってくれることを期待しています。
この間の国際交流の取り組みは近隣自治体にも伝わり、首長たちからも問い合わせがきています。万博を契機に、国際交流で磨き上げた「うらほろスタイル」が広がり、人材教育やまちづくりの参考事例になることを願っています。

当町では、町内唯一の公立高校である県立遊佐高等学校の存続に向けて入学志願者数を増やすため、令和元年より「地域みらい留学」の仕組みを活用し、「国内留学生」を受け入れてきました。この間、取り組みは一定の成果をあげ、同校は廃校の危機から脱しつつあります。一方で、国内全体で人口減少が進むなか、将来的に留学生の受け入れは海外にも枠を広げる必要があるのではないかとの危機感もあります。「万博国際交流プログラム」への参加には、国際感覚をもった人材の育成はもとより、将来、海外留学生の受け入れを見据えた、実証的な事業という意味合いもあります。交流相手国にマダガスカル共和国を選定した理由には、アフリカ諸国で第2位を誇る日本語学習者数や、治安や政治情勢の安定がありました。
今回のプログラムとしては昨年、遊佐高校の生徒3人が同国を訪問し、現地の高校生との交流を行いました。この交流は周囲にも影響を与えているようで、実際に町の短期留学補助制度を使って海外へ留学する生徒も出てきていると聞きます。遊佐町で学ぶ若者の国際感覚の醸成につながっているようです。今年は、同国から中学生が訪れ、遊佐町の中高生9人の「おもてなし隊」による交流プランで当町の魅力を満喫してもらいました。こうした町外との交流が、地域の持続可能性を高めることは、これまでの国内留学の取り組みでも経験してきました。今後も「過疎を資源に変える」という理念のもと、今回の「万博国際交流プログラム」を契機に世界に選ばれる遊佐町をめざしていきます。

当市はこどもたちの育成や地域の活性化に対する国際交流の効果を高く評価しており、長年、独自性のある国際交流イベントを実施してきた実績があります。その1つである世界音楽の祭典「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」が始まった平成3年以来、「スティールパン」アーティストを派遣してくれたトリニダード・トバゴ共和国と交流が続いてきました。この交流をさらに発展させ、STEAM教育や地方創生の強化につなげることが、プログラム参加の動機でした。
今回のプログラムでは、令和6年度以降、同国から招聘したアーティストとの交流を行ってきました。昨年のアンケートでは、多くのこどもが「郷土を誇りに思う」「将来も南砺に関わりたい」と回答してくれており、成果を実感しています。8月には、万博会場で地元の小中高生約60人が日本最古の民謡ともいわれる当市の五箇山地方の民謡「こきりこ」を披露しました。私自身も、幼いころに見た1970年の大阪万博の記憶は、鮮烈に脳裏に焼きついています。それと同様に、市内には民謡保存会のみなさんをはじめ、かつての大阪万博に参加した人も多数おり、皆が一様に「当時の感動をいまのこどもたちにも味わってほしい」との熱い想いを共有しています。その想いに後押しされ、地域の誇りを胸に「こきりこ」を披露したこどもたちが、いずれ親世代になって「万博のレガシー」を次の世代に受け継いでいく。そんな未来を想像し、今回の経験を教育現場に取り入れるなど将来につなげていく考えです。

有田市が「万博国際交流プログラム」の前身のモデル事業に参加した令和5年度当時は、当市に立地するENEOSの製油所機能停止が決定し、市の産業構造の大きな転換期を迎えていた時期でした。未来を担う人材の育成にはこれまでも注力してきましたが、このプログラムは、こどもたちが国際的な視野と多様な価値観を養い、社会課題に主体的に向き合う力を育む絶好の機会と考えました。交流相手国にアラブ首長国連邦(UAE)を選んだのは、前回の万博開催国として訪問した縁に加え、石油依存からの脱却をめざすドバイのまちづくりに、学ぶべき点が多いと感じたからです。
本プログラムでは、「有田市こども未来基金」に賛同したENEOSなどの支援も受け、昨年は有和中学校の生徒20人をドバイへ派遣しました。生徒たちは異文化に触れることで大きな刺激を受け、保護者や地域のみなさまからも高く評価されています。今年は万博の開催に合わせて、9月にドバイのGNS*から43人の学生を当市に招き、さらなる交流を深めるとともに、9月19日のUAEナショナルデーには、有和中学校の全校生徒約600人が万博に参加し、GNSの生徒たちと共同パフォーマンスを披露します。
ENEOSからは今年、製油所跡地に「持続可能な航空燃料(SAF)」の製造拠点を整備する方針が発表され、地元としても人材の輩出への期待や責任を感じています。当市は、このプログラムを起点に、国際感覚豊かな地域へと成長し、今後も人材育成だけでなく、観光や産業振興にもつながる好循環を築いていきます。
*GNS:GEMS Al Barsha National Schoolの略称
本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。