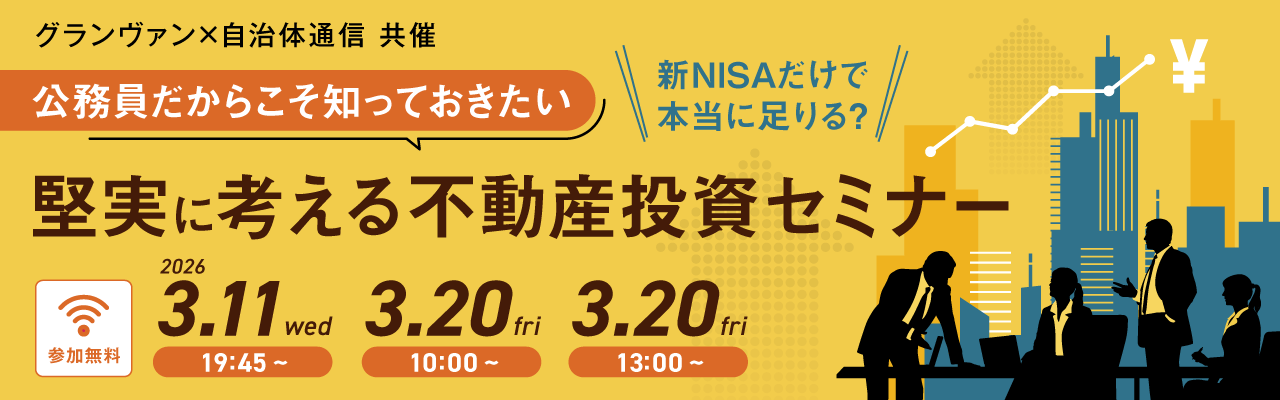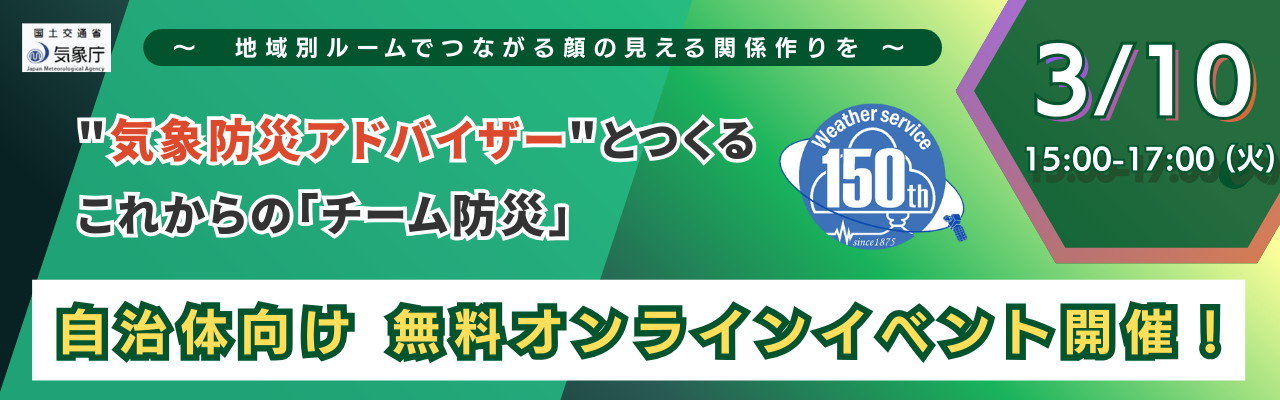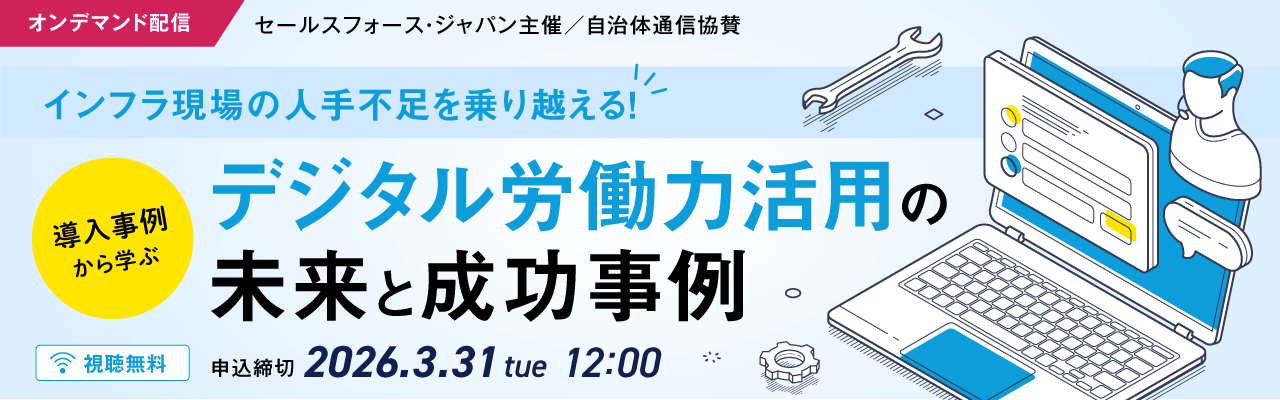「偽・誤情報に惑わされるな!“自分は大丈夫”と思っている人ほど危ない!?」 みんなで守ろう「ネットコミュニティ」フォーラムに参画!


TikTok Japanは、2025年6月7日(土)に国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)が主催し、総務省が後援した『みんなで守ろう「ネットコミュニティ」フォーラム』に協力企業として参画しました。本フォーラムは都内会場で一般の方も招いて実施し、同時にTikTok LIVEで配信を行いました。総務省や慶應義塾大学大学院、日本ファクトチェックセンター、一般社団法人トラスト&セーフティ協会、一般社団法人ソーシャルメディア研究会、LINEヤフー株式会社などの偽・誤情報に関する専門家や有識者によるトークセッションが行われました。また参加型クイズや偽・誤情報のオリジナルボードゲームなども実施し、参加者が体験を通して学べる内容となりました。
TikTok Japanは、2025年1月に総務省が立ち上げた官民連携プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」に参画。その取り組みの一環として、専門家やクリエイターと協力し、幅広い年代における安全なネットリテラシーの向上と、安心安全かつ信頼できるデジタル空間づくりへの貢献を目的とした『みんなで守ろう「ネットコミュニティ」プロジェクト』を実施しています。これまでに「クリエイター向け『偽・誤情報対策ワークショップ』」や、偽・誤情報について学ぶための学習教材映像の制作を実施し、今回のフォーラムへの協力はその第3弾の活動となります。
フォーラムには人気TikTokクリエイターたちも参加。遠坂めぐ(えんさかめぐ)さん(@meg_ensaka)がMCを務め、あきとんとん🤔さん(@akitonton)、しんのすけ🎬映画感想さん(@deadnosuke)、すみはねさん(@sumihane)、そば湯さん(@sobayu8055)らがトークセッションに参加。タレント・ブランドプロデューサーのpecoさんとともに、偽・誤情報の具体的な事例やその見分け方、対応策などについて、フォーラムの来場者やTikTok LIVEから参加する方々の理解を深めました。
“自分たちの手でネット空間をより良いものにしていく”意識を

左からTikTokクリエイターのすみはねさん、あきとんとんさん、そば湯さん
フォーラムの冒頭では、あきとんとんさんとすみはねさん、そば湯さんが登壇。来場者に向け、「誤った情報に惑わされないために、気をつけていることはありますか?」と投げかけると、会場からは「一つの情報源を信じるのではなく、多くの情報源から正しい情報を見極める」「家族で話し合う」などの意見がありました。あきとんとんさんは「一つの発信や拡散が大きな影響を及ぼすこともある」とし、「今日はしっかりと偽・誤情報について学びましょう」と呼びかけました。3人の「スタート!」という掛け声に合わせ、フォーラムが開幕しました。
フォーラムの冒頭では主催の国際大学グローバル・コミュニケーション・センター所長の松山良一氏が開会あいさつ、総務大臣政務官で衆議院議員の川崎ひでと氏が来賓あいさつに登壇し、自由民主党デジタル社会推進本部長で衆議院議員の平井卓也氏の応援メッセージが上映されました。

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター所長 松山良一氏
松山所長は、「インターネットの利便性が向上している一方で、偽・誤情報の拡散や誹謗中傷など様々な課題を抱えている」とし、今後の課題として「メディア情報リテラシーを高めて、誰もが安心して参加できる健全なネットコミュニティをつくっていくことが求められている」と述べました。そして参加者と視聴者に向けて「自分たちの手でネット空間をより良いものにしていくという意識・実践を持ち帰ってもらえる機会にしてほしい」と、今回のフォーラムに対する期待を込めたメッセージを送りました。

総務大臣政務官 衆議院議員 川崎ひでと氏
開催のあいさつに登壇した川崎ひでと氏は、1973年に発生した豊川信用金庫事件を紹介しました。この事件では、女子高生の雑談をきっかけに誤情報が広がり、取り付け騒ぎにまで発展しました。川崎氏は「1973年というネットがない社会でさえ、誤情報によって大きな事件が起こりました。今、我々の手の中にはスマートフォンがあり、当時とは比べものにならないほど多くの情報が世の中に拡散されます。だからこそ、『この情報って本当に正しいのかな?』という意識を忘れずに情報に接することはとても大切です」と警鐘を鳴らし、「皆さまがICTリテラシーを身につければ、ネットの空間はより過ごしやすい健全なものになります。ぜひ今日この時間を皆さまでともに考えていく時間にしていただきたいと思います」と呼びかけました。

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 企画官 吉田弘毅氏
次に、総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 企画官の吉田弘毅氏が、政府の取り組みを説明しました。
吉田氏はまず、総務省が2025年3月31日(月)から4月2日(水)にかけて全国47都道府県の2,820名を対象に実施した「ICTリテラシーに係る実態調査」(※)の結果を紹介しました。本調査では、過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対して、その内容をどう判断したかを尋ねたところ、「正しい情報だと思う」「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47.7%でした。また偽・誤情報に接触した人のうち25.5%の人が、何らかの手段を用いて拡散したという結果に。こうした現状を踏まえ、吉田氏は政府として6つの分野で総合的な対策を進めていることを説明しました。それは「普及啓発・リテラシー向上」「技術の研究開発・実証」「人材の確保・育成」「国際連携・協力」「社会全体へのファクトチェックの普及」「制度的な対応」です。
(※)総務省「ICTリテラシーに係る実態調査」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000176.html
制度的な対応として、2025年4月に「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されたことを挙げ、この法律により、削除対応の迅速化や運用状況の透明化が義務付けられていること、また技術の研究開発・実証として、「生成AI等に起因する偽・誤情報の検知」と「情報の発信元等の真正性の証明」という二つの観点から技術開発を支援していることを述べました。特にAI技術の悪用への対策として、吉田氏は次のように説明しました。
「近年は、AIを使ったディープフェイクも増えています。例えばディープフェイクで作られた部分を赤く表示して可視化するなど、情報の受け手の側がAIで合成された偽・誤情報に当たるか否かを判断しやすくするための技術開発を支援しています。この技術については、画像・映像以外の、例えば音声やテキストへの応用も進めているところです。あわせて、情報の発信元が正しいかを証明する技術の開発も支援しています」
最後に吉田氏はウェブサイトやゲーム、CM、教材を活用した普及活動を紹介し、講演を締めくくりました。
「情報の拡散は直接の会話が最も多い」偽・誤情報の現状と具体的な対策

フォーラムの最初のセッションは、「偽・誤情報の現状と対策の在り方について」です。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授の山口真一氏と、日本ファクトチェックセンター編集長の古田 大輔氏、TikTokクリエイターのすみはねさん、そば湯さん、ゲストタレントのpecoさんが登場し、会場の皆さまやTikTok LIVEの視聴者と一緒に学びました。
山口氏はまず、「偽情報は意図的・意識的につくられた嘘・偽りの情報」「誤情報は勘違いや誤解によって拡散した間違った情報」と偽・誤情報の違いについて説明。具体的な事例として、2016年のアメリカの大統領選挙やコロナ禍での出来事を振り返りました。
「選挙の3カ月、候補者に関連する偽・誤情報が、ある特定のSNS上で3,760万回も拡散されたということが分かっています。事実を拡散された回数よりも、偽・誤情報を拡散された回数の方が多かったのです。またコロナ禍では、セルフチェックに関するデマや陰謀論が拡散。WHOが『インフォデミック』(インフォメーション『情報』とパンデミック『感染症の世界的流行』を合わせた造語)として警鐘をならすほどでした」(山口氏)

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授 山口真一氏(左)と、日本ファクトチェックセンター編集長 古田 大輔氏(右)
山口氏は現在起きている問題として、インフルエンサーへの誹謗中傷、反対にインフルエンサーによる偽・誤情報拡散なども挙げました。特に警戒すべき情報として「『投資の必勝法』『簡単に稼げる副業』『お金を配ります』といった人の欲望や不安に付け込む情報には注意が必要。著名人の画像を無断で使用する悪質な手法も横行している」と呼びかけました。
さらに深刻な問題として、ディープフェイクによる偽画像や偽動画の問題にも言及しました。「水害の様子として拡散された映像がAIによって作られたものだったという事例が報告されています」と具体例を紹介し、「AIの大衆化により、誰もが偽・誤情報を作成・拡散できる『ウィズフェイク2.0』とも呼べる時代に突入している」と現状を分析しました。
山口氏は、実際に拡散された15件の事例を対象とした研究結果を紹介しました。
「正しく真偽判断できている人はわずか15%で、年代による差は見られなかった。偽・誤情報の拡散は直接の会話が最も多く、自分から家族へ、家族がSNSへ投稿し、現実からネット、ネットから現実へと繰り返し拡散される構造が明らかになっている。皮肉なことに、自分は騙されないと考える人ほど偽・誤情報を信じてしまう傾向があるのです」
山口氏によると、偽・誤情報は人に伝えたい要素が強く、真実の6倍のスピードで拡散されるといいます。こうした深刻な状況を踏まえ、山口氏は社会的な対策の必要性を強調。「政府や自治体、事業者、業界団体、メディア、教育機関、市民などが連携した社会対策が不可欠である」と述べました。また個人ができる対策として「まず自分も騙される可能性があることを認識すること。そして内容がわからない場合は拡散しないこと。どうしても拡散したい情報があれば、必ず情報検証を行い、それでも真偽が判断できない場合は拡散を控える。この習慣を身につけることが、社会全体への最大の貢献となる」と呼びかけました。
山口氏が、TikTokクリエイターに偽・誤情報に関する経験を尋ねると、具体的で参考になる体験談が共有されました。すみはねさんは、「数日前、あるクリエイターの結婚報告があった。家族に言いそうになったけど我慢し、クリエイターの事務所の公式ホームページを確認。発表がなかったので、誰かに伝えることは避けた」と回答。これに対し山口氏は、「公式の情報を確認するのが素晴らしい」と絶賛しました。

タレント・ブランドプロデューサー pecoさん
pecoさんは、「約1年前、フォロワーさんから『妊娠したの?結婚するの?拡散されてるよ』というメッセージをもらった。当時私が選択した対策は無視すること。なぜなら、このようなデマに対して否定的なコメントを出すことは、かえって相手の思うツボになってしまうからです」と、自身の体験を振り返りました。これに対し山口氏は「そういう対策もありますね」としたうえで、「拡散され誹謗中傷などの被害が大きくなった場合は、『否定する』ことも大切です」と、状況に応じた柔軟な対応の重要性についても補足しました。
偽情報を見極めるためのポイントとは?
続いて、日本ファクトチェックセンター編集長の古田大輔氏が解説。古田氏は、偽・誤情報は大きく7つに分類できることを説明しました。それは捏造、改変、文脈の操作、なりすまし、生成AI、根拠不明、パロディです。
古田氏が「文脈の操作は、誤解を与える文脈に情報を置き換える手法。災害時などに、過去の動画を現在の出来事として流すケースなどがこれにあたります。なりすましは実在の組織や人物を装う手法です」と解説すると、pecoさんは「何度もなりすましの被害に遭っています」とコメントしました。
古田氏は続けて、「根拠不明は検証不可能な主張のこと。『闇の組織に支配されている』といった陰謀論がこれに該当します。パロディは風刺を目的としたもので、世の中を楽しくする良い面もありますが、パロディを本物の情報として拡散してしまう人もいるため注意が必要です」と説明。そして、偽情報を見極めるためのポイントとして、「発信源」「根拠」「関連情報」3つを提示しました。

具体例として、能登半島地震で「車に閉じ込められた」という投稿の発信元が海外だったケースを挙げ、「まず『誰が、どこから発信しているのか』『その情報を知る立場にある人なのか』を確認してください」と述べました。さらに、「示された根拠が本当に根拠になり得るか、その情報を知りうる立場の人や機関が何を発信しているか、報道機関はどう報じているかなどの関連情報を調べます。高度な検索、画像や動画検索、オープンデータなども活用しましょう」と呼びかけました。古田氏は最後に「ファクトチェックセンターでは無料の『ファクトチェック講座』を開設しています。偽・誤情報について学びたい方はぜひ参考にしてください」と締めくくりました。
次に、偽・誤情報を見極める方法の実践として、pecoさんとTikTokクリエイター、来場者がクイズに挑戦。以下2つの投稿のうち、正しいのはどちらかをスマホの検索機能を駆使しながら考えました。
A「東大寺の大仏殿の柱にある穴は、大仏の鼻の穴と同じ大きさで、くぐるとご利益があると言われている」
B「新倉山浅間公園はパノラマの富士山と五重塔と桜が一緒に撮影できる、京都随一の絶景スポット!」
来場者の多くが「Aが正しい」に挙手しました。「Bが正しい」に挙手したそば湯さんに理由を尋ねると、「『富士山 五重塔 桜』で検索したら画像が出てきた」と回答。これに対し古田氏が「最高の間違え方です!」と笑顔を見せると、会場は笑いに包まれました。古田氏は「正解はA」と述べ、正しい調べ方を解説しました。「『東大寺 大仏 鼻の穴 大きさ』などとなるべく細かく検索します。すると柱や鼻の穴についての解説が出てくるので公式の情報を確認しましょう」
そして、すでに捏造された情報は溢れていると指摘し、「写真があったとしても、本当とは限らない」としました。さらに地理的な常識の重要性についても言及し、「よく考えると、京都からあんなに鮮明に富士山は見えません」と続けると、TikTokクリエイターや会場からは「おぉ〜!」「たしかに〜!」といった声が上がりました。その後もファクトチェックのクイズは続き、画像検索や信頼できる情報源の確認などをしながら理解を深めました。古田氏は最後に重要なメッセージを送りました。
「『いいね』やシェア、コメントをする前には、必ずその情報の真偽を調べることが重要です。クリエイターだけでなく、すべてのユーザーが自分自身もメディアの一部であることを自覚しましょう」

ここで会場は休憩時間に入り、その間にTikTokクリエイターたちは、ここまでの講演内容をおさらいしました。ホワイトボードを使って、偽・誤情報を取り巻く現状や対策について分かりやすく解説し、参加者の理解をさらに深める時間となりました。
オリジナルボードゲーム『偽・誤情報に惑わされずトップクリエイターを目指せ!』で学ぶ

次のセッションはオリジナルボードゲームによるメディア情報リテラシー実践です。ボードゲーム『偽・誤情報に惑わされず トップクリエイターを目指せ!』は、サイコロを振ってコマを進めるすごろく形式のゲーム。プレイヤーは、偽・誤情報に惑わされないスキルを身につけながらトップクリエイターを目指します。
「偽・誤情報」という難しいテーマを、楽しみながら学べる本ゲーム。すみはねさん、遠坂めぐさん、pecoさん、ソーシャルメディア研究会(みねまいさん、いーぶいさん)がゲームプレイに参加しました。ゲームでは、偽・誤情報についてプレイヤー同士で話し合ったり、考えを共有しながら進めるシーンもありました。「偽・誤情報を信じた経験は?なぜ信じたか?」のテーマが出ると、参加者たちは真剣に考えて回答しました。

MCを務めたTikTokクリエイターの遠坂めぐさん
遠坂めぐさんは「本人と見られる音声や動画があり信じてしまったけれど、ディープフェイクの可能性もあるから検証が必要だと思いました」と回答し、ポイントを獲得。この回答により、最下位から逆転優勝を飾るという展開になりました。
TikTokクリエイターからは、「炎上や投稿に関する心配事がリアルなのでぜひ皆さんにも見てほしい」「楽しみながら学べるので中学や高校に配ってほしい」「すごろくで負けていてもディスカッションで逆転できる、面白いゲームでした」などの感想がありました。また、TikTokライブの視聴者からは「楽しく学べるコンテンツ!」「炎上疑似体験は大事ですね」とコメントが寄せられました。
「表現の自由をどう守っていくか」安全な情報空間の作り方

最後に、「安全な情報空間の作り方」について講演がありました。私たちが利用しているプラットフォームや企業がどのような取り組みをしているのか、そして安全な情報空間はどうすれば築いていけるのか。LINE ヤフー株式会社 政策企画本部メディア部長の槇本英之氏、慶應義塾大学大学院 法務研究科教授の山本龍彦氏、TikTok Japan 公共政策部長の西村健吾が登壇しました。

TikTok Japan公共政策部長 西村健吾
西村は、TikTokの現状と対策について「TikTokの利用者は若年層だけでなく30-40代にも広がり、多くの年代で使われています」と述べ、偽・誤情報対策として二つの主要な対応を取っていることを紹介しました。
「一つ目はTikTokのコミュニティガイドラインで、安心安全に楽しんでもらうためのルールを制定。二つ目はコンテンツモデレーションで、違反コンテンツや違反アカウントの削除や停止を実施し、生命身体に危険がある場合は関連当局に連絡します。また、信ぴょう性が未確認の情報やAIを活用した、もしくはAIによって生成された投稿に対するラベル付けも義務化しています」(西村)

LINEヤフー株式会社 政策企画本部メディア部長 槇本英之氏
槇本氏は、VOOMやオープンチャットなどのプラットフォームでの取り組みについて詳しく説明し、「偽・誤情報対策として主に次のアプローチを取っています」として、まず投稿の削除について言及しました。
「一日あたり約31万件(Yahoo!ニュースのコメント)、1500万件(LINEオープンチャット)ある投稿を、AIと人の目でモニタリングしています。またサービスの導線上での情報発信、おすすめ表示におけるアルゴリズムの工夫、匿名アカウントの悪用防止策などを講じています。これらの取り組みにより、健全なコミュニケーション環境の維持を図っています」(槇本氏)

慶應義塾大学大学院 法務研究科教授 山本龍彦氏
山本氏は、「『情報的健康』というコンセプトをキーワードに、誹謗中傷や偽・誤情報に溢れるデジタル空間をどう改善していくかを提唱しています」と自身の研究テーマを紹介しました。表現の自由の観点から考えると、削除による対応には限界があると指摘し、「重要なのは一人ひとりの意識です」と強調しました。さらに身近な例を用いて、「食べ物は『バランスよく食べましょう』と言うように、情報も偏らず摂取すべき。多様な情報に触れることで免疫ができ、偽・誤情報にも惑わされにくくなるのではないか」と述べました。
モデレーターの山口氏から、プラットフォーム事業者としての課題について尋ねられると、こんな回答がありました。「最大の課題はグレーゾーンの情報への対応。どこまでモデレーションするかは非常に判断が困難で、過度に行えば表現の自由を侵害してしまいます。プラットフォーム運営者として、安全性と自由のバランスをどう取るかが重要な課題となっています」(西村氏)
槇本氏は「私たちも同じような悩みを抱えています」と共感します。「間違った情報に対し、誰かが『正しくはこうだ』指摘する。こうしたコミュニケーションの広がりも、偽・誤情報に惑わされないために必要です。正しい情報の提示や普及啓発で、議論の流れをつくっていくのも私たちプラットフォームの役割だと考えています」
これに対し、山本氏は次のように述べました。「プラットフォーム事業者はフードコートのような存在で、様々な情報を扱っており、中には体に良くないジャンクフードのような情報もあります。心に毒になってしまう情報や人の行動をコントロールする情報は控えるなど、その情報が良いか悪いかは最終的には客であるユーザーが判断すべき。だからこそ私たち一人ひとりが情報的健康に対する意識を持たなくてはいけません」
この分かりやすい例えに、すみはねさんは「フードコートのたとえがすごくわかりやすくて、しっくりきました!」とコメントし、理解が深まった様子を見せました。ここで山口氏から「偽・誤情報はネット普及前から存在しており、事業者だけの力で解決することは不可能。社会全体として何に取り組めばいいのでしょうか」と疑問が投げかけられました。
この質問に対し、TikTokクリエイターたちから実体験に基づく貴重な意見が寄せられました。「偽・誤情報について、私たちはどこで学ぶべきなのでしょうか。例えば『ダイハード4』では犯人がホワイトハウス爆破の偽映像で世界を混乱させました。十数年前の映画でしたが、現在では私たちのような素人でもそのような映像を作ることが可能になっています。一人ひとりがこの技術の身近さを知ることが重要かなと。映画というエンタメからも偽・誤情報の危険性や仕組みを学ぶことができ、有効な学習手段となります」(しんのすけさん)
「私の世代は、小学生からスマホを持っていてネットは身近な存在で、情報を得るのはほとんどSNSから。親に正しい使い方を教えることも多いけれど、一方で身近すぎてちゃんと考えていなかったんだなと気づきました。だからこそ、私たち若い世代もしっかり学ぶことが大事だと思いました」(すみはねさん)
「ブログやSNSなどを経験し、特にSNSがきっかけでテレビ出演するようになりました。SNSには良い面も悪い面もあるため、6歳の息子にはまだ見せたくない気持ちでいます。しかし、すみはねさんの話を聞いて考えが変わりました。小さい頃から適切にSNSに親しむことで、情報を見極める力が育つのかもしれません」(pecoさん)
これらの意見を受けて山口氏は「子どもにスマホを持たせる際は、単に与えるだけでなく、その使用環境や背景をしっかりと伝えていくことが最も大切」と述べました。また、現状の課題として「インフルエンサーの発信によって行動を変えた人が多い一方で、政府の発信は人々に届いていない」と指摘。これに対し山本氏は「政府の発信力の弱さを聞いてショックでした」と述べながらも、重要な提言をしました。
「これまでクリエイターの方と話す機会はありませんでしたが、本日のように対話していくことが大切だと感じました。政府や専門家だけで考えていても発展は期待できません。政策によって透明性を高め、何の情報を摂取していくかを個人が適切に決められる世の中になることが理想です」
これに対してpecoさんは、「表現の自由を守っていきたいという話が聞けて嬉しく感じました」と笑顔を見せ、「プラットフォーム側の配慮だけでなく、私たちの意識向上こそが、表現の自由と安全な情報環境の両立を実現する鍵になるのだと思います」と呼びかけました。
自分の発信や行動に対する責任の重さを実感

こうしてすべてのセッションが終了し、TikTokクリエイターがそれぞれ今日の感想を述べました。
「ネット上では先週のトレンドが今週には古くなるほど情報の変化が激しく、その中での偽・誤情報の判断はより困難になっています。運転免許を取得するのと同じように、ネットを安全に使うためのリテラシーを体系的に学ぶことが現代社会では必要だと感じました」(そば湯さん)
「ネットの世界も現実の一部であるにも関わらず、私たちはつい別世界のように感じてしまいがちです。しかし、画面の向こうには必ず一人の人間がいます。この当たり前のことを改めて認識すると、自分の発信や行動に対する責任の重さを実感します。偽・誤情報に関するイベントには何度も参加していますが、学びは尽きません」(しんのすけさん)
「偽情報は一概に悪いものとは言えません。しんのすけさんの言うように、エンタメや虚構作品も、ある意味では偽・誤情報。重要なのは、それをどう扱うかということです。エンタメとして楽しむのか、事実として受け取るのか、その判断と責任が問われます。偽・誤情報に限らず、あらゆる情報に対して私たちはその重みと影響力を真剣に考える必要があると改めて感じました」(遠坂めぐさん)
「教育系クリエイターとして、自分の発信や行動が他者に与える影響の大きさを日々体感しているからこそ、責任の重さを感じています。今後、学校での授業を予定しており、この影響力を良い方向に活用したいと考えています」(あきとんとんさん)
「難しいテーマでしたが、考えることが好きなので議論できて楽しかったです。異なる視点から議論しても、最終的に辿り着く結論は同じでした。これまでなんとなくしか理解していませんでしたが、正しい知識を身につけられる良い機会となりました」(すみはねさん)
この後、クリエイターが制作した啓発動画が上映されイベントは幕を閉じました。
しんのすけ🎬映画感想さんの動画
https://www.tiktok.com/@deadnosuke/video/7488982114013220103?lang=ja-JP
すみはねさんの動画
https://www.tiktok.com/@sumihane/video/7486721289042808082
あきとんとん🤔さんの動画
https://www.tiktok.com/@akitonton/video/7486080470296579335
そば湯さんの動画
https://www.tiktok.com/@sobayu8055/video/7486408090062048520
遠坂めぐ(えんさかめぐ)さんの動画
https://www.tiktok.com/@meg_ensaka/video/7486471167847501072
破天荒夫婦〜嫁が破天荒過ぎて愛しい〜さんの動画
https://www.tiktok.com/@hatenkou22/video/7487524020565445894
みいるか🐬🎨さんの動画
https://www.tiktok.com/@miiruka_/video/7486413228705107208
祈世麻里💫さん
https://www.tiktok.com/@kise_mari/video/7490028331568581893
KOKO🐣🐥さんの動画
https://www.tiktok.com/@koko_garden55/video/7486412953588075794
ニシコリ_Nishikoriさんの動画
https://www.tiktok.com/@nishikori50000/video/7487882524660714807
フォーラム終了後には、出演したクリエイターが会場出口に並んでハイタッチでお見送りを実施。当日会場に足を運んだファンとの交流を楽しみました。
専門家の皆さまとともに、幅広い年代における安全なネットリテラシーの向上と、安心安全かつ信頼できるデジタル空間づくりについて考える機会となった本フォーラム。今後もTikTok Japanは、幅広い取り組みを通じて引き続き安心安全なネット利用とユーザーのネットリテラシー向上に取り組んでまいります。
本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。