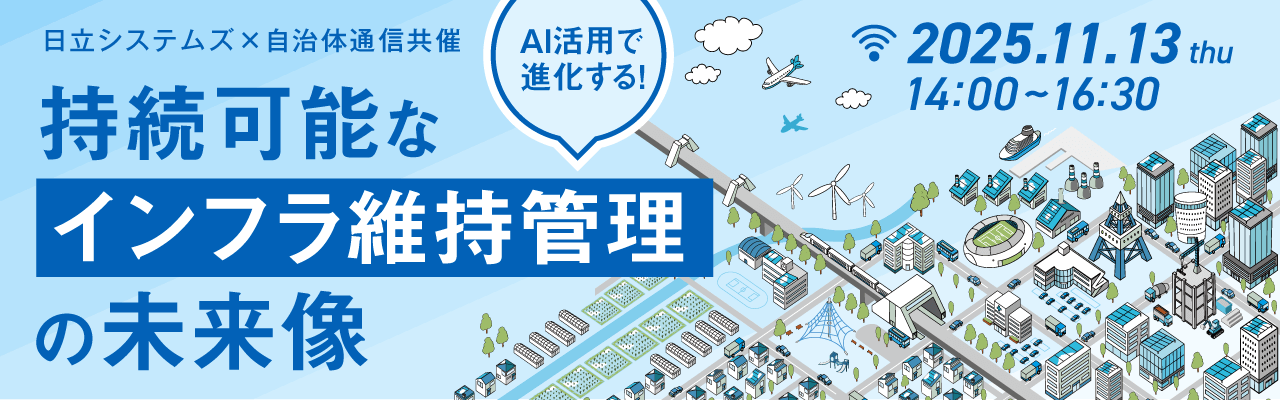指定管理事業で「公共施設のDX」も実施 地域デジタル化とビジネスの両立を実現

自治体が地域DXプロジェクトを実施するパートナーとして、地元のケーブルテレビ事業者と連携する事例が全国で増えている。情報通信の技術力やノウハウを持ち、地域密着で事業を展開しているケーブルテレビ事業者は、地域DXの連携相手として最適だ。「自治体×ケーブルテレビ連携」による地域DXは自治体や地域住民にとって、どのようなメリットをもたらしているのか、全国の主要事例を取材したレポート記事を8回にわたり連載する(7/24(木)~25(金)開催の「ケーブル技術ショー2025」では、この連載でレポートする事例など、各地で進められている「自治体×ケーブルテレビ」の連携事例について、シンポジウムや展示等で詳しく紹介する)。
連載4回目の今回は、知多メディアスネットワーク(株)(愛知・東海市、山本隆明社長)の事例を取材した。同社は知多半島の各市町と「地域DX推進協定」を締結するなど、地域DXのさまざまな取り組みを実施しているが、本稿ではその中から公共施設の指定管理事業に焦点を当てたい。同社の指定管理事業は施設の管理運営だけでなく、ICT技術を導入することで公共施設の業務効率向上や集客を図ることに特徴がある。「公共施設のDX」を行う同社の取り組みは、指定管理におけるケーブルテレビ事業者だからはたすことができる役割を示している事例だ。
(取材・文:『月刊B-maga』編集部・渡辺 元)
施設のキャッシュレス化やWi-Fiアクセスポイント整備


店舗のキャッシュレス化を行なった飲食施設「KURUTOおおぶ」。人流解析の導入も構想している


Wi-Fiアクセスポイントなどを整備した文化観光拠点「登窯広場」(左)と「廻船問屋瀧田家」(右)。デジタルサイネージも準備中だ
知多メディアスネットワークグループは、2025年度には自治体から指定管理者として4つの施設の管理運営を担う。すでに2施設を管理運営している。これらの指定管理事業は、同社の地域DX事業において重要な位置を占めている。
1件目は、JR大府駅下の健康、観光、飲食の複合施設「KURUTOおおぶ」。ここは以前から指定管理を受託している。指定管理の基本条件として、設備の維持、清掃が適切に行われることが求められるが、「当社はさらに人が集まるためのプロモーションを実施しています。加えて、飲食店のキャッシュレス化を推進するなど、新たな取り組みも進めています。将来的には、人流監視システムを導入し、賑わいの変化をデジタル的に検証することも視野に入れています」(知多メディアスネットワーク(株) 代表取締役社長 山本隆明氏)。
2件目は、知多半島ケーブルネットワークが昨年4月から指定管理を受託している常滑市の文化観光拠点「登窯広場」と「廻船問屋瀧田家」。常滑は日本六古窯の一つであり、古くから焼き物の街として知られている。「やきもの散歩道」という観光ゾーン内にあるこの2つの施設は少し離れているが、一体的に維持管理している。「観光DXの拠点として利用しやすい環境を整えるため、キャッシュレス決済やWi-Fiのアクセスポイント、防犯カメラを導入し、デジタルサイネージの導入を準備中です。指定管理料による収益は大きくないものの、観光DXの拠点としての可能性を見込み、管理運営に取り組んでいます」(山本社長)。
デジタルプロモーションや劇場用映画製作にも参画

デジタル予約システムや造園管理のDXを導入する予定の「梅の館」と「七曲公園」

入場券のキャッシュレス化や予約システムを導入する「東海市創造の杜交流館」。知多メディアスネットワークはオープニング上映映画の制作にも参画した
3件目は、今年4月から管理運営を請け負うこととなった知多市の「梅の館」と「七曲公園」。これらは市の公園であり、「梅の館」は梅のシーズンに賑わう施設だが、通年での集客を目指している。「そのため、デジタルプロモーションの活用や、造園管理のDXによる業務効率化に挑戦する方針です。また、施設内に飲食店やバーベキュー場があるため、デジタル予約システムを導入し、省力化しながら収益化を図る計画で準備中です。公園全体のWi-Fi整備も準備しています」(山本社長)。総務省の実証事業にも応募中だ。一方、「七曲公園」は今後整備が予定されており、将来を見据えた形で受託している。植栽管理が中心となるため、この分野で実績のある日比谷花壇グループとの共同事業体で進めており、花や樹木の管理は日比谷花壇に任せる形となっている。
そして4件目は、「東海市創造の杜交流館」。隈研吾氏が設計した新しい公共施設で、映像上映や映像制作が可能な施設だ。館内にはカフェが設置されている。同社は、「入場券のキャッシュレス化や予約システム、監視システムの導入を進めます。アナログな施錠方式をスマートロックへ変更することも予定しています」(山本社長)。
この施設は5月1日にオープンした。それに合わせて短編映画『ミラーライアーフィルムズ』の上映が行われた。本プロジェクトは「映画監督でなくても映画を撮れる」というコンセプトのもと、俳優やタレントが監督を務めるもので、今回はタレントの加藤浩次氏とNEWSの加藤シゲアキ氏の監督による短編映画を制作した。これらの作品は、東海市内で撮影され、施設のこけら落としのオープニング作品として上映される。同社はこのプロジェクトの実行委員会に参加している。
同社はこの4件の指定管理事業を通じて、地域の公共施設のデジタル化を推進し、ここでの事例を他の施設へ展開していく考えだ。
ケーブルテレビ事業者に指定管理を委託する利点
同社による公共施設の指定管理は、単なる管理運営にとどまらず、施設のDX化による運用効率の向上や、利用者の利便性向上、サービスやコンテンツの充実を実現している。そのため、施設側にも利用者側にも大きなメリットがある。ケーブルテレビ事業者は地域に責任を持つ企業であると同時に、情報通信や映像に関する高い知見と技術を有している。そのため、指定管理者として公共施設の管理運営を受託することは、自治体や住民にとっても大きな利点がある。これこそが、同社による指定管理の核となる考え方だ。
全国的な傾向として、小規模な施設の指定管理は、地元のシルバー人材センターやビルメンテナンス会社などに委託されることが多い。これには、施設の管理運営に加え、地域の雇用創出の意図も含まれている。一方、一定規模以上の施設の指定管理では、高度な企画や大規模なコスト削減などが期待されるため、大手企業に委託されるケースが多い。
しかし、大手企業への委託が進む中で、地域の不満や全国画一的なサービスへの懸念が課題となっている。例えば、大手書店チェーンが運営する図書館が成功事例として語られ、同様の手法を導入しようとする自治体も多いが、すべての地域でうまくいっているわけではない。単に図書館に大手コーヒーチェーンを誘致すれば成功するわけでもない。「近年大手志向の流れが一時強まったものの、そういったことがわかってきて、最近では地元企業への委託に回帰する動きも見られます」(山本社長)。
地域回帰の傾向が強まる中、自治体が委託する企業として、ケーブルテレビ事業者は最適な候補の一つだ。「自治体が多くの公共施設管理運営のプロポーザルで掲げるニーズは、交流人口の増加であり、ケーブルテレビが持つネットワークやプロモーション機能は、そのニーズに応える上で有利となります。ケーブルテレビ事業者は公共施設の指定管理事業で、大手企業が提供するような一般的なサービスではなく、地域に関する深い知識を活かした新たな魅力を付加するサービスを提供できます」(山本社長)。
今後は土地探しの段階から公共施設関連事業に参画も
同社の指定管理事業の取り組みは、営利活動ではあるが、それより地域のデジタル化という社会的責任の側面が強い。同社は利益だけを目的とせず、自治体と協力して地域DXを推進する姿勢を示している。「当社は自治体から出資を受けている第3セクターの企業であり、自治体がデジタル化という社会課題の解決を当社に委託することは、出資の意図とも合致しています」(山本社長)。
同社の活動エリアは知多半島の3市1町に及ぶ。地域DX事業では、特定の自治体のみを優先するのではなく、エリア全体の発展を目指しているという。「他の地域でもこのスタンスを共有するケーブルテレビ事業者は、それぞれの地域における複数自治体のDXハブとして機能することが可能であり、地域DXの推進にとって非常に有効です」(山本社長)。
営利活動の観点でも、指定管理事業は十分利益を上げられる。同社が最も長く取り組んでいる「KURUTOおおぶ」の指定管理は約8年に及ぶ。次回の委託が保証されているわけではない。だが、指定管理事業における委託期間は、新規の公共施設では3年、それ以外は全国的に5年が基本であり、「5年間の契約であれば、投資の回収リスクは分散できます。例えば、5,000万円の投資を行なっても、年間1,000万円の回収計画となるため、それほど大きなリスクにはなりません」(山本社長)。1年単位の契約ではリスクが高いが、5年の指定管理であれば、投資のリスクは十分に抑えられるという考えだ。
今後、同社の公共施設関連事業は、初期の土地探しの段階から関与する形に広がる可能性がある。「自治体の人口減少に伴い、既存の公共施設は統廃合が進み、再建の機会が生まれます。その際、土地探しの段階から関与する、建設から関わる、施設完成後に指定管理者として入る、というように参画タイミングが何度かあります。早い段階で関わるほど難易度は高いのですが、地域活性化により効果的な取り組みができるため、ケーブルテレビ事業者にとっては大きなチャンスとなります」(山本社長)。
現在同社は、自治体から公共施設に関するさまざまな相談を複数受けており、今後の事業の発展を期待している。全国の自治体にとって地域DXが重要なテーマとなっており、特に公共施設のDXは大きな課題だ。その点で、自治体と地元のケーブルテレビ事業者とのコラボレーションは有効であり、大きな可能性を持っている。
自治体・ケーブルテレビ連携のイベント「ケーブル技術ショー2025」
本連載の地域DX事例のキーパーソンが結集するシンポジウムも開催
ケーブルテレビ業界で国内最大の展示会「ケーブル技術ショー2025」が、「自治体+ケーブルテレビ」のイベントに進化して2025年7月に都内で開催される。近年、自治体が地域DXのインフラ構築や運営などの業務を地元ケーブルテレビ事業者に委託する成功事例が全国で増えている。ケーブルテレビ業界でも、地域DX事業への取り組みに業界を挙げて力を入れている。
このような動向を受けて、今年のケーブル技術ショーは自治体関係者向けの展示やセミナー、ケーブルテレビ事業者と自治体の来場者、出展者が意見交換や交流を深めるための交流イベントなどを大幅に強化する。
ケーブル技術ショーでは、本連載でレポートする自治体・ケーブルテレビ連携による地域DXのキーパーソンたちも会場に結集。シンポジウムやセミナーで、より詳しい情報を話したり、聴講者からの質問に直接答えたりする。交流イベントで情報交換もできる。
※本連載、ケーブル技術ショー2025の自治体・ケーブルテレビ連携に関する主催者展示、シンポジウム、セミナーの企画は、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「地域ビジネス推進タスクフォース」のご協力をいただきながら実施します。
●「ケーブル技術ショー2025」の概要
開催日 | 2025年7月24日(木)・25日(金) |
会場 | 東京国際フォーラム |
主催 | (一社)日本ケーブルテレビ連盟、(一社)日本CATV 技術協会、(一社)衛星放送協会 |
参加料金 | 無料※(事前登録制) |
※「ケーブルコンベンション2025」も同会期・同会場において開催されます。

| 設立 | 1975年7月1日 |
|---|---|
| 代表者名 | 理事長 中村 俊一 |
| 本社所在地 | 〒160-0022 |
| 事業内容 | 各地の自治体は「デジタル田園都市国家構想交付金」や「地方創生推進交付金」などを活用し、地域の活性化や持続化可能な地域社会の創生を目的にICTサービスの導入によるさまざまなDX改革を進めています。 地方公共団体と繋がりが深いケーブルテレビは、地域密着の情報通信インフラとして、あるいは地域に根差した事業者として、地方公共団体や民間企業と連携し、自治体DXや地方共創、スマートシティの取り組みなどを積極的に進めています。 ケーブル技術ショー2025では、地域課題解決に向け地方公共団体やケーブルテレビ事業者を集め、ソリューションやノウハウなどの解決策の提供に加えビジネスマッチングを開催いたします。 |
本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。