「AIにできること」から「住民が人にしてほしいこと」への発想転換
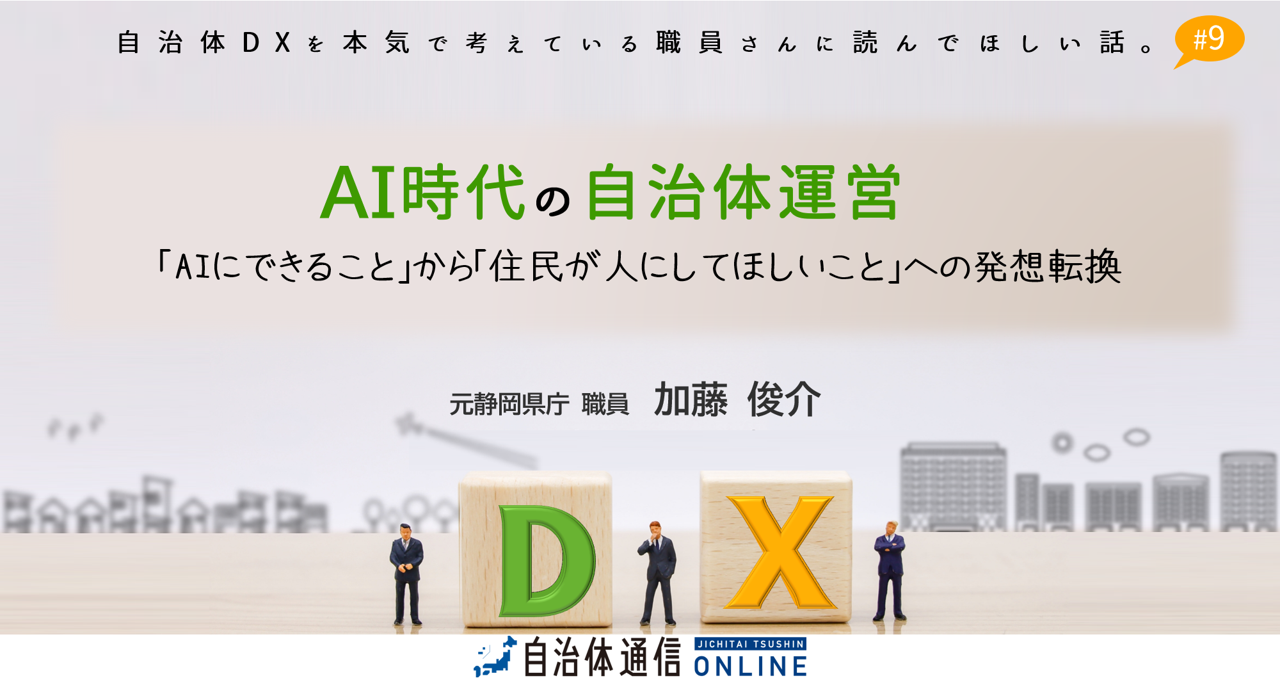

「官と民」両方の立場から公共に携わってきた筆者が自治体DXの現在地を明らかにし、未来を展望する本連載。今回は自治体×AIについて。AI導入に踏み切る自治体が増加する一方で「自治体業務におけるAIとの分担のありかた」や、そもそも先例のないことなどが原因なのか、AI活用に戸惑っている自治体職員は多いようです。そこで今回は「自治体職員とAIの付き合い方」について、海外事例もまじえながら幅広い観点から考察します。
AIを活用できない業務を探す方が難しい時代がやってくる
現在、多くの自治体でAIの活用場面を模索している段階かと思います。生成AIの登場により、これまで以上にAIが身近になり、「どこから手をつければよいか」と検討されている職員の方も少なくないでしょう。しかし、近い将来、むしろ「AIを活用できない業務を探す方が難しい」時代がやってくると考えます。すでにそうおっしゃる方もいます。
私自身、最近さまざまなAIサービスを日常的に活用しており、その利便性と進化のスピードに驚いています。文章作成の支援から、多言語翻訳、データ分析、新規事業の壁打ちまで、ほんの数か月前には考えられなかったレベルでAIが業務をサポートしてくれるようになりました。優秀でいつでも一緒に働いてくれる職員を複数人チームに雇ったような環境です。
自治体業務は文書による記録が徹底されており、判断基準も条例や規則・内規などで明文化されていることが一般的です。これはまさに、AIが活躍できる環境が整っていると言えます。例えば、議事録作成はもちろん、会議の論点出し、住民からの問合せ対応、多言語での情報提供、法令の確認、保育所入所選考、人事異動の配置検討などなど、すでに実証や導入が進んでいる事例も数多くあります。申請に対する許認可業務なども、判断基準があるのでAIによる一次審査は十分可能と思います。
東京都が策定したAI戦略「東京都AI戦略(令和7年7月)」 では、業務を「都民サービス」「都民サービス関連業務」「職員内部業務」の3つに分類し、それぞれでAI活用を体系的に推進する方針を示しています。その規模感からも、AIの可能性の広さがうかがえます。
.png)
エストニアが教える「デジタルでできるが、敢えてしない」設計思想
ここで興味深い事例を紹介します。電子政府の先進国として知られるエストニアでは、ほとんどの行政手続きがオンラインで可能です。しかし、結婚・離婚・不動産取引という3つの手続きについては、「敢えて」オンライン申請を提供していないようです。
理由は、これらが人生における重要な意思決定だからです。技術的にはオンライン化は可能ですが、それを提供しないことで考える時間を提供しているのです。
これは、AIの活用を考える上でも重要な示唆を与えてくれます。「AIができる」ことと「AIがすべき」ことは必ずしも同じではないということです。
AIと人の最適な役割分担を考える
では、どのような業務をAIに任せ、どのような業務を人が行うべきなのでしょうか。この境界線を考える際には、単純な効率化だけでなく、サービスの質向上という視点も重要になります。
◎効率化重視の業務
まず、効率化を重視すべき業務では、AIの活用を積極的に進めるべきです。議事録作成、申請書の一次審査、保育所入所選考の点数計算などがこれに該当します。これらは判断基準が明確で、迅速性や正確性が求められる業務です。
◎質の向上を目指す業務:AIと人の協働による新たな可能性
生成AIの大きな特徴は、効率化だけでなく質の向上も同時に実現できることです。AIが複数の選択肢を提示し、人がその中から最適な判断を行う。AIが膨大な情報を整理・分析し、人がそれを基に住民の個別事情に応じた対応を行う。このような協働により、ひとりの職員だけでは到達できない質の高いサービスが提供できるようになります。
例えば、住民相談において、AIが過去の類似事例や関連制度を瞬時に検索・整理し、職員がその情報を基に住民の状況に応じたきめ細かな対応を行う。政策立案では、AIが各種データを分析して複数のシナリオを提示し、職員が地域の実情を踏まえて最適な方向性を選択する。
重要なのは、AIは共に「成長する」ということです。我々が正しい依頼の仕方を学び、良質な情報をインプットし、AIの回答を適切に修正するやり取りを重ねることで、AIの回答精度は向上していきます。まだ間違いや現実的でない提案が返ってくることもありますが、AIの特性を理解し、継続的な改善を重ねることで、人だけでは実現できない質の高い成果を生み出すことができます。
100%の精度を求めると途端にAIが使いにくくなります。このプロセスは人間同士の関わり方と本質的に同じではないかと思います。部下・同僚にも100%を求めないようにAIにも同様に接するのがいいと思います。

自治体職員はAIとどう「付き合う」べき?
◎人の温もりが重要な業務:明確な線引きと曖昧な領域
一方で、人の温もりや共感が重要な業務も確実に存在します。子育て相談や用地買収に関わる住民への説明のように、明確に人が対応すべき業務もあります。
しかし、線引きが曖昧な領域も少なくありません。例えば、結婚届の受理はどうでしょうか。人が受け付けることでお祝いの気持ちが伝わり、人生の記念すべき瞬間により特別感を演出できるかもしれません。一方で、迅速な処理を望む住民もいるでしょう。
この線引きは、自治体がどのように住民と接したいのか、住民がどちらを好むのかによって変わってくる可能性があります。自治体や場合によっては住民ひとりひとりで答えが違うかもしれません。
◎住民目線での境界線設計
だからこそ、「何を人間がやった方がいいのか」を住民目線で考えることが直近重要になると思います。技術的に可能だからといって、すべてをAIに置き換える必要はありません。各自治体が独自性を発揮できる領域でもあり、「何を人にしてもらったらうれしいのか」「より幸せを感じられるのか」を住民と対話しながら見つけていくことで、その自治体らしいサービス設計が可能になります。
◎未来展望:住民が選択できるサービス設計
将来的には、住民自身がAI対応か人的対応かを選択できるサービス設計も実現すると考えます。急いでいる時や定型的な手続きではAIを選び、重要な相談や複雑な事情がある時は人的対応を選ぶ。このような「選択の自由」を提供することが、住民中心のサービス設計の在り方になるかもしれません。
さらに、個人の属性や過去の利用履歴に基づいて、最適なサービス提供方法をAIが提案することも考えられます。高齢の方には丁寧な人的対応を、デジタルネイティブ世代には効率的なAI対応を、というようにセグメント対応、パーソナライズ化が進展していくと想像します。
住民の幸せを起点とした設計を
AIを活用する際に最も重要なのは、「住民にとって何が最も心地よい対応なのか」という視点です。技術的に可能だからといって、すべてをAIに置き換える必要はありません。
むしろ、AIを「敢えて使わない」という選択も含めた戦略的な設計が求められます。効率化によって生み出された時間と人的資源を、住民との信頼関係構築や地域の魅力向上に振り向ける。そのような使い分けができれば、AIは自治体にとって価値ある技術となるはずです。
デジタル化と同様に、AI活用においても「起点」の発想が重要です(参照:本連載#2「《ありがちな自治体DX “3つの落とし穴”》デジタル化のために必要な「起点」の発想」)。AI導入自体を目的とするのではなく、住民の幸せや地域の課題解決という目的から逆算して、最適な手段を選択していく。このような姿勢が、持続可能で住民に愛される自治体運営につながるのではないでしょうか。
加藤俊介@官民共創:@ShunsukeKato_

%20(1).png)



