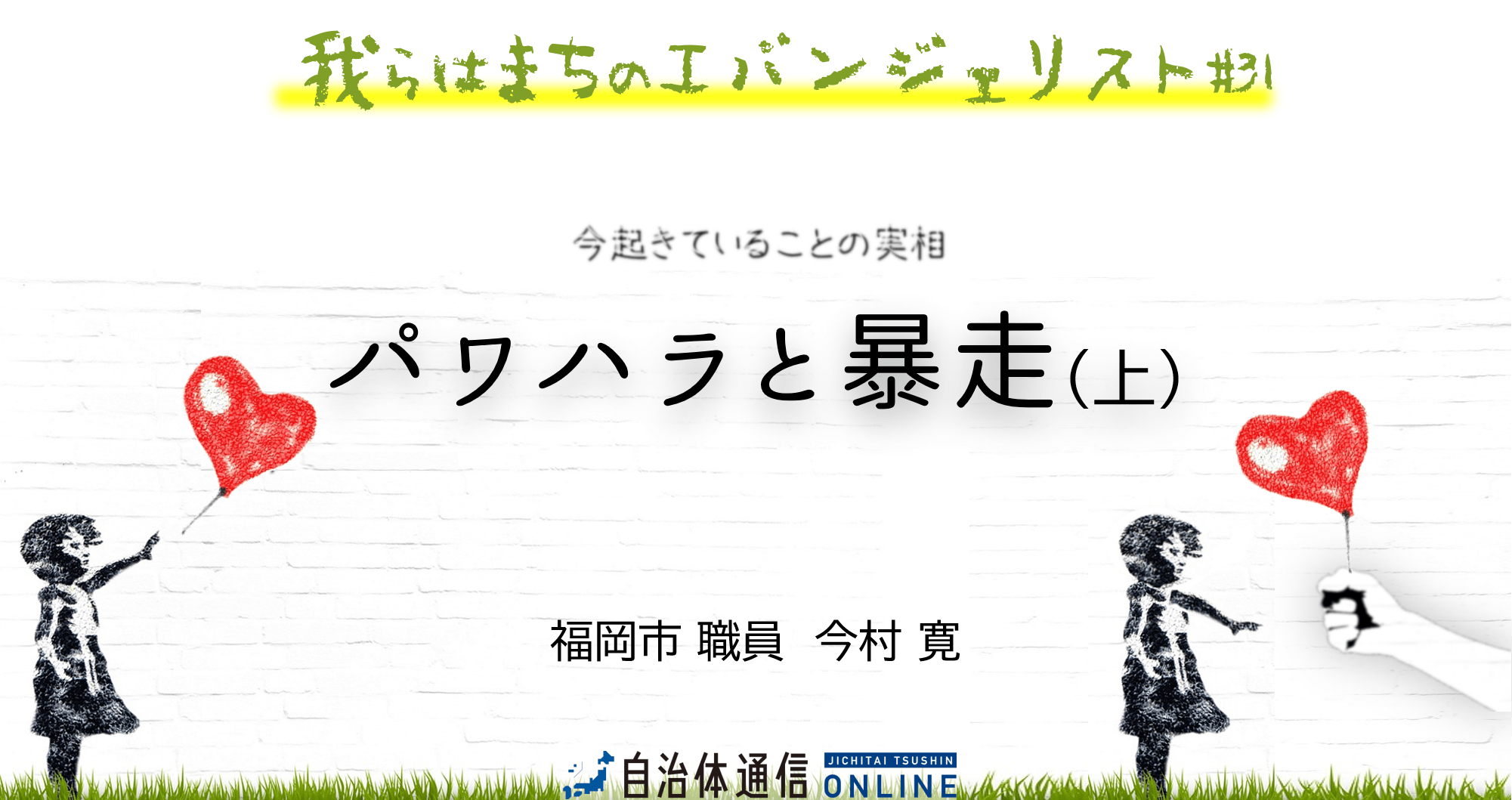
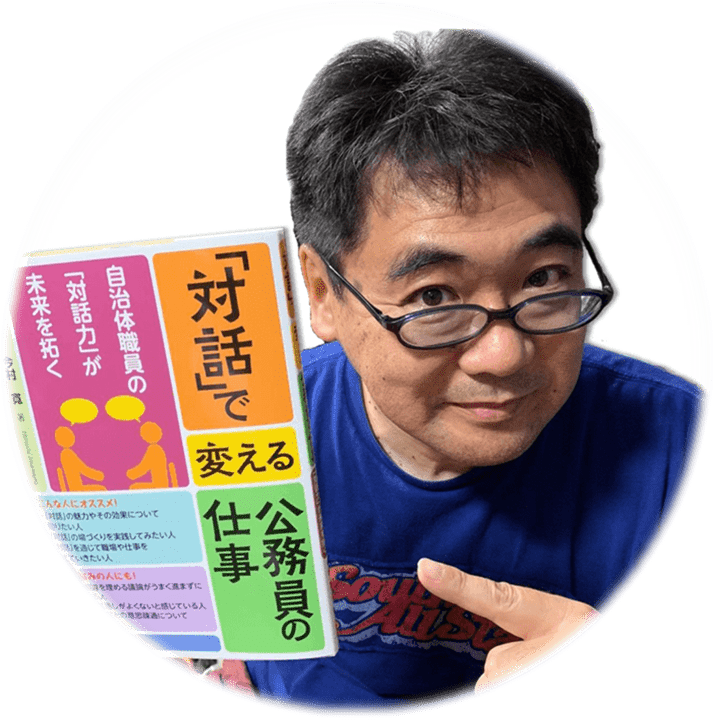
今回と次回の2回連続で、今、自治体界隈を揺るがしている問題を考察します。わたしたち自治体職員が学びとるべきポイントとは?
残念な事件…
大変残念な事件が起きています。
※参照:「兵庫“知事にパワハラ疑い”文書作成 元局長が死亡」(2024/7/8 NHK)
現職の地方公務員(局長級)が知事のパワハラ疑惑(自身に対するものではなく組織全体に対して)についてマスコミ等の第三者に告発したが、そのことが原因として告発者が停職処分とされ、議会において事実解明のための委員会が設置されたがその開催を待たずに告発者本人が自死したという痛ましい事件です。
首長は様々な理由で組織に対して号令をかけますが、有権者の信任を背景に自らの主張の正当性を信じて疑わない首長は時としてその指示、号令に必要以上の「力」を籠め、部下職員がその「力」を強く感じることがあります。
「自ら公約で掲げた政策を推進したい」「市民の求めることを実現したい」
という政治的価値観は時に
「見栄えの良い成果を出したい」「ライバルを蹴落としたい」
という邪な考えに至ることがあり、また
「次の選挙で勝ちたい」「確実に支持を広げたい」
という政治的思惑も絡まって、政治的に中立で公平公正な職務遂行が求められる公務員に、本来命じてはならない指示をしてしまう。
単なる首長のワガママではなくそこに政治的な意図(パフォーマンス、マウント、政敵への攻撃など)がある場合には、政治的に無色であるはずの我々公務員が泥を被ることを暗に強制され、歯向かうと「お前は俺の政治家生命を奪う気か」と恫喝されることだってあるのです。
首長の号令を実現するために「選挙で選ばれた首長のいうことだから」と職員の思考が停止し、「市民のために」というお題目のもとで上位の者だけの意向で意思決定が行われ、正常な自治体運営ができなくなってしまう。
これが今、起こっていることではないかと思っています。
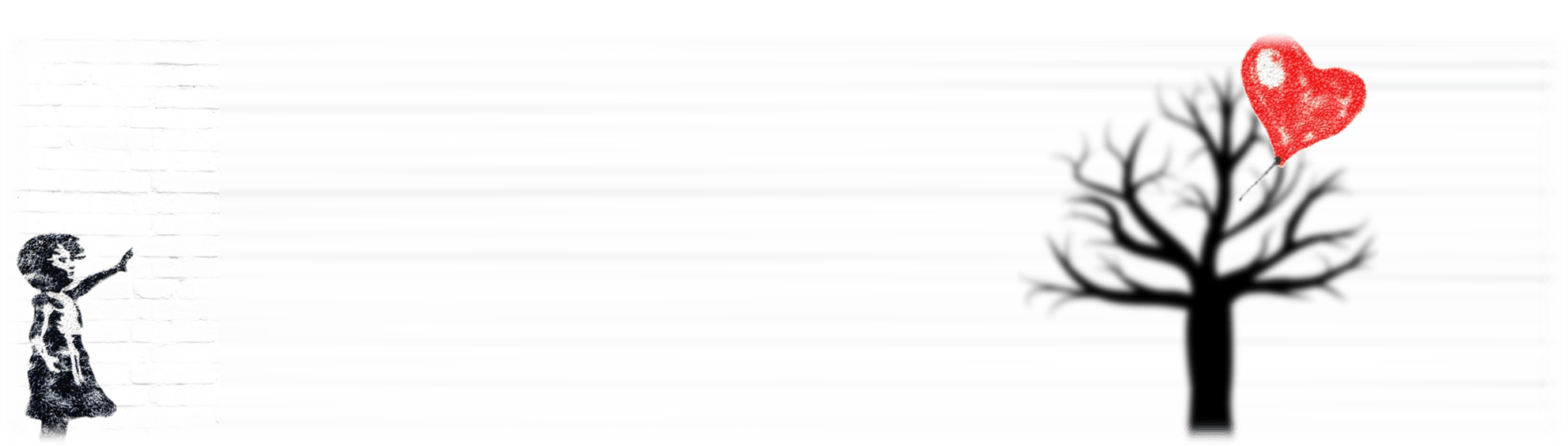
組織の問題はなかったか?
一連の問題はパワハラというワードが強すぎて知事の個人的な資質そのものに焦点を当てた報道になっていますが、告発者の真の意思はパワハラ行為そのものではなくそのことによって県政が歪められてしまったことへの抗議です。
告発者が指摘している7つの項目うち3つは投票の依頼・協力という公務員が関与してはならない政治的行為そのものであり、他にも知事の政治的地位を押し上げるために行われた不正の疑いのある行為が挙げられるなど、県政として本来ならばやるべきではなかったことが知事の命令で行われたとの指摘で、それは単にハラスメント行為が職員への人権侵害であるという問題だけでなくそういう歪な関係性の中で出された業務命令に起因して不適切な行政運営が行われたのではないかという視点で問題視すべきでしょう。
単なるハラスメントならいざ知らず、不適切な業務命令だったとすればそれは知事ひとりで実行できる行為ではなく知事の命令を組織として受け止め、対応した官房部門や事務方も一定の責任を負わなければなりません。
告発者もそのことをわかっていて、政治的な力を背景にした行政運営の歪みについて知り、それをそのまま語ることが憚られたため、知事のパワハラという視点での告発となったのではないでしょうか。
さらに明らかになってきたこと
そんな視点でこの問題を注視していたところ、さらに明らかになってきたのが、知事のパワハラという報道の陰に隠れた、知事側近たちによる横暴、密室での行政運営です。
参照:「人命よりも不正の隠蔽が優先する兵庫県庁、斎藤知事の辞職ではもうすまない」(2024/7/26 JBpress)
私はこの事件発覚の当初より、今回の内部告発に対する犯人捜しや内部調査だけでの断罪を根拠とした人事的な措置などの不適切な処理方法について通常の組織運営ではあり得ない、尋常ではないという感覚を持っていましたが、ここで報じられている一握りの幹部の暴走を許した土壌は何だったのでしょうか。
(「パワハラと暴走・下」に続く)
■ 今村 寛さんの著書紹介
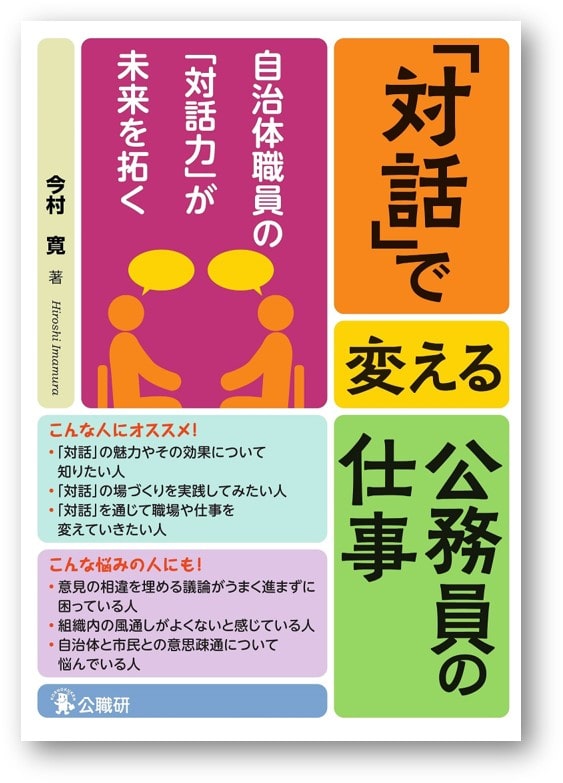
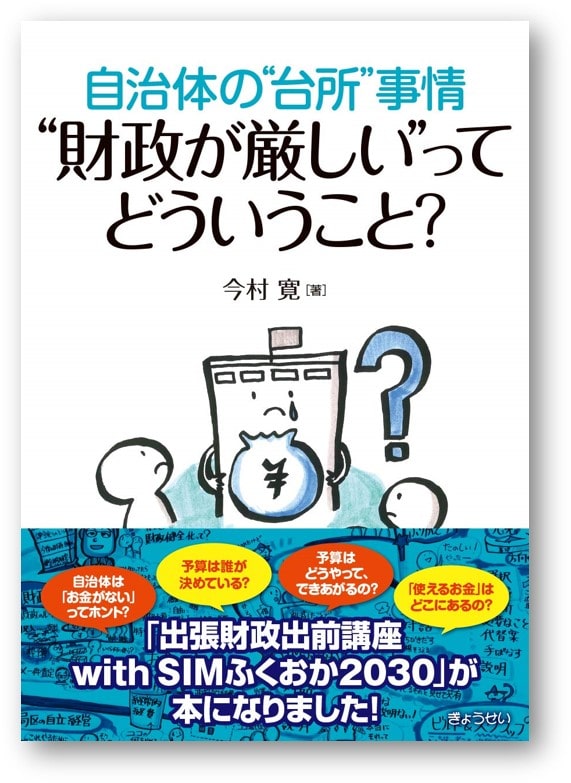
■ 「自治体財政よもやま話」(note)を更新中

%20(1).png)

.png)

