
※下記は自治体通信 Vol.68(2025年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。
明治9年の県域確定から数え、来年で150周年を迎える岩手県政。東日本大震災から14年が経過し、国の第2期復興・創生期間も終了する令和7年度は、同県の震災復興という意味でも大きな区切りの年となる。この令和7年度の予算について、同県知事の達増氏は、「世界に開かれたいわて地方創生予算」と名付け、国が推進する「地方創生2.0」と歩調を合わせて、「岩手らしい地方創生に取り組む」としている。果たして、同県はいかなる地方創生を展開していくのか。同氏に聞いた。

元外交官の経験を活かして、「4つの危機」から脱却
―知事として5期目も半ばを迎える今、これまでの達増県政の成果をどのように振り返りますか。
私が就任した18年前には、岩手県は「4つの危機」に直面していました。「人口減少」「県民所得の低迷」「雇用の低迷」、そして「医師不足の深刻化」という4つの危機を受け、これらの「危機を希望に変える」ことを掲げたこの間の県政を振り返ると、いずれのテーマでも一定の成果をあげることができたと思っています。もっとも顕著だったのは、ここ数年で自動車・半導体を中心に製造業の産業集積が進んだことにより、県内における雇用の確保と賃金水準の向上が同時に進んだことです。これを受け、一時期に比べ、人口の転出超過にも歯止めがかかっています。また、医師不足問題についても、岩手医科大学の定員増加を実現し、その成果として平成28年度以降、県内に若手医師が増え始めている状況になってきました。
―それらの危機克服の過程において、発揮されてきた達増カラーとはどういったものでしたか。
1つには、元外交官として培った「危機管理能力」が発揮できたと思っています。外交官の仕事の多くは、対立や紛争を戦争に発展させない、もしくは事故や災害の被害を最小限に抑えるための危機管理にあります。危機から目を逸らさず、いち早く情報をつかみ、なすべきことを決定し、意思統一を図って実行に移す。この危機管理の鉄則を県政で実践してきました。
もう1つは、新型コロナウイルス感染症の「5類移行」後における県の海外PRにおいても、元外交官としての経験を活かせていると思っています。異文化交流を通じた友好関係の構築は外交官の専門領域ですが、これこそまさに現在の岩手県のインバウンド観光振興の現場で求められていることです。振り返れば、東日本大震災直後の復旧支援において、海外からの支援を最初に受け入れたのは当県であり、その後、「開かれた復興」というスローガンを掲げて国内外から積極的に支援を受け入れてきた経緯があります。世界を意識し、世界に開かれた地方創生の推進は、今後の岩手県政における重要なテーマにほかなりません。
「地方創生2.0」は、海外に開かれているべき
―岩手県では、令和7年度予算も、「世界に開かれたいわて地方創生予算」と命名していますね。
地方創生10年の反省を踏まえてスタートした「地方創生2.0」は、海外に「開かれた地方創生」であるべきだと私は思っています。インバウンド観光や県産品の輸出を通じて、「海外からの評価」をテコにしながら地域の振興を図り、人口減少に歯止めをかけていくという戦略です。コロナ禍以降、日本全国でインバウンドが回復していますが、特に当県をめぐっては、令和5年1月の米紙ニューヨーク・タイムズが「2023年に行くべき52ヵ所」に盛岡市を選んだことが1つの契機となり、海外から大きな注目が集まるようになっています。高まり始めた海外からの評価は、さまざまな資源を当県に呼び込むことにつながり、各種の政策を推進する際の大きな原動力にもなりえると考えています。この戦略は、岩手県政の長期計画である「いわて県民計画」の推進においても同様に考えています。
―「いわて県民計画」では、どのような政策目標を掲げていますか。
「いわて県民計画」においては、知事の任期に合わせた4年間の「中期計画」を策定しており、現在進行中の中期計画「第2期アクションプラン」では、4つの重点事項を設定しています。すなわち、「人口減少対策」を主軸とし、「グリーントランスフォーメーション(以下、GX)の推進」「デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」をその両翼に配置し、これらを支える基盤として「安全・安心な地域づくり」を位置づける体系としています。あらゆる個別政策はこの4つの重点事項に包含されることになるわけですが、人口減少対策やGXを推進する際にも、国際戦略を絡めて、世界に開かれたかたちで各種政策を強力に推進していく計画です。
国際戦略が政策の推進力に
―具体的に教えてください。
たとえば、「人口減少対策」をめぐってはまず、多種多様な雇用を県内に創出していくための積極的な産業振興策を1つの柱と位置づけています。そこでは、国際競争力を持った自動車や半導体といった製造業のほか、ブランド米や和牛といった農畜産物、さらには南部鉄器や漆器、その他伝統工芸品といった、いずれも世界市場で受け入れられている地場産業を、特に力を入れて振興していきます。
また、「GXの推進」については、再生可能エネルギーの県内自給率が50%に迫ろうとしている現在、大手自動車メーカーの県内工場では、水力発電由来の電力100%で自動車を生産する動きがすでに始まっています。カーボンニュートラルで生産される自動車は、欧州市場などで高く評価されていることが背景にありますが、これなども国際戦略が政策の推進力となっている1つの好例といえます。

―確かに、世界への意識が岩手県政の1つの特徴ですね。
来年は岩手県政150周年の節目となりますが、その間には、国際連盟の事務局次長を務め、著書『武士道』で日本の精神文化を欧米に紹介した新渡戸稲造や、外交官出身として国際協調路線を貫き、日本初の本格的な政党内閣を率いた原敬といった国際人を輩出しています。さらに遡れば、岩手県は江戸時代から南部藩として蝦夷地防衛を任され、黒船来航より50年以上も前から国際関係の最前線で外交・防衛の洗礼を受けてきた歴史もあります。そうした歴史からも、世界的視野が、岩手県には根づいているのかもしれませんね。
「いわて県民計画」は、県民の「希望インデックス」
―最後に、政策実現の先にどのような県の未来を描いていますか。
これまで述べてきたように、世界に開かれた魅力や先進性を磨きながら、「いわて県民計画」が掲げる「一人ひとりの県民が希望を持てる岩手県」の実現をめざしていきます。そのために県政運営において意識すべきは、「情報」を重視する姿勢だと思っています。「情報」こそが危機や絶望を希望に変えていく推進力だと考えているからです。県民一人ひとりを意識した的確な情報収集に基づいて県政を進めることができれば、「県民の計画」と名称を改めた狙いの通り、「いわて県民計画」が県民一人ひとりの希望がつまった「希望インデックス」となりえる未来を実現できると考えています。
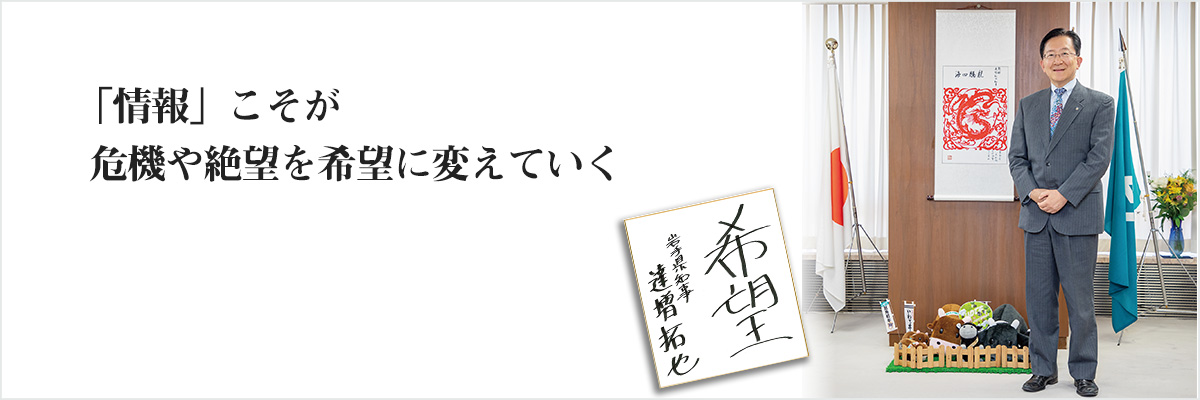

%20(1).png)



