
※下記は自治体通信 Vol.68(2025年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。
令和7年に開港400年の大きな節目を迎えた青森市。古くは弘前藩の港町として栄え、その後も港とともに発展してきた歴史を持つ同市だが、現在は多くの地方都市と同様、人口減少や若年層の転出超過に直面している。そうしたなか、令和5年に市長に就任した民間企業出身の西氏のもと、同市では「DX先進都市」「子育て先進都市」をめざすべき都市ビジョンに掲げ、若者世代に地域の魅力を訴求する施策に力を入れているという。その詳細を同氏に聞いた。

「DX先進都市」「子育て先進都市」を標榜
―令和5年6月の市長就任にあたり、どのような使命感を持っていたのでしょう。
私は長く、青森商工会議所の副会頭として、行政とともにまちづくりに汗を流してきました。そのなかでは、青森市は全国でもトップクラスのスピードで人口減少や少子高齢化が進行しているとの認識があり、地元経済界としても真剣に対策に取り組まなければならないという危機感を持っていました。そうした背景から、就任にあたっては、「DX先進都市」「子育て先進都市」という2つのめざすべき都市ビジョンを掲げ、民間出身ならではのスピード感を持って取り組む決意でのぞみました。実際に、就任から1年半の間に、公約に掲げた重点施策には100%着手し、それに関わる事業予算についても100%予算化している状態です。
―具体的に、どのような政策を打ち出しているのでしょう。
私は市政運営において、「仕事をつくる」「人をまもり・そだてる」「まちをデザインする」という3つの柱を打ち出しています。
青森市が直面する人口減少を分析すると、やはり高校卒業後、もしくは大学卒業後、進学や就職を機に若い世代が地元を離れてしまうことが社会減の大きな要因となっています。いちどは都会に出るのも大切なことですが、問題はその後も戻ってこない若者が多いことで、これは市内に働く場が少ない現実を物語っています。「仕事をつくる」とは、そうした若い世代の受け皿づくりを最優先課題に据えた政策です。ここでは、地域全体のDX推進がカギを握るとも考えており、「DX先進都市」という都市ビジョンを掲げた背景の1つにもなっています。
「地元に戻る」選択肢が、つねに頭にあってほしい
―「人をまもり・そだてる」においては、どういった政策を推進するのですか。
ここでは医療、福祉の充実のほか、未来を担う人材を育てる「子育て支援」や「教育環境の充実」を重要な政策テーマに掲げており、ここでも念頭にあるのは、若者世代への訴求です。これまでの青森市政は、高齢者向けの福祉施策に重点が置かれていましたが、これからは子育て支援や若者政策にも十分に資源を配分しなければいけません。こども・若者政策の司令塔として、今年4月に「こども未来部」を新設したのもそのためで、もう1つの都市ビジョンである「子育て先進都市」に向けた政策を強力に推進していきます。
―いずれの柱でも「若者への訴求」を強く意識されているのですね。
将来にわたって活力ある地方都市としてあり続けるためには、若者世代に共感を持ってもらい、選ばれるまちづくりをしていかなければならないと思っているのです。いちど都会に出た若者たちにも、「地元に戻る」という選択肢がつねに頭の中にある状態でいてもらいたい。そのためには、若者世代を意識した政策や、地元へのシビックプライドを育てる取り組みは非常に重要だと思っています。
青森市は、第二次世界大戦で空襲によって一帯が焼け野原になったため、歴史的建造物がほとんど残っておらず、歴史的資料も多くが消失してしまった不幸な過去があります。そのため、「お城がある弘前市とは違って、青森市には歴史がない」などと思っている市民は多いのです。しかし、それは大きな誤解であり、かつては弘前藩の藩港として栄えた豊かな歴史を持つ地域なんです。
―港とともに発展してきたまちなのですね。
まさにそのとおりです。青森市は、中心市街地が海沿いに発展した特殊な都市形態が特徴であり、船を降りるとすぐに街中エリアがひろがっています。近年は、海沿いのエリアに緑地公園が整備され、商業施設やミュージアムなども続々と整備されています。インバウンド客数が全国でもっとも早くコロナ禍以前の水準を回復した都市の1つでもありますが、その原動力になっているのも青森港に寄港するクルーズ船であり、その数は今年、過去最高を更新する予定です。
青森港をめぐっては昨年、国が進める洋上風力発電事業の建設拠点となる「基地港湾」に指定され、3年後からの使用をめざして整備が進んでいます。大きな経済効果が期待されており、先の「仕事をつくる」政策にも、大きな目玉と期待しています。まさに、港の存在とは切っても切れないまちです。そして今年は、青森港開港400年の年でもあるんです。
地域を学ぶ「青森学」で、まちへの誇りや愛着を育てる
―この大きな節目は、青森市にとってどのような年になりますか。
青森市の歴史を振り返り、港町としてのプライドを胸に秘め、港町青森をどう発展させていくか、みんなで一緒に考える良いタイミングにしたいと思っています。青森市ではこれまで、こどもたちが地域を知る機会が少なかったとの反省から近年、市内の小中学校で地域の歴史や文化を学ぶ「青森学」という学びの時間を設けています。こうした学びを通じて、まちへの誇りや愛着を感じてくれるこどもたちも増えています。毎年、桜のシーズン前に地域の公園の清掃や枝拾いを行う際は、多くの小中学生が参加してくれます。商店街の街頭での花植えなどにも進んで参加してくれるこどもたちも多いです。市政運営の3つ目の柱に私は「まちをデザインする」と掲げていますが、こうした活動に若い世代が自ら参画してくれることが、住みよい持続可能なまちをつくる第一歩になるはずです。シビックプライドとは、単にまちが好きという感情ではなく、このような「まちを良くしているのは自分である」という誇りを持つことにほかならないと私は思っています。

まちの新しい歴史を築き、未来につないでいく
―最後に、今後の市政ビジョンを聞かせてください。
当市の総合計画が定める将来の都市像は「みんなで未来を育てるまちに」です。青森市には課題も多いですが、一方で観光客数の増加や洋上風力発電の基地港湾選定といった追い風も吹いています。過去を振り返れば、戦禍から復興を果たし、数々の困難を乗り越えてきた歴史もあります。400年の節目に、先人たちが紡いできた歴史にあらためて想いを寄せながら、市民がともに手を携えてまちの新しい歴史を築き、それを未来につないでいきたいと考えています。
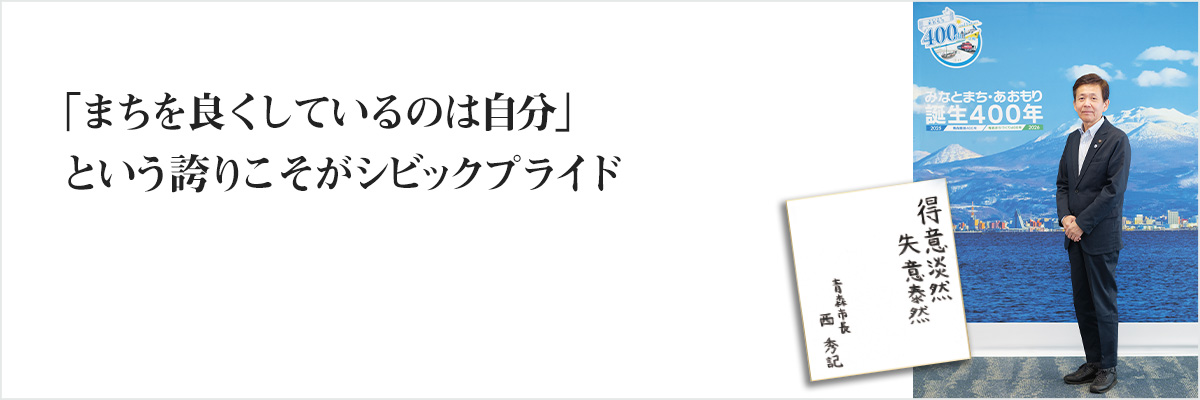

%20(1).png)



