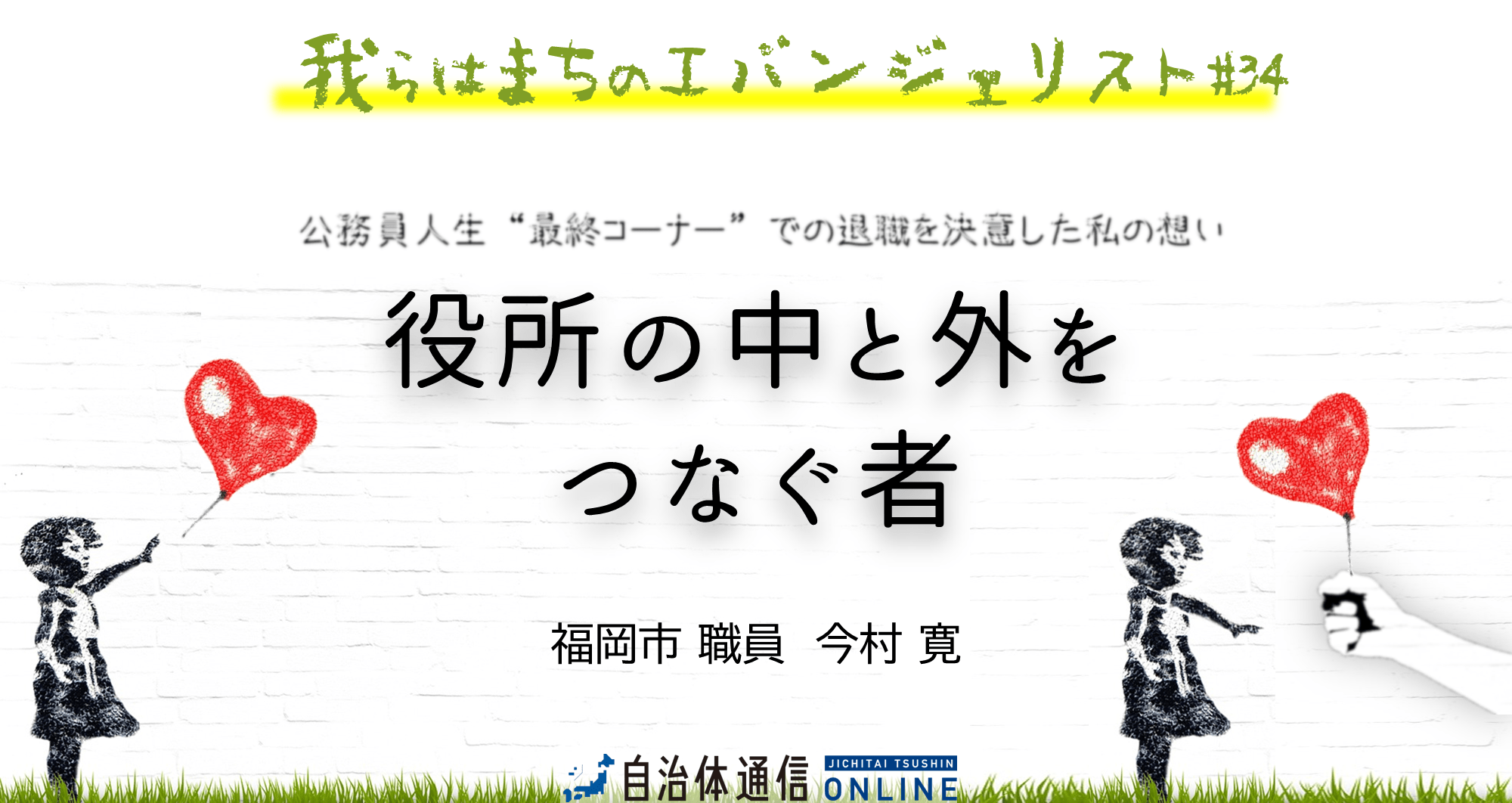
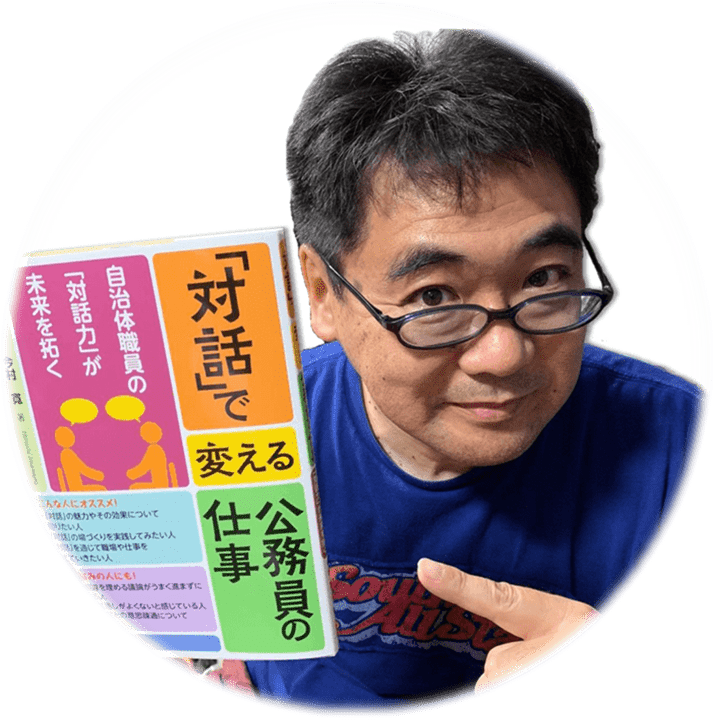
今回で全34回を迎える本連載の最終回。連載筆者の今村さんから読者のみなさんへの惜別のメッセージを、是非お読みください。
突然ですがご報告です
本年12月末を以て福岡市役所を退職することにしました。
退職の理由ですが、50代後半に差し掛かり今後の人生を展望する中で、夫婦に残された人生の時間をより有意義なものにするためには、時間や職責の制約から解放され、自分たちのペースで日々を過ごし、心の落ち着きと安らぎのある暮らしに切り替えていきたいと強く感じているためです。
このため、退職後は特に組織や団体に雇われて勤務するのではなく、個人事業主としてプライベートの時間とのバランスを取りながら、これまで在職中に手掛けてきた自治体財政をテーマとした講座の出講や対話の場づくりなどを引き続き行い、自治体の経営改革や公務の能率向上、人材開発、官民連携等の支援を行っていく予定です。
福岡市役所に奉職して33年9ヶ月。この間、組織内外で私を支え、苦楽を共にしてきた皆様方には言葉にならない感謝の気持ちでいっぱいです。
福岡市役所で働いてきたことで世の中の役に立つことができる今の私が形作られてきたことは間違いなく、そのことをとてもありがたく思う一方で、ここまで育ててもらった組織から離れることに寂しさやすまなさを感じてもいます。
来年からは市役所を離れ公務員の身分ではなくなりますが、福岡を愛し、福岡のために働きたいという気持ちに加え、福岡という枠を越えて世の中のために自分の力を尽くしたいという気持ちに変わりはなく、中身はまったく同じですので、引き続きおつきあいのほど、よろしくお願いいたします。
これまで私の市役所生活を支えていただいた全ての皆さんに深く御礼申し上げるとともに、これからも変わらぬご厚情ご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

中途退職者が増えている理由
定年を待たずに地方自治体の職場を離れて新天地へ旅立つ仲間が近年とみに増えています。
退職の理由は人それぞれですが、世間で報道されているような給与等の待遇面での不満だけではなく、むしろ新天地で得られるものや果たしたい役割への期待からの転職ではないかと思われます。
とはいえ、地方公務員という安定した身分を捨てることで収入が変動するリスクは当然あり、また理想に燃えて新天地へはばたいたとしてもその思いが叶うかどうかでさえ保証はありません。
それでもリスクを承知で新たな道を探る公務員仲間が増えているのは、社会全体の人材流動化の動きももちろんありますが、地方公務員として自治体で働く現状に対して何らかの不満が起爆剤となっていることは否めません。
私が今回、退職を決めたことを伝えると、自分も同じように考えていたという方やもう退職を決めたという方にかなりの確率で出会いました。
私自身は今の仕事が嫌でそこから逃げるために辞めるというわけではないのですが、皆さんが今の仕事を続けることに疑問を持つ環境はよくわかります。
私たちの業界が抱えている課題はとても深くて重く、一人の力で抗うことはできないと改めて感じました。
公務員を辞めて転職した方、あるいは転職を検討している方が自らの職場に不満を感じていることの多くは「お役所仕事」という言葉に代表される「形式的で時間がかかり、実効の上がらない仕事ぶり」が温存され一向に改まる気配がないことではないでしょうか。
この現状を変えたいといくら熱望して実際に行動を起こしても、自分だけの力ではこの巨大で強固な岩盤を穿つことはできず、「組織が旧態依然のままで変革が期待できそうにない」と変革をあきらめ、新天地へ羽ばたいていくというのが実情ではないかと思います。
私たち地方自治体職員は、その変革の必要性に気づいていないということではなく、ほとんどの場合はわかってはいるけど動き出すことができない(したくない)ということなのですが、その現状を打破するために必要なものは何でしょうか。
改革を支えるものは「民意」
一部の「意識の高い」公務員が変革の必要性を叫び、改革を進めようとしてもあれこれ難癖をつけて牙を抜き、爪を折ってお蔵入りにしてしまう現状肯定型の公務員組織を変える一番確実な方法は「民意」だというのが私の考えです。
私たち公務員は市民の声、市民の目線をとても気にしています。
自治体組織の「変革」についても、多くの市民がそう感じている、あるいは少なくても強く「求める」市民がいるという事実は、公務員の重い腰を上げるのには効果があるでしょうし、現状を変える「変革」へのためらいを払しょくし、舵を切ることを決断させるのもまた民意です。
前例踏襲や事なかれ主義に走ろうとする公務員がその殻を破り改善改革の一歩を踏み出すのに彼らが欲しがる「安全性の確保」。
新たな判断を下しても大丈夫ですよ、誰もあなたを責めませんと、改めて市民からのお墨付きをもらいたいという心理もあるのです。
地方公務員の中途退職理由となっている「変革が期待できない」という状態を変えていくことができるのは「民意」を私たち公務員自身がいかに感じ取ることができるかにかかっています。
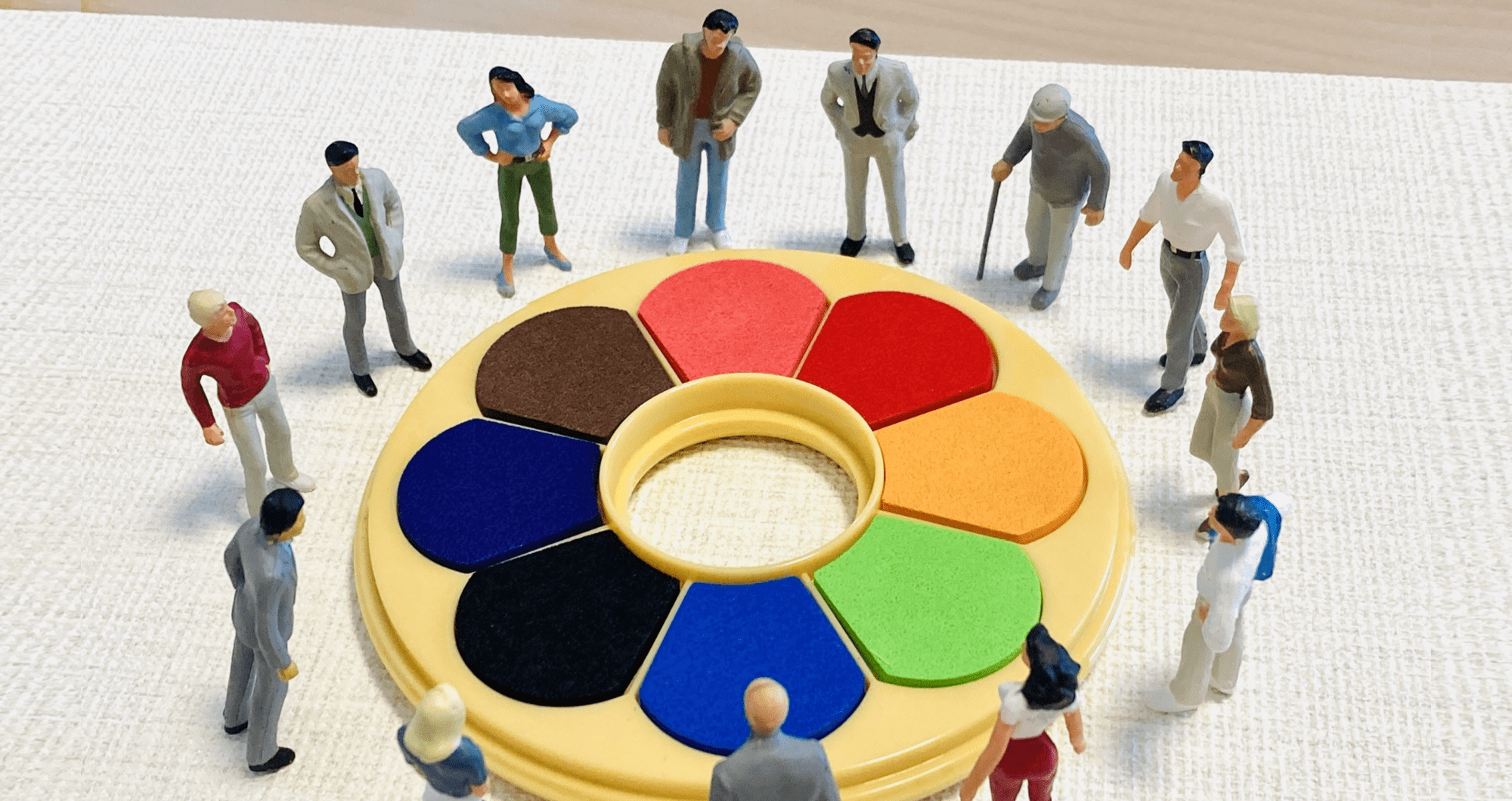
多様な民意を「感じ」取ろう
市民の目線を持って自分たちの仕事を検証し、市民の付託に真摯に対応すべく自らを変革していくことができるようになるには、まず市民が何を求めているか知るために市民の声に耳を傾けることが必要です。
市民の声を聴き、求めるものが理解できれば、動けないわけではないはず。
逆に市民から見れば、今、自分が求めていることを行政組織としてどう考え、どう取り組んでいるかが見えないために、そもそも市民の側から何を求めてどう声を上げていくのかがわからないという現状もあります。
「対話」で変える公務員の仕事
ここでいう「民意」は選挙で示されるものだけではありません。
私たち公務員、あるいは私たちの仕事ぶりがどう思われているのか、市民の皆さんに見えているもの、わからないと感じていること、ひょっとしたら私たち公務員が気づいていないけれども生じているちょっとしたすれ違いなどについて忌憚なく語る機会があれば、と思います。
大きな組織にありがちな、組織の中の常識、論理で動く「たこつぼ化」。
私たち公務員は、ひとつひとつの組織は小さくても、国、都道府県、市町村という大きな括りの中で、公務員ムラという閉ざされた世界に安住してしまっています。
私たち自身がその中から出てきて心を開くべく、互いの違いを認め合いながら、互いの求めているものを理解し合い、その溝を埋めること、距離を縮めることのために、外側にいる市民の皆さんからも気軽に声をかけていただけるよう、そんな関係性の良き隣人としておつきあいいただけるよう、胸襟を開き市民との「対話」の場に身を投じることが必要だと思います。
組織の縦割り打破にしても、行政と市民とのすれ違いからくる「お役所仕事」の一掃も、私たち自身が自分の職場で与えられた職務を遂行する際の愚直な忠実さが一因となっています。
私たちは公務員として法令を遵守し、上司の命令に従い、組織の使命を達成するために全力を尽くす「組織の使命に忠実であらねば」という呪縛に囚われているのです。
公務員ならではの強い使命感も大事ですが、この強い囚われからの解放が、市民への心を開き、市民の立場、意見を理解することにつながります。
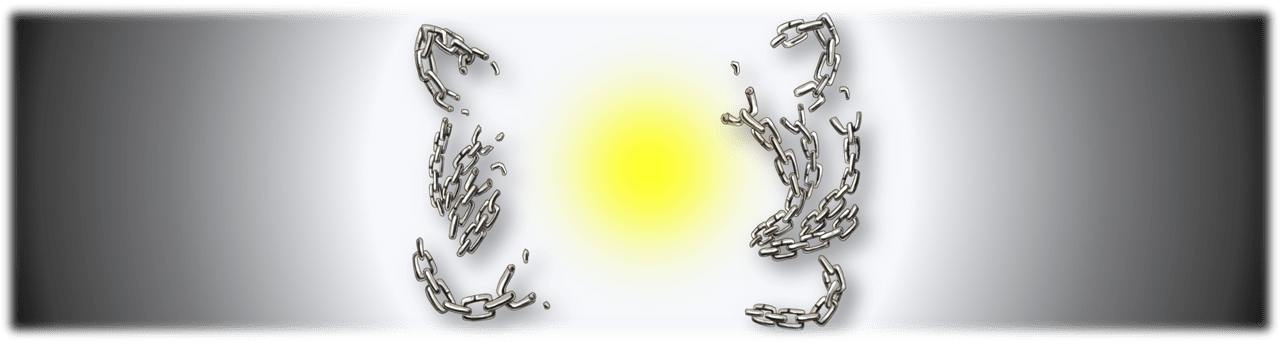
私たちが職務を離れ個人として自分らしくあることができる居心地の良い職場。
これまでの個人的経験に紐づいた自分自身の価値観や思いを言葉にし、共有できる風通しの良い職場。
行政と市民とのすれ違いや組織の縦割りに起因する「お役所仕事」の一掃は、私たち公務員自身の心を解放することができる、居心地の良い、風通しの良い職場づくりからはじまるのかもしれません。
中と外をつなぐ伝道師(エバンジェリスト)として
まずは我々公務員が現状を内側から語り、そのことについて市民からの忌憚のない意見をもらえる自由な対話の場を設け、そこでたくさんの公務員と市民が直接つながって互いの立場を超えた情報共有と行政側、市民側の相互が共感できる関係性が構築されることが「変革」に向けた第一の工程です。
既に役所の外に旅立っていった“辞め公”の皆さんの多くは、この工程に必要な自治体組織と市民との対話の橋渡し役として新天地で活躍されているのではないでしょうか。
そういう意味で、彼らが地方公務員の道を離れた理由は決して現状からの逃避ではなく、追い求める理想の自治体像に向かって「変革」を進める先遣隊として、自治体の外に出て、自治体に残った我々とともに改革を進めるためなのだろうと思っています。私もそのひとりとして自治体の中と外をつなぐ架け橋、対話の伝道師(エバンジェリスト)となり、自治体の中でこれから先も踏ん張り続ける仲間たちが働きやすくなるよう、辞めたいと思わなくて済むよう、そして市民にとって本当に役に立つ仕事ができるよう、全力を尽くしたいと思います。
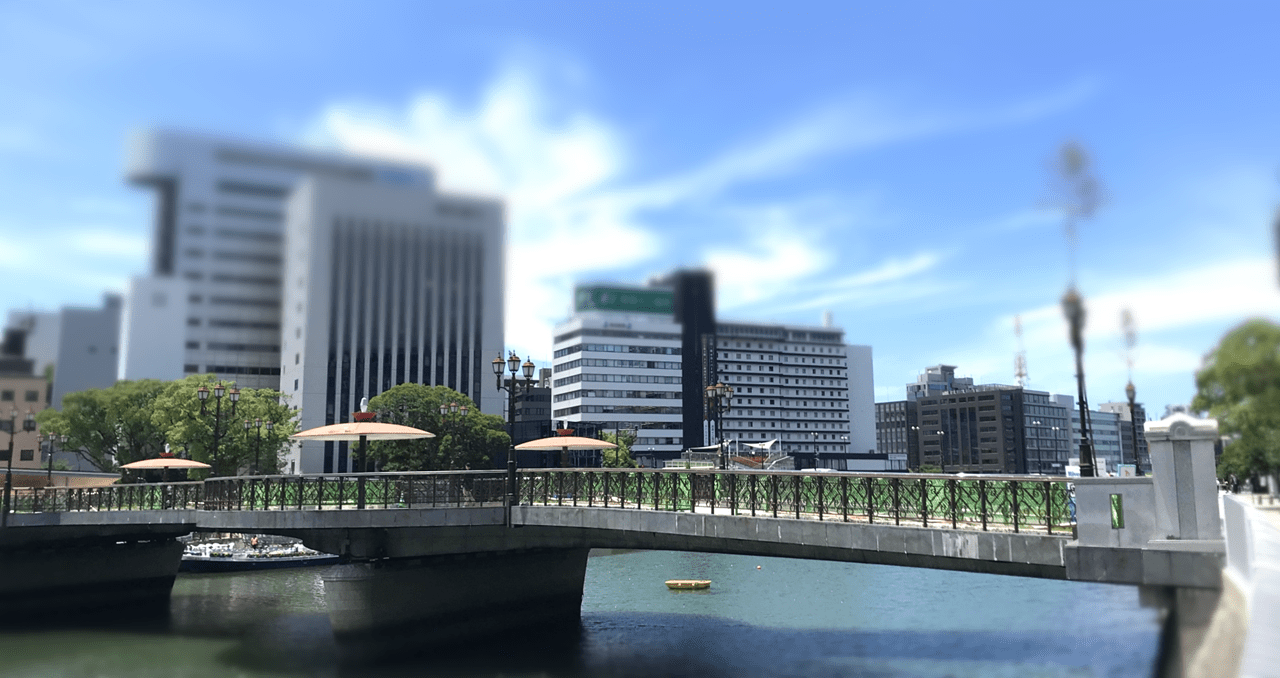
画像は福岡市の「福博出会い橋」。かつて川を挟んで分かれていた「博多」と「福岡」というふたつの町が出会い、つながってゆくという想いをこめて名づけられた
~終わりに~
2021年の10月から3年にわたり不定期で寄稿してきました「我らはまちのエバンジェリスト」は今回を以ていったんの区切りとさせていただきます。
長らくのご愛読、ありがとうございました。
■ 今村 寛さんの著書紹介
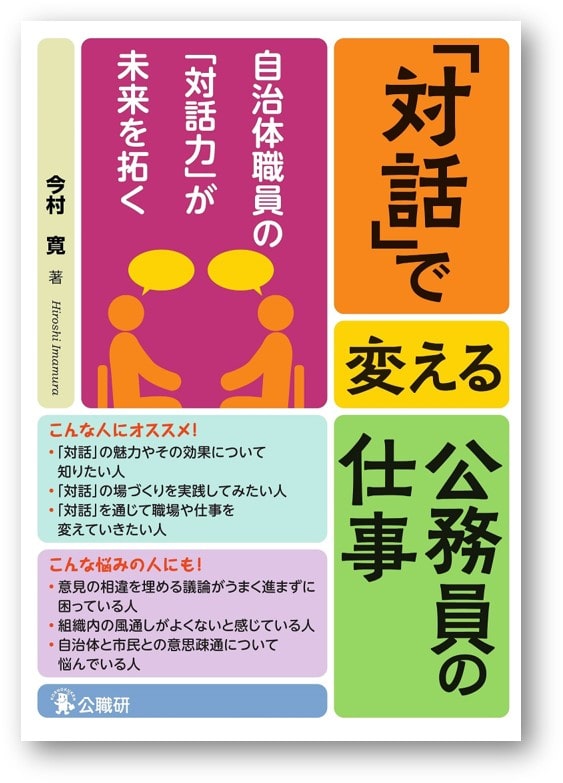
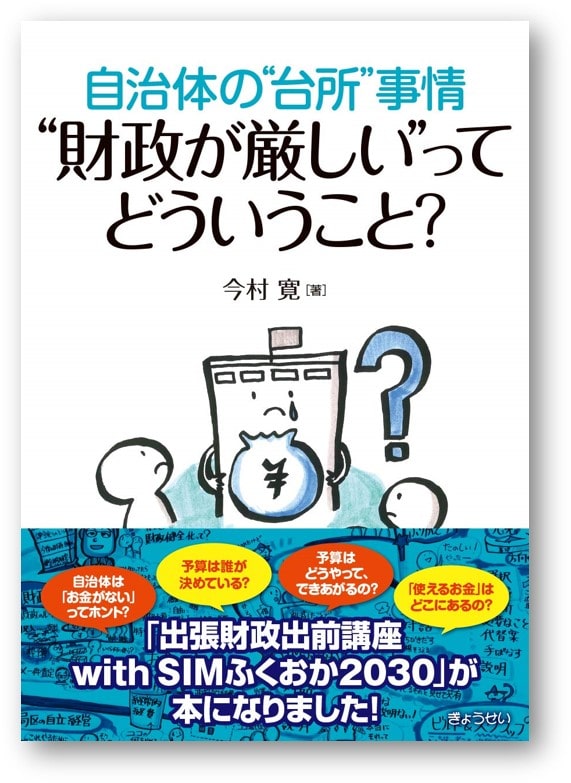
■ 「自治体財政よもやま話」(note)を更新中

%20(1).png)




