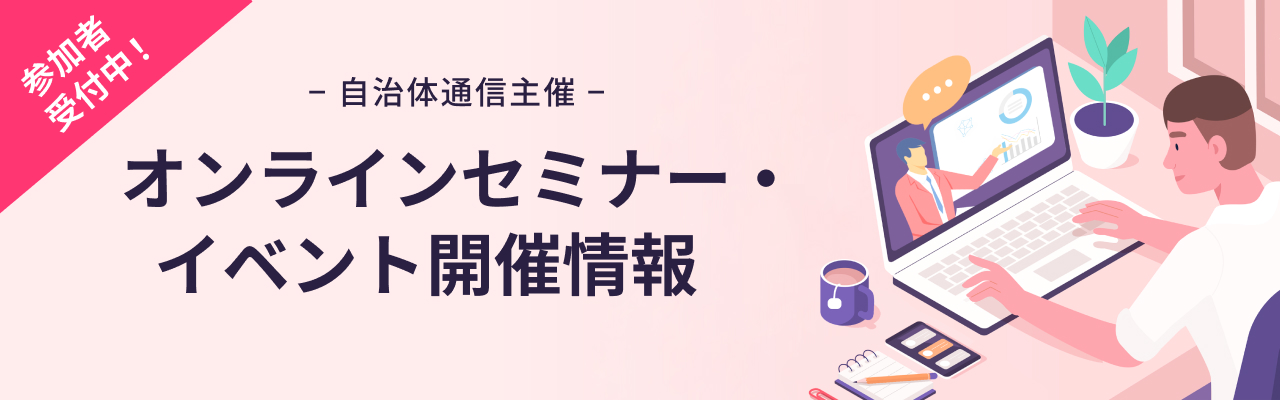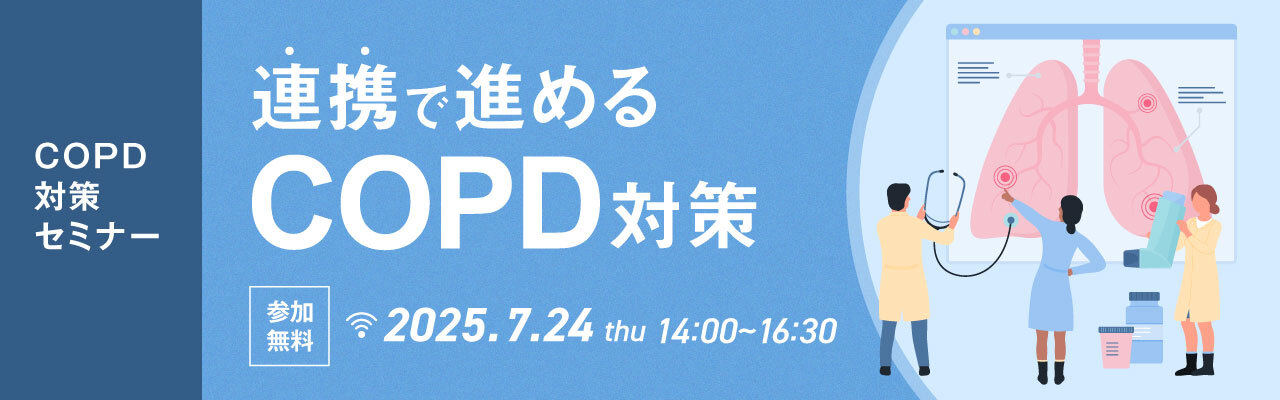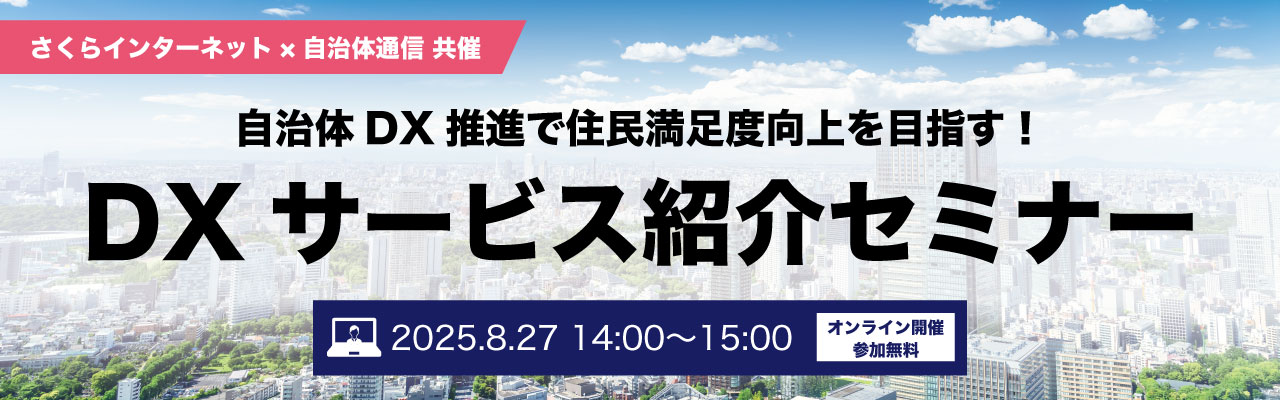地方創生の効果を上げる“4つのノウハウ”
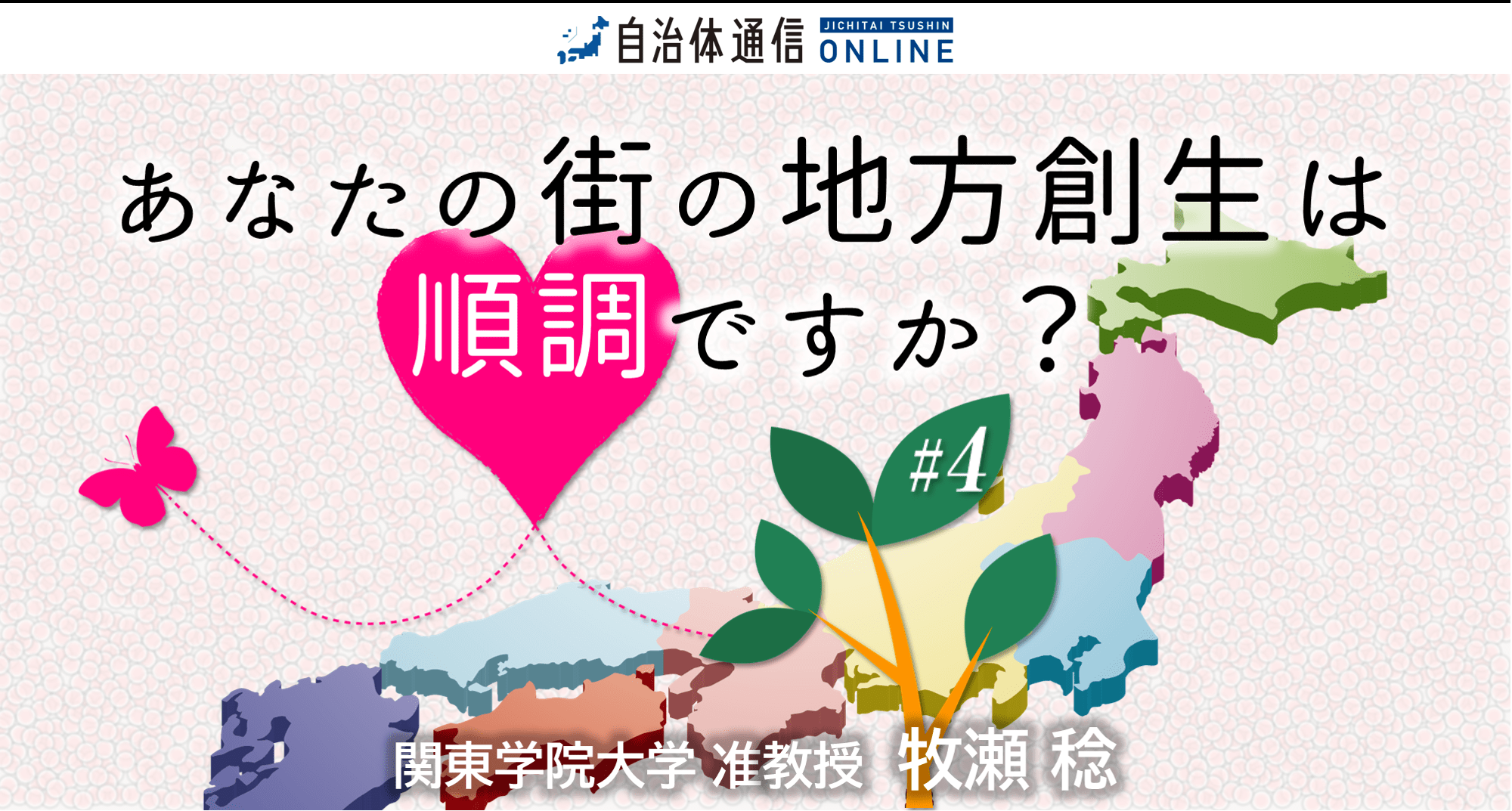
【自治体通信Online 寄稿連載】あなたの街の地方創生は順調ですか?④(関東学院大学准教授・牧瀬 稔)
自治体の地方創生プロジェクトをサポートする民間企業に効果を上げる地方創生のあり方を取材しました。取材したのは多くの支援実績がある大手広告代理店、読売広告社の北村 俊明氏(ひとまちみらい研究センター プロデューサー)、五十嵐 勇氏(同)、上野 昭彦氏(都市生活研究所 所長代理)。本連載の執筆者である関東学院大学法学部の牧瀬稔准教授のゼミ生である齋藤 洋香さん(法学部地域創生学科3年)、越 達哉さん(法学部地域創生学科3年)、峰尾 涼さん(法学部地域創生学科3年)、柴田 亜実さん(法学部地域創生学科2年)、鈴木 海人さん(法学部法学科2年)が“若者世代の視点”で聞き、牧瀬准教授が監修しました。
【目次】
■ 「ヒトづくり」が最重要
■ 「自走」を目指す
■ 地域の強みを活かす
■ 地域資源をブランド化
■ 「まちの魅力」をつくりだす
「ヒトづくり」が最重要
―読売広告社が地方創生に取り組んでいる経緯や理由を教えてください。
地方自治体や地方企業の課題に対して、これまでに広告会社として培った知見をまとめて、地方創生・地域活性化というテーマに応えるためです。そのプロジェクトとして、2年ほど前に、ひとまちみらい研究センターという社内プロジェクトを立ち上げ、より専門性が高いチームをつくりました。そして、2019年4月から、ひとまちみらい研究センターは、プロジェクトが発展する形で正式な部門になりました。
我々がこれまで従事してきた中で、地域にあるニーズには、大きく分けると、観光振興、産品開発、移住定住促進の3つに分けられると考えています。これらの課題に対して、そのソリューションを提供するという専門的な部門が、ひとまちみらい研究センターです。

我々のアプローチの考え方として、「ヒトモノコトバ」というテーマがあります。観光振興、産品開発、移住定住促進といった、地域にある3つの主要ニーズに応えるため、考えてきたことは「ヒトづくり」「モノづくり」「コトづくり」「場づくり」の4つです。
この中で一番重要なのは、ヒト(担い手)づくりです。地方創生は我々が地域に入っていって瞬間的に盛り上げても持続しません。そのため、その現場にいる人達、つまり人をつくることが一番重要です。
「自走」を目指す
モノづくりというのは、産品開発などです。
我々の特色として、クライアントの商品やサービスの開発を支援する活動を行っています。我々が持っているクリエイティブ力やコミュニケーションスキルを活用したモノづくりのあり方が地方における産品開発にも生きています。
コトづくりというのは、イベントのような体験設定などから始めていきます。
場づくりというのは、地域のアピールの拠点を作るといったようなことをしています。例えるならば当社が得意としていたマンション販売における販売センターやモデルルームのようなものです。
自走することを目指して「ヒトモノコトバ」としています。「ヒト」が最初に来ているのは、ヒトづくりが大切で、まずなくてはならないからです。そういったことを我々はやっています。
地域の強みを活かす
―具体的な地方創生における取り組み内容を教えてください。
まずは、観光振興の取り組みについて「南島原食堂」「鳥取美人物語」「アヒル隊長霧島温泉大使」の事例を紹介しましょう。
南島原食堂
南島原市(長崎)では、観光客を主なターゲットとし、地元の廃校を活用して食堂をつくりました。地元特産のそうめんを活用したオリジナルメニューなどを提供しています。当時の走りであったインスタ映えも考えています。
ここは地元の女性たちで運営してもらっています。サスティナブルに、ずっと継続的に、この廃校利用を続けていけるようにするためです。
鳥取美人物語
鳥取県は、秋田美人、加賀美人、京美人、越後美人とならぶ五大美人産地のひとつだそうです。食べ物から自然まで楽しむことによって旅人まで美しくなるというコンセプトで、観光資源を鳥取美人が紹介するWeb展開をしました。
アヒル隊長霧島温泉大使
霧島市(鹿児島)は、温泉が有名です。当社が提供しているキャラクターのひとつに、アヒル隊長があります。そのアヒル隊長に霧島市の温泉大使に就任してもらいました。お風呂とアヒルは相性がいいので。
温泉がたくさんあり、かつ家族で入るような温泉が多いため、子どもと一緒に入る「浴育」というコンセプトにし、お風呂を楽しみませんかと、観光客を含め地元の人も、多くの家族連れに来てもらって、温泉を楽しむという企画を行いました。
地域資源をブランド化
次に、産品開発についていくつか紹介しましょう。地域の恵まれた素材を使って、どのような商品開発をするか、そしてどのようにPRを行うのかという取り組みについてです。紹介するのは「三戸精品」「津軽半島 浜小屋仕込み」「NEBUTA STYLE」です。
三戸精品
三戸町(青森)では「地産外消をしたい」「付加価値をつけた商品開発をして首都圏で多くの商品を売っていきたい」というニーズがありました。この地域では、リンゴをはじめ、ホップ、がまずみ、ぶどう、さくらんぼなど、たくさんの農産品があります。それらを、ジュース、ビール、ジャム、チップスなどの加工品に仕立てて、首都圏で販売しています。
三戸町に地域商社を設立し、これら商品の製造販売をしています。
地域商社とは、地域に根差した、地域の雇用促進をして外貨を獲得する活動をしている会社のことです。そこに当社も出資をさせてもらい、経営にも参画しています。

津軽半島浜小屋仕込み
青森県津軽半島の商品開発では、首都圏から青森県に来県した人が旅の思い出として買って帰る青森県を代表するようなお土産づくりを目指して取り組みました。
統一ブランドをつくり、そのブランドの下で地元にある複数メーカーが自社の既存商品をリパッケージして商品群を生み出す、というものです。統一ブランドの開発やパッケージデザイン、商品名や商品説明コピーの考案、容量や価格設定などを検討しながら進めていきました。
「津軽半島浜小屋仕込み」のブランドの傘の下で、短期間で10数種類の商品を作りました。いまでは県を代表するお土産になっています。
NEBUTA STYLE
日本を代表する祭り、青森のねぶた祭りにも関わっています。
ねぶたは、1年近い期間をかけて作られますが、その年の祭りが終わるやいなや解体し廃棄されてしまう存在です。彩色和紙で作られた美しいねぶたを再利用しないのはもったいないですよね。
青森県では、300万人近くの集客を誇る祭り以外の期間に通年でねぶた祭りを感じてもらいたい、さらには日本のみならず世界にねぶたの魅力を発信していきたいと考えておりました。そこで、どうやってねぶたの魅力を発信していこうか、どのようにねぶたを楽しんでもらおうかを考えたときに、ねぶたの美しさを伝える商品ブランドをつくることにしました。
廃棄される前に和紙を切り取って、照明器具としてアップサイクル(リサイクルとは異なり、単なる素材の原料化や再利用ではなく、元の製品よりも次元・価値の高いモノを生み出すことを最終的な目的とする持続可能なものづくりのこと)しました。

おかげさまで評判を呼び、活動が評価され、いくつかの賞をいただいたり、マスメディアで紹介され話題になり、ねぶたもこの照明器具も世界的に評価をいただきました。
それをきっかけにして、照明器具のバリエーションを増やし、その他にねぶたの技法を活用した内装を行ったり、ねぶたに親しみをもって楽しんでもらえるようお土産品としてフェイスパックや文房具などの雑貨もつくりました。ねぶたというものを、商品を通じて、年間で楽しんでもらおうというねらいがあります。
また、地元でねぶた制作を行っているねぶた師の竹浪比呂央さんと当社が一緒になって、LLP(有限責任事業組合)を地元青森につくりました。いまでは、この事業体がこれらの照明や雑貨品を製造販売しています。そして生まれた収益は、ねぶた師を目指す後継者の育成にあてられています。
「まちの魅力」をつくりだす
次に移住定住促進について「柏の葉キャンパスシティ」「手をつなぎたくなる街 湘南ひらつか」の取り組みを紹介します。
柏の葉キャンパスシティ
柏市(千葉)では、何もないところから新たな街をつくって、ここで色々な生活や文化発信の拠点にしているような活動をしています。
手をつなぎたくなる街 湘南ひらつか
平塚市(神奈川)では市民が住み続けたくなる街ということで、主にSNSを活用して平塚市民から写真を応募するなどしていただき、市民のシビックプライドを高める活動を行いました。
最後に、上記3つには当てはまらない取り組みもあります。それはつがる市(青森)のアンテナショップ「果房メロンとロマン」および多摩市(東京)のシティプロモーションです。
つがる市アンテナショップ「果房メロンとロマン」
これは、つがる市の特産品のひとつであるメロンに特化したテーマ型のアンテナショップです。都内の神楽坂にあります。
つがる市は、農業が主要産業ですが、その農家の数がどんどん減ってしまっています。そこで就農促進として、Iターン、Uターンで就農者を増やすことを目的として、首都圏でどのようにしたら就農者を集められるかについて考えました。
実は青森県の年間メロン収穫量は全国4位で、その7割がつがる市で生産されています。そこで、メロンに特化したアンテナショップをつくることで来場者に関心をもっていただき、その後につがる市を訪れてもらおう、そして市のファンになってもらい、やがては就農者を増やしていこうということが、このアンテナショップの目的です。

多摩市PRプロモーション
多摩市では「もっと知名度を上げたい」「PRしたい」というニーズがあり、そこでSNSで広がるよう、多摩市在住の女子柔道家で五輪メダリストの松本薫さんを起用してキャンペーンを実施しました。
ここに挙げたのは取り組みの一部ですが、このような形で、主に地方自治体のお役に立つような仕事をたくさん進めています。
本連載「あなたの街の地方創生は順調ですか?」バックナンバー
第1回 意外と曖昧な「地方創生」の定義とは
第2回 「公民連携」が規模に左右されない強い自治体をつくる
第3回 第2期地方創生では「人口縮小との共生」が不可避
読売広告社の概要
1946年設立、現在業界第2位の広告会社グループ。日本を中心に海外にも拠点を置いている。特色ある部門として、地方創生に取り組む「ひとまちみらい研究センター」、広告会社流モノづくりを行う「次世代ものづくり研究所」、都市×生活者のマーケティングを行う「都市生活研究所」がある。

牧瀬 稔(まきせ みのる)さんのプロフィール
法政大学大学院人間社会研究科博士課程修了。民間シンクタンク、横須賀市都市政策研究所(横須賀市役所)、公益財団法人 日本都市センター研究室(総務省外郭団体)、一般財団法人 地域開発研究所(国土交通省外郭団体)を経て、2017年4月より関東学院大学法学部地域創生学科准教授。現在、社会情報大学院大学特任教授、東京大学高齢社会研究機構客員研究員、沖縄大学地域研究所特別研究員等を兼ねる。
北上市、中野市、日光市、戸田市、春日部市、東大和市、新宿区、東大阪市、西条市などの政策アドバイザー、厚木市自治基本条例推進委員会委員(会長)、相模原市緑区区民会議委員(会長)、厚生労働省「地域包括マッチング事業」委員会委員、スポーツ庁参事官付技術審査委員会技術審査専門員などを歴任。
「シティプロモーションとシビックプライド事業の実践」(東京法令出版)、「共感される政策をデザインする」(同)、「地域創生を成功させた20の方法」(秀和システム)など、自治体関連の著書多数。
牧瀬稔研究室 https://makise.biz/

%20(1).png)