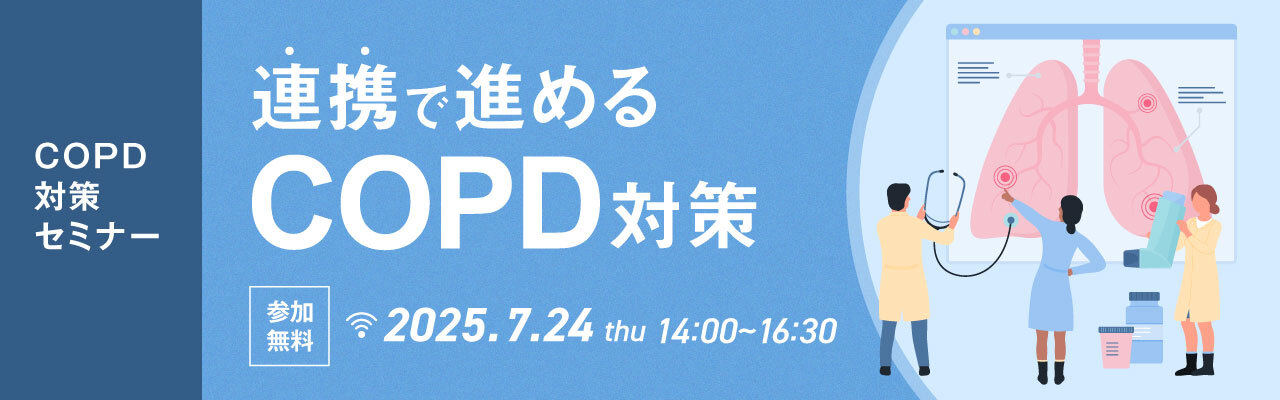「削減ありき」でヨコ並び“地方議会改革”の歴史
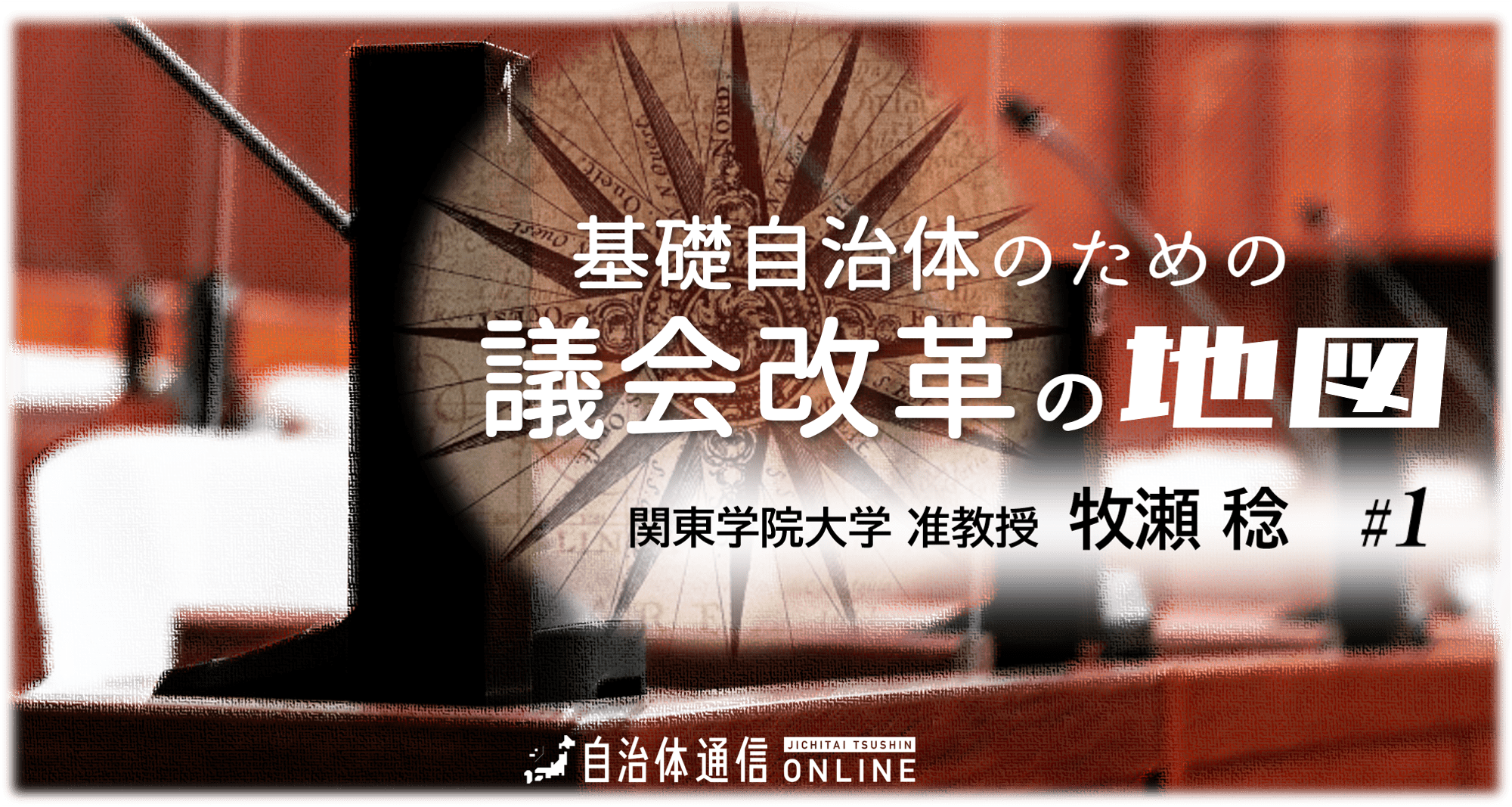
【自治体通信Online 寄稿連載】基礎自治体のための議会改革の地図①(関東学院大学法学部准教授/社会情報大学院大学特任教授・牧瀬 稔)
「議員定数削減が地方議会改革の前提となっているが、これは間違っている」―。多数の自治体の政策アドバイザーを務めるなど“自治体の現場”に精通する筆者が地方議会改革の行方を展望します。第1回はこれまでの地方議会改革の歴史を検証します。
【目次】
■ 縮小・削減・廃止は改革か?
■ 875分の477
■ 新聞報道で見る潮流
■ 基礎自治体での初出は1989年
■ 具体化に移行するのは90年代
縮小・削減・廃止は改革か?
近年、ほぼすべての議会で何かしらの議会改革が行われている。この連載では基礎自治体における地方議会改革の意味や歴史を振り返り、“これから”について考察してみたい。
ところで、議会改革という4文字には、さまざまな意味が含まれている。
下のケーススタディは各議会のホームページなどから抽出した「議会改革の意味」になる。さまざまな議会改革があることが理解できる。
ケーススタディ
~自治体によって異なる「議会改革の定義」~
※自治体ホームページなどから抜粋(黄色マーカーは筆者註)
ケーススタディ①
住民の皆さんに(中略)身近な政治の舞台へ関心を持っていただくだけでなく、住民の皆さんとともにまちづくりに参加できるような議会をめざした取り組みが行われています。このような取り組みのことを「議会改革」と言います。(北陸の基礎自治体)
ケーススタディ②
議会としての機能を十分に発揮できる改革の推進が必要との観点から(中略)「議員定数の削減」、「政務活動費の使途状況の公開等」、また「議会基本条例の制定」などの議会改革を進めてきたところです。(東日本の基礎自治体)
ケーススタディ③
地方分権が名実ともに加速し、市長事務部局等の執行機関の改革が進む中、市議会として(中略)さらに本格的、積極的な議会改革に取り組み、住民の代表機関である議会の活動を住民に理解が得られるよう開かれた議会運営の構築を目指すため議会改革に取り組みました。(関東の基礎自治体)
ケーススタディ④
「開かれた議会」「議会の機能強化・活性化」「経費節減」「公正性・透明性の確保」に向けて、議会改革に取り組んできました。(西日本の基礎自治体)
多くの場合は具体的な議会改革として「議会ホームページの開設」「政務活動費領収書の公開」「市民と議会の集いの開催」など、議会と議員活動の透明性確保や住民理解の向上についての前向きな取り組みを掲げる一方で、「議員定数の削減」「議長公用車の廃止」「議員報酬等の減額」などが挙げられている。
筆者が捉える議会改革の意味は、読んで字のごとく「議会を改革すること」である。改革とは「よりよくあらためること」と辞書にある。改革という言葉には、縮小や削減という意味は含まれていないと理解するのが一般的だ。
しかし、かつての議会改革は議員定数の削減をはじめ、何かにつけて削減や縮小と言う思考が強かったように感じる。
議会をよりあらためた結果として、議員定数の削減ならば理解できる。ところが、少なくない議会は、議員定数削減を前提として議会改革を進める傾向が見られる。
これは間違っているだろう。
繰り返しになるが、議会改革とは「議会をよりよくあらためること」である。この視点で考えるならば、議員定数の増加という観点もあるだろう。
875分の477
情報提供の意味で言及すると、「議会改革」という4文字が条例名に使われているのは愛荘町(滋賀)の「愛荘町議会改革条例」と芽室町(北海道)の「芽室町議会改革諮問会議設置条例」がある。
もちろん議会基本条例の条文では「議会改革」という言葉が盛り込まれている。あくまでも条例名に限定して「議会改革」という4文字があるのは2事例のみである。
愛荘町条例は「町民に身近な政府として議決機関ならびに監視機能を発揮するため、議会の政策立案機能を高め議会および議員の活動の活性化と充実に必要な議会運営の理念と改革事項を定め、町民が持続的で安心して暮らせるまちづくりの実現に寄与する議会に向けて取り組むことを目的」としている(同条例第1条より抜粋)。
芽室町条例は「芽室町議会基本条例第20条の規定に基づく附属機関として、芽室町議会改革諮問会議を設置し、その組織及び運営に関することを定める」ことが趣旨となっている(同条例第1条より抜粋)。
鹿児島大学司法政策教育研究センターが提供している「全国条例データベース」(https://elen.ls.kagoshima-u.ac.jp/ )を活用すると875の議会基本条例があることがわかる。
さらに「議会改革」をキーワードに検索をかけると、477の議会基本条例が抽出される。
たとえば、戸田市(埼玉)の「戸田市議会基本条例」は第25条の見出しが「議会改革の推進」である。条文は「議会は、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする」と明記している。
相模原市(神奈川)の「相模原市議会基本条例」は第22条が「議会改革」という見出しであり、条文は「市議会は、社会情勢その他の変化に迅速かつ適切に対応するため、議会の改革に不断に取り組むよう努めるものとします」となっている。
この“477”という数字の受け取り方は人により異なるだろう。
筆者は、875の議会基本条例全体のおよそ半分ほどにしか議会改革という文言が書き込まれていないという事実に、やや驚いた。もっと多くの議会基本条例に議会改革を書き込まれていると思い込んでいた。
新聞報道で見る潮流
「議会改革」という4文字は、いつから使われるようになったのだろうか。過去の新聞記事から検討した。その結果は、下のグラフを参照していただきたい。使用した新聞は「朝日新聞」「毎日新聞」「読売新聞」「産経新聞」の全国紙4紙。何回か波があることが理解できる。

過去の新聞記事を確認すると、「議会改革」の4文字がはじめて登場したのは、1985年6月28日の朝日新聞(東京夕刊)である(もっと古くから登場している可能性はある。4紙に限定した調査結果である)。
同記事の見出しは「都政へ私の期待、私の注文 都議選告示、各界に聞く」である。
そのなかで、日本婦人有権者同盟会長の紀平悌子氏(元参議院議員)が「今度の選挙は都議会改革のチャンスにすべきだと思います。過去4年間、情報公開や定数是正、消費者行政、婦人の地位向上などの点で、各候補がどんな仕事をしてきたか、じっくり判断したいと考えています」とコメントしている(下線は筆者註)。
この発言の中に「議会改革」という4文字が登場している。。
基礎自治体での初出は1989年
1980年代後半には、何回か議会改革という言葉が登場している。しかし、これらの議会改革の多くは海外の議会改革である。
例えば、1987年は台湾「議会改革めぐり野党が蒋総統の演説を妨害、中断させる異例の事態」である。
1988年は「ソ連の大幅人事異動、全面改革へ照準 新議会制をPR」である。「台湾国民党が議会改革案を採択」という見出しの記事もある。
その中で1989年12月3日の朝日新聞に「『逆風まだ」保守系4人減 久留米市議補選」 の記事に議会改革という言葉が登場している。これは日本の地方議会を対象としている。
同記事の一部を引用・抜粋すると「社会党久留米総支部の野口健一委員長は『市議会改革という地域選挙だったが、消費税廃止の訴えにも市民の関心が高いことを、街頭演説などでひしひしと感じた』」とある(下線は筆者註)。
具体化するのは90年代
議会改革という言葉は1980年代に登場していたことが理解できる。しかし、この時代の議会改革は、海外の事例が中心である。たとえ地方議会を対象としても「スローガン」としての議会改革の意味が強い。
議会改革という言葉は見られつつあったが、具体的な取り組みまでは実施されなかったと考えられる。
しかし1990年代に入ると、議会改革を進める具体的な取り組みが起きてくる。次回では1990年代以降の議会改革を紹介する。
(「透明化 疑問符 対立~1990年代から2010年代の地方議会改革ヒストリア」に続く)

牧瀬 稔(まきせ みのる)さんのプロフィール
法政大学大学院人間社会研究科博士課程修了。民間シンクタンク、横須賀市都市政策研究所(横須賀市役所)、公益財団法人 日本都市センター研究室(総務省外郭団体)、一般財団法人 地域開発研究所(国土交通省外郭団体)を経て、2017年4月より関東学院大学法学部地域創生学科准教授。現在、社会情報大学院大学特任教授、東京大学高齢社会研究機構客員研究員、沖縄大学地域研究所特別研究員等を兼ねる。
北上市、中野市、日光市、戸田市、春日部市、東大和市、新宿区、東大阪市、西条市などの政策アドバイザー、厚木市自治基本条例推進委員会委員(会長)、相模原市緑区区民会議委員(会長)、厚生労働省「地域包括マッチング事業」委員会委員、スポーツ庁参事官付技術審査委員会技術審査専門員などを歴任。
「シティプロモーションとシビックプライド事業の実践」(東京法令出版)、「共感される政策をデザインする」(同)、「地域創生を成功させた20の方法」(秀和システム)など、自治体関連の著書多数。
<連絡先>
牧瀬稔研究室 https://makise.biz/

%20(1).png)
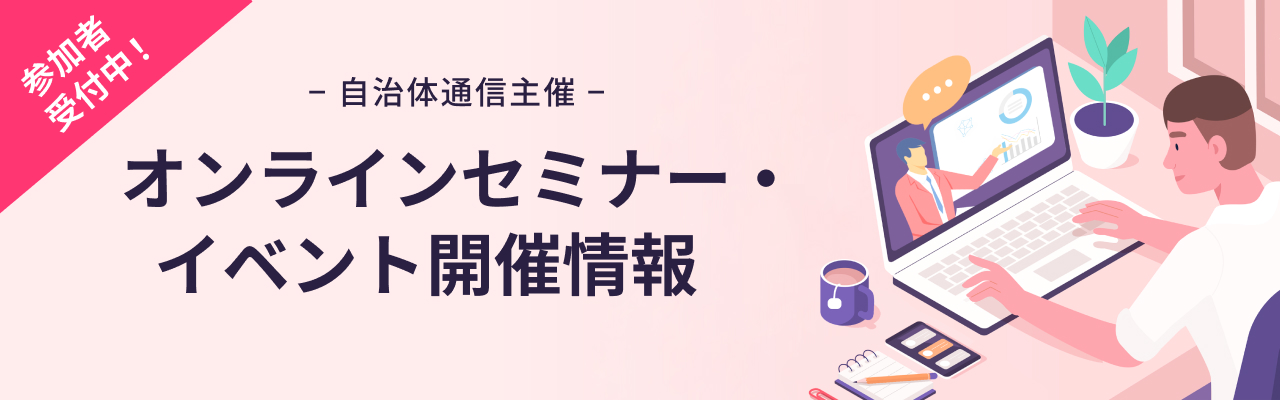
%20(2).png)