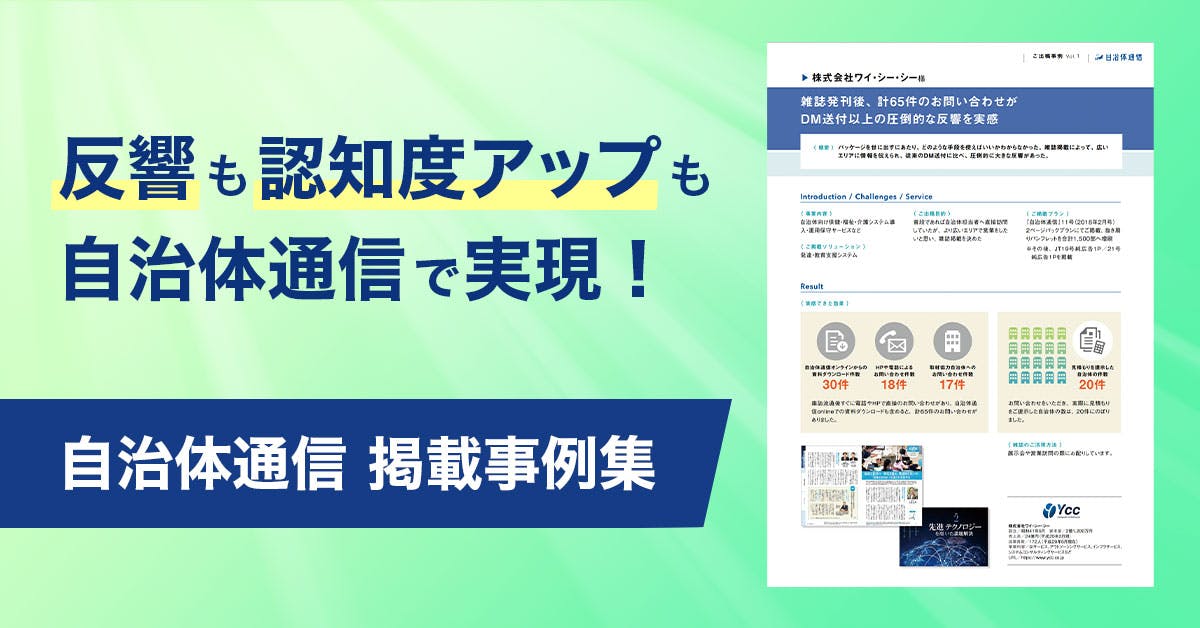【自治体事例】自治体の防災DXは「ハザードマップ」が鍵。最新事例から探る自治体の防災に関する取り組みとは?

自治体へのソリューション提案において、防災分野、特に「防災DX」はますます重要性を増しています。しかし、「自治体が具体的にどのような課題を抱えているのか分からない」「自社の技術をどう提案に結びつければ良いか悩んでいる」といったお声も少なくありません。
特に、住民の生命と財産を守るための基本情報である「ハザードマップ」は、多くの自治体が作成・周知の方法に課題を抱えており、新たなソリューションが求められている領域です。
・自治体が直面するハザードマップの具体的な課題
・デジタル技術を活用した課題解決の成功事例
これらの情報を通じて、自治体向けにサービスやソリューションを提供する企業様にとって、提案書づくりやアプローチの参考となれば幸いです。
「流域治水」が必要な理由
近年の気候変動は、世界的にさまざまな影響を及ぼしていますが、日本においては特に雨量の増加が危惧されています。近年の特徴としては短時間豪雨が増加傾向にあり、1時間あたり50mmを超える豪雨の発生件数は過去40年で約1.5倍に増加しています。こうした豪雨は特定の地域だけでなく全国的に発生しており、過去10年間で何らかの水害が発生した自治体は1700以上にのぼります。
さらに、国土交通省の試算によれば、今後、年間の平均気温が2℃上昇すると、降雨量は約1.1倍、河川などの流量は約1.2倍、洪水発生頻度は約2倍に上昇すると想定されています。そうなれば、ますます水害が発生しやすくなり、国民生活への影響も強まると考えられます。
これまで日本では、過去の雨量などをもとに、河川の堤防強化などの水害対策を進めてきましたが、今後は気候変動による想定以上の雨量への対応が求められます。そこで、堤防などで水流を食い止めるだけではなく、「水害が発生しても被害を軽減して住民生活を守る」という発想でまちづくりを進めることが必要になったのです。これが「流域治水」の根底にある考え方です。
従来のハザードマップには「空白域」が生じることも
水害から住民を守る「流域治水」において、自治体がすぐにでも実践できる取り組みが、水害リスク情報の発信です。なかでも、ハザードマップの公表はその代表例と言えるでしょう。国土交通省が運営する「ハザードマップポータル」は、誰でもアクセスできるうえ、地域を指定すれば全国各地の詳細なハザードマップを表示することができます。自治体のなかには、国交省のハザードマップを用いて、公式ホームページや防災アプリなどで地域のハザードマップを発信している事例もあります。
しかし近年、国交省の浸水想定区域には指定されていないものの、浸水のリスクが高いハザードマップ上の「空白域」があることがわかってきました。というのも、ハザードマップは国が管理している一級・二級河川や湾岸区域での水害を対象にしているため、各自治体などが管理する中小河川の氾濫などの予測は反映されていないのです。
たとえば、令和元年の東日本台風の際、宮城県丸森町では中小河川に位置づけられていた川で氾濫が発生し、ハザードマップ上の「空白域」で浸水被害が起きました。この「空白域」の特定は、地域の実情に詳しい自治体だからこそできる取り組みです。このような中小河川の浸水想定区域に加え、浸水の発生頻度などを記したハザードマップを「水害ハザードマップ」と呼んでいます。
水害ハザードマップのつくり方
水害ハザードマップの作成手順については、国土交通省が発出している「水害ハザードマップ作成の手引き」に詳しく記載されています。ここでは、その要点を簡単にまとめて紹介します。
手順①利活用シチュエーションを決める
まずは、水害ハザードマップを「いつ・どこで・誰が」活用するのかを想定して作成する必要があります。この工程を最初に実施するのは、活用する住民像やシチュエーションをあらかじめ想定しておかないと、まったく活用が進まないという事態が考えられるからです。たとえば、外国人が多い地域で日本語しか記載のない水害ハザードマップを作成しても、住民に活用されず、本来の目的を果たせないからです。
具体的には、以下のような用途や目的を決め、発信する媒体などを選定する必要があるとされています。
【いつ】
- 平時での活用:普段から水害について検討し、防災の知識を身につけるという観点から作成する場合は、地域の水害について多様な情報を記載する(公共施設での配布物etc)
- 緊急時での活用:「自分のいる場所の水害リスク」と「どこに逃げるか」などの最低限の情報を記載する(避難情報の発信etc)
【どこで】
- 自宅:自宅の水害リスクがわかるような工夫が必要になる(各地区ごとの浸水想定マップetc)
- 自宅外(通勤、旅行など):自分の居る場所での水害リスクがわかる(防災アプリ活用etc)
【誰が】
- 一般:水害リスクを知るためには、「PCなどの情報機器の扱いに慣れている人」と「そうでない人、情報環境が整備されていない人」で情報の収集の仕方が異なることを想定し、各層に向けた媒体の選定(紙媒体、アプリの併用etc)
- 避難行動要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児など防災施策において特に配慮を要する方):多様な配慮事項が想定されるため、作成前に関係者との連携が必要(医療・介護施設でのBCP策定etc)
- 外国人:多言語対応が必要になる(多言語対応etc)
手順②作成範囲や縮尺を決める
実際にマップを作成する際には、最初に作成する範囲を決める必要があります。この範囲は市区町村などの境界線で区切らず、住民の生活範囲で区切ることが望ましいとされています。なぜなら、市区町村の境界近くで生活する住民にとっては、隣接地域の地形や浸水区域がわからないと、適切な避難行動が行えない可能性があるからです。
さらに、同一の流域に属している市区町村など、水害特性や避難経路などが似ている隣接自治体においては、複数市町村で1つの水害ハザードマップを共同して作成することも考えられます。
縮尺については、住宅や避難場所、避難経路などが判別できるよう、1/10,000~1/15,000程度より大きな縮尺が望ましいとされています。
手順③記載事項を決める
記載する事項は、大きく「必須項目」と「推奨される項目」に大別されます。それぞれの事項は以下の通りです。
【必須項目】
- 想定最大規模の水害に係る浸水想定区域と浸水深
- 津波災害警戒区域と津波基準水位
- 土砂災害警戒区域
- 早期の立退き避難が必要な区域
- 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
- 地下街等(建設予定又は建設中を含む)、要配慮者利用施設、大規模工場等
- 水位観測所等の位置(映像が提供されるCCTV等を含む)
【推奨項目】
- 浸水継続時間が長い区域
- 海岸線への津波到達時間
- 浸水到達時間
- 地盤高(標高)
- 排水ポンプ場
- 防災関係機関(役場、警察、消防、病院)
- 防災備蓄倉庫
水害ハザードマップの活用事例
■東京都:「東京都防災アプリ」
東京都では、防災アプリを導入し、都民が無料で使用できるように多様な情報を発信しています。このアプリの特徴は平時から防災情報を学べるコンテンツや、日頃から備えておきたい備品などの情報から、災害時に即時に使用できるマップなど、網羅的に防災情報を取得できる点にあります。
水害においては、3D都市モデルで高潮浸水リスクが確認できるほか、GPSと連動して自分がいる地域の浸水状況がひと目でわかるアニメーションなどの機能を搭載し、子どもから高齢者までわかりやすい設計になっています。
■横浜市:「わいわい防災マップ」
横浜市(神奈川県)では、洪水・内水・高潮の3つのハザードマップを1枚の地図に落とし込んだ水害ハザードマップを「わいわい防災マップ」というホームページ上で公開しています。1時間あたり153㎜の想定される最大規模の降雨により、下水道管や水路からの浸水が想定される区域や、浸水する深さなどの情報がわかるようになっています。
上記の事例のように、近年はアプリやホームページを活用した水害ハザードマップの提供が増えてきました。一方で、移動手段が限られている高齢者や、即時避難が難しい障がい者などに対しては、外に避難するのではなく、建物の上階に避難する「垂直避難」などを推奨する自治体もあります。

水害ハザードマップで避難の実効性を高めよう
気候変動によって、いつ・どこで豪雨に見舞われるのか予測が困難になりつつあり、その被害も激甚化の一途を辿っています。台風などが発生していなくても、線状降水帯が発生すれば、短時間で極端な降水量を記録し、河川の氾濫や浸水などの被害を生みます。こうした被害を堤防などで完全に防ぐことはできません。今後は浸水想定区域などを見直し、住民と共有しながら、地域における治水のあり方を再検討する「流域治水」に基づいた対策が求められます。
その第一歩が、水害ハザードマップを活用した避難経路の確保です。浸水リスクを詳細に把握できれば、地区ごとにどのような経路を用いれば安全な場所に避難できるのかを想定できるようになります。そのうえで、より安全な避難経路を策定し、それを住民と共有することが重要なポイントになります。この経路を用いて、地域住民と避難訓練に取り組む自治体など活用事例も拡がりを見せています。
マイナンバーカードの普及が進んだいまこそ、こうした民間企業のアイデアや知見、技術を活用しつつ、さらなる職員の業務効率化や、住民サービスの向上を目指すことが、自治体には求められてくると言えるでしょう。
まとめ|防災DXの検討は企業と自治体の連携チャンス
防災DXを軸にした自治体の取り組みは、企業の技術やノウハウを活かせる余地が広がっています。
官民連携のヒントや、他の自治体の事例などにご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
参考事例資料のご提供や、サービスに関する活用事例についてのご紹介も可能です。
【参考】
国土交通省「「流域治水」の基本的な考え方~気候変動を踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う総合的かつ多層的な水災害対策~」
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf
国土交通省「水害ハザードマップ作成の手引き」
https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/saigai/tisiki/hazardmap/pdf/suigai_hazardmap_tebiki_202305.pdf
東京都「東京都防災ホームページ」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028747/index.html
横浜市「わいわい防災マップ」
https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/PositionSelect?mid=65