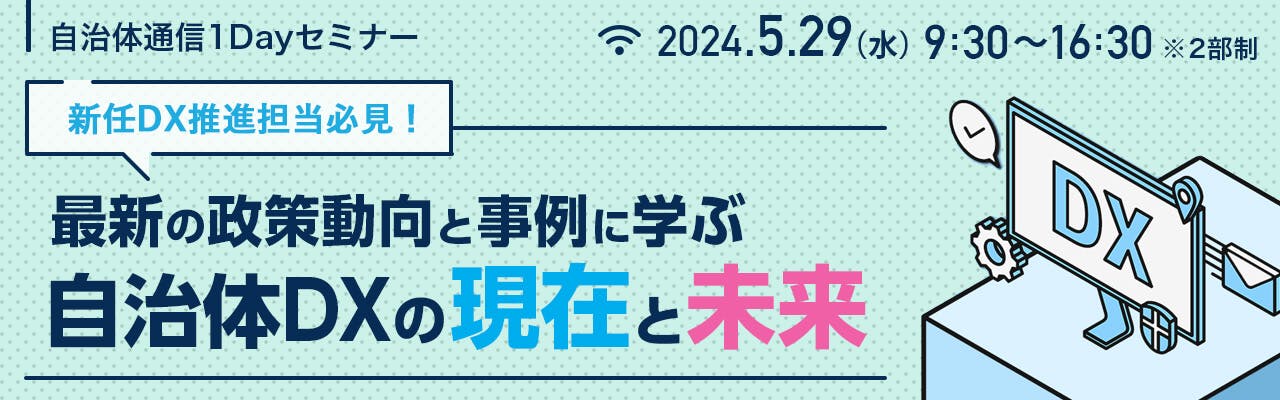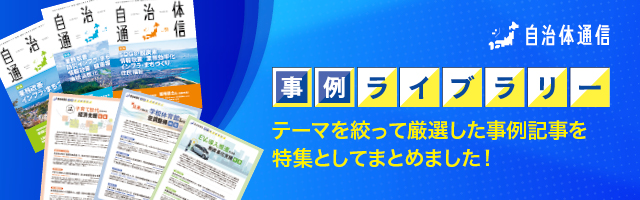神奈川県藤沢市の取り組み
無人航空機を使った災害・危機管理対策①
ライフセーバーの「目」と「声」となり、ドローンが海岸の安全を見守った
経済部 観光シティプロモーション課 主幹 木村 嘉文
※下記は自治体通信 Vol.28(2021年2月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。
災害や事故の発生時には、迅速な現場状況の確認や人命救助が自治体に求められるが、海や河川、山中では、ときに、人が立ち入りにくい場所での活動が求められることも多い。こうしたなか、藤沢市(神奈川県)では、ドローンを活用した海岸パトロールを実施した。パトロールにドローンを活用した経緯や、その成果について、観光シティプロモーション課の木村氏に聞いた。

例年より少ない数の人員で、海岸を監視することに
―藤沢市では海岸の安全を守るために、どのような取り組みを行っていますか。
毎年、「藤沢 海・浜のルールブック」という夏期の海岸利用ルールを作成、運用しています。これは、海水浴場の開設を前提に神奈川県が定めるガイドラインにもとづくものです。しかし令和2年は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、神奈川県が「海水浴場を開設しない」と発表。これにより、海の家や関連施設が設置されないことになりました。ただ、毎年約150万人が訪れる当市の片瀬海岸には、やはり一定数の人が訪れることを予測。そこで、市独自の海岸利用ルール「夏期海岸藤沢モデル2020」を策定し、運用することにしたのです。
―どのような内容なのでしょう。
たとえば、マリンスポーツを楽しむ人と海水浴客の接触を防ぐために、海上の利用エリアをすみ分けました。また、民間団体の協力でライフセーバーの活動拠点も設置されることに。しかし、ライフセーバーの数は例年よりも少なく、限りある人員で広い海岸をいかに監視するかが課題となりました。そうしたなか、慶應義塾大学でドローンの運用を研究するコンソーシアムからドローン活用の提案を受けました。さらに、神奈川県の支援も得ながら、7月18日から約3週間にわたり、実験的な意味合いも兼ね、ドローンを活用した海岸パトロールを実施することになったのです。実際の運用では、消防分野でのドローン活用で豊富な実績があるJDRONEの支援を受けました。「人が多い砂浜の上を飛行させない」といった安全性を考慮し、実運用を開始できました。
―どのようにパトロールを行ったのですか。
1時間に1回、片瀬海岸西浜の海岸1.2㎞にドローンを専門のパイロットが飛行させました。ドローンに搭載された最大200倍ズームが可能なカメラが陸上の様子を撮影し、ライフセーバーが監視するのです。その際、禁止エリアでマリンスポーツを行っている人がいれば、スピーカーを搭載したドローンで注意を呼びかけます。このほか、浮力体を投下することで溺者救出を支援するドローンも訓練で使用。浮力体は水に落ちると膨らむ特殊なもので、「ドローンの実用性は活用次第で大きく広がる」ということを実感しました。

遠方の禁止行為にも、スピーカーで注意を促せた
―実際にドローンを活用したパトロールを実施して、どのような効果を感じましたか。
多くのライフセーバーが、「人の目や声が届かない場所も監視できた」と、ドローンの有効性を実感したそうです。たとえば、「離岸流(※)が発生しそうなので、沖の方も見てきてほしい」といったライフセーバーからパイロットへのリクエストは日を追うごとに増え、ライフセーバーのニーズにドローンが応える場面が多くありました。また、落雷があってライフセーバーが海へ入れないときも、ドローンが海上を監視し、泳いでいる人がいないかどうかを確認できました。このほか、対岸の江の島の岩場で、禁止されているバーベキューをしている人をドローンが発見したことも。その場所まで人が移動するには時間がかかりますが、ドローンがスピーカーを使ってすぐに注意できました。
※離岸流 : 海岸に打ち寄せた波が沖に戻ろうとする時に発生する強い流れ
―海岸の安全対策に関する今後の方針を聞かせてください。
コロナ禍が収束し、本来のように海水浴場が開設されることがもちろん望ましいですが、海岸パトロールにドローンを活用した実績を活かし、今後も海岸の安全を守っていきたいです。また、今回の取り組みを通して得られた経験や、ドローン運用に関するデータを広めることで、海岸の安全に限らず、広く災害・危機管理対策の強化につなげられたらと考えています。
支援企業の視点
無人航空機を使った災害・危機管理対策②
情報収集から救助支援まで、実用の幅は大きく広げられる
ソリューション営業部 部長代行 天野 武正
ソリューション営業部 法人営業グループ 安心院 日向
※下記は自治体通信 Vol.28(2021年2月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。
前ページでは、海岸のパトロールにドローンを活用した藤沢市(神奈川県)の事例を紹介した。ここでは、同市のドローン運用を支援したJDRONEに取材。災害・危機管理分野におけるドローンの活用状況や、活用のポイントについて、同社の担当者2人に聞いた。


地形データの収集で、詳細な土砂被害推定にも寄与
―自治体の災害・危機管理対策におけるドローンの活用状況を教えてください。
安心院 実際には、まだ活用が少ないのが現状です。しかし、ドローンによる空撮影像がテレビで放映されるようになり、災害・危機管理対策への活用に関心をもつ自治体は増えています。ドローンは、人が入り込めない危険な場所に入れるだけでなく、ヘリコプターが航空法の規定で飛行できない高度150m以下の高さで機動的に飛行できるのが強みです。
また、平時においても、災害対策として活用することが可能です。
―どのような活用が想定できるのでしょう。
安心院 たとえば、土砂災害や洪水の危険がある指定箇所の空撮です。これまでも、災害が発生する可能性が高い場所は航空撮影によって特定できていました。ドローンではさらに、低空でより詳細に地形のデータを収集することが可能。そのデータから、「どのくらいの量の土砂が流れ出す恐れがあるのか」といった、さらに詳細な被害を推定することが可能です。
―実際にドローンを効果的に活用するには、どのようなポイントがありますか。
安心院 まずは、実運用に備え、飛行を想定する場所の事前調査を行うことです。ドローンのパイロットは画面の映像だけを見て操縦するので、機体の先に障害物がないかどうかを把握しておく必要があります。場所によってはドローンに発信する電波が届かないこともあり、機体の整備が必要になることもあるでしょう。こうした準備を含め、ドローン活用には専門家の支援が必須です。そこで当社では、ドローンの実力を最大限に発揮できるよう、事前調査を含めた総合的な支援を行っています。

実運用の実績が評価され、神奈川県と防災協定を締結
―具体的にどのような支援を行うのでしょう。
天野 まず、機体をカスタマイズすることで、ドローン活用の幅を広げる支援を行っています。たとえば、災害時に住民が孤立した際、スピーカーとウインチを搭載したドローンを使えば、被災者に声をかけたり、紙とペンを渡して必要な物資を書いてもらったりすることが可能になるでしょう。
じつは、こうしたカスタマイズは、ただ機材を搭載すればよいわけではなく、専門的な技術や知識が必要なのです。たとえば、ドローンでは、機体を操縦する電波のほかに、映像や音声を伝送する電波を使いますが、これらの電波が混信すれば思い通りに操作できません。通信分野を含めた専門的な知見と、ドローン実運用の豊富な経験を積んできた当社だから可能な支援だと言えます。
安心院 当社ではさらに、ドローンのパイロットの育成も行っています。首都圏有数の広さをもつドローン飛行の訓練施設を所有しており、公的機関でも、警察や消防分野への育成支援実績が豊富です。
―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。
天野 導入に向けたコンサルティングから実運用まで、ドローンの活用に関する幅広い支援を行っていきます。当社の前身となった事業部は、平成26年からドローンの研究を開始し、実用に向けた実績を重ねてきました。こうした実績や知見が評価され、昨年は神奈川県と、ドローンを活用した情報収集や捜索活動などで協力する防災協定も結んでいます。今後も、災害・危機管理分野へのドローン活用を広めていきたいですね。

| 設立 | 令和元年7月 |
|---|---|
| 資本金 | 8,000万円(令和元年7月現在) |
| 従業員数 | 34人(令和元年11月2日現在) |
| 事業内容 | ドローンに関する導入コンサルティング、ソリューション開発、空撮サービス、航空調査、インフラ点検サービス、スクールなど |
| URL | https://jdrone.tokyo/ |
| お問い合わせ電話番号 | 03-4236-0080(平日9:00〜18:00) |
| お問い合わせメールアドレス | contact@jdrone.tokyo |
ソリューションの資料をダウンロードする